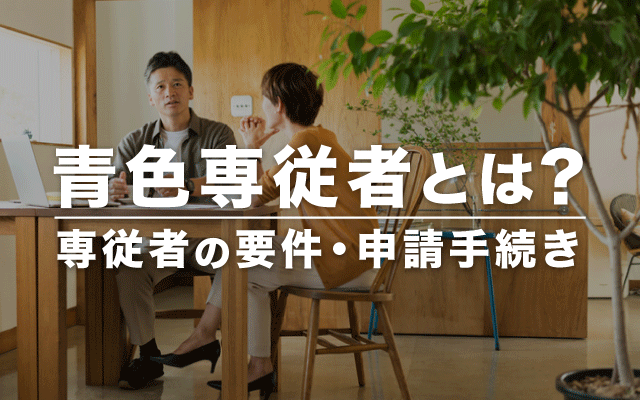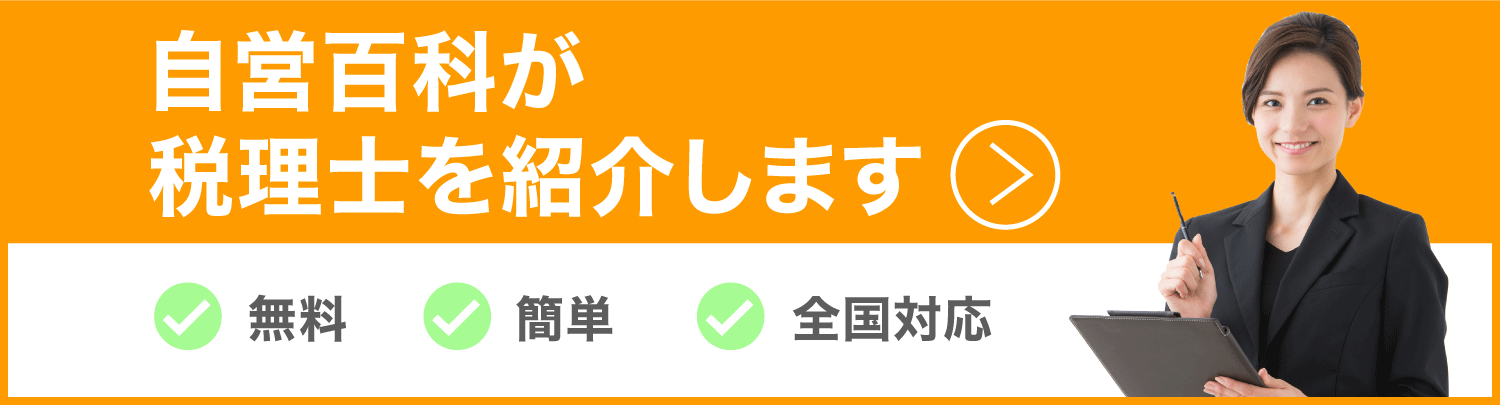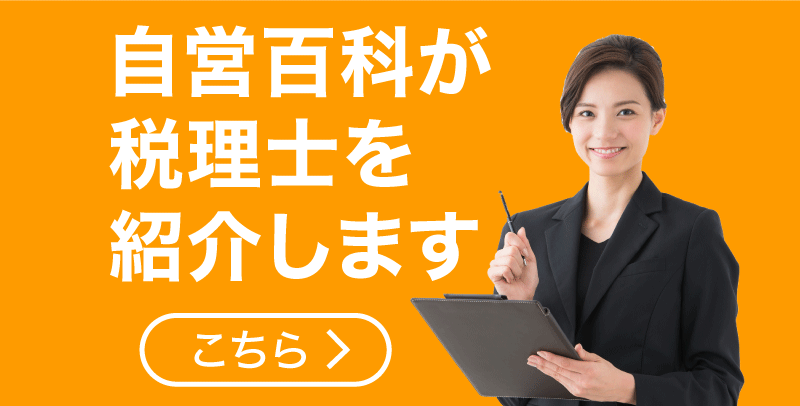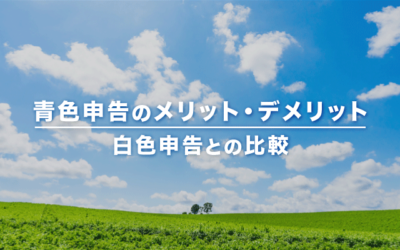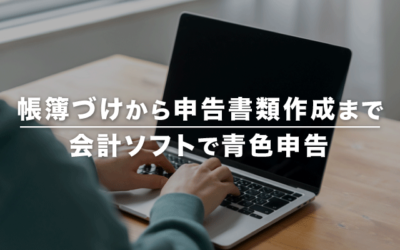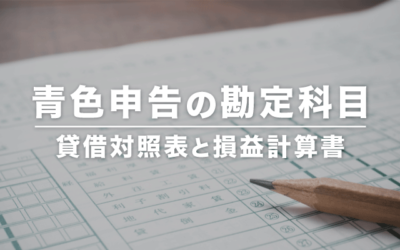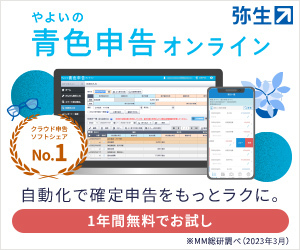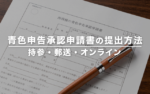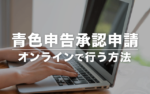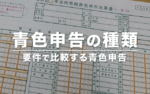個人事業主が家族に対して給与を支払っても、通常は経費にできません。しかし、青色申告の個人事業主は、条件を満たすことで「専従者給与」として経費計上できます。青色事業専従者の条件や届出方法などを初心者向けに解説します。
目次
専従者給与とは?【必要経費の勘定科目】
青色申告の個人事業主は、以下の条件をどちらも満たすことで、親族に支払った給与を「専従者給与」という勘定科目で必要経費にできます。ちなみに、専従者給与の消費税区分は不課税(通勤手当のみ課税)です。
専従者給与を計上できる条件
- 給与を支払った親族が「青色事業専従者」に当てはまる
- 個人事業主が所定の届出書を提出している
親族とは、厳密には6親等以内の血族(本人と血の繋がりがある人)と配偶者、3親等以内の姻族(配偶者と血の繋がりがある人)のことをいいます。
>> 「事業的規模の不動産所得」と「事業所得」の違いとは?
青色事業専従者の条件

「青色事業専従者」とは、ざっくりいうと、青色申告をしている個人事業主が抱える家族従業員です。具体的には、下記の条件をすべて満たす親族が該当します。
青色事業専従者に該当する親族の条件
- 事業主本人と「生計を一にする配偶者その他の親族」である
- その年の12月31日時点で「15才以上」である
- 青色申告者の事業に「年間6ヶ月を超えて」もっぱら従事している*
* 一定の場合には、従事可能な期間の半分を超えていればよい
①と③の条件がちょっとわかりづらいので、以下で詳しく解説します。
「生計を一にする配偶者その他の親族」とは
この条件については、「生計を一にする」という言葉の意味と、「配偶者その他の親族」の範囲に分けて解説します。
「生計を一にする」とは
国税庁によると「生計を一(いつ)にする」とは「日常の生活の資を共にすること」をいいます。同居している親族は、大抵これに該当します。
なお、国税庁によれば、別居している親族でも「生活費や学費などを常に送金しているとき」や「単身赴任や留学などの余暇には起居を共にしているとき」は、生計を一にしていると言えるようです。
生計を一にするとは – 国税庁
「配偶者その他の親族」とは
「配偶者その他の親族」とは、配偶者・6親等以内の血族及び3親等以内の姻族を指します。たとえば、夫・妻・子供・父・母・孫・祖父・祖母・いとこなどが該当します。
親族と扶養親族の違い・親等の数え方など
「年間6ヶ月を超えて専ら従事している」とは
原則として、年間で6ヶ月を超える期間、青色申告者が営む事業に「専念」して働いていればOKです。法令上は、これを「専ら(もっぱら)従事」といいます。
ただ、何をもって「専念」とするかは、明確な基準がありません。仕事の内容・量・業態などを総合的に考えて判断しましょう。
専念とは言えないケース(所得税法施行令165条2項)
- 学校に通っている
- 他に職業がある
- 老衰や心身の障害で、働く能力がほとんどない
※いずれも、事業に問題なく専念できているケースは除く
上記は「少なくとも、このケースは専念しているとは言いがたいですよ」という例示にすぎません。たとえば、家事や育児に専念している配偶者は、上記のどれにも当てはまりませんが、事業に専念しているとは言えません。
ちなみに、従事可能な期間の2分の1を超えて働いていれば、6ヶ月を超えていなくても青色専従者になりえます。たとえば、以下のようなパターンが考えられます。
6ヶ月を超えていなくてもOKなパターン(主な例)
- 8月末で会社を辞めた家族に、9月~12月の4ヶ月間フルで働いてもらった
- 12月に新規開業し、1ヶ月間フルで働いてもらった
- 夏場の3ヶ月しか営業していない店で、2ヶ月間フルで働いてもらった
青色事業専従者に該当しないケース
親族が青色事業専従者の条件を満たさない場合、「専従者給与」は計上できません。微妙なケースでは税務署が個別の状況に応じて判断するので、心配な場合は事前に税務署の窓口で相談してください。

通常の従業員として雇う場合
15才以上の親族であっても、生計を一にしていない場合は、青色専従者の条件から外れます。しかし、通常の従業員として雇うことは可能なので、その給与は「給料賃金」として経費にできます。この場合、労働基準法で保護される「労働者」扱いになります。
たとえば、自分の父親と二世帯住宅で暮らし、それぞれ独立して生計を立てている場合は、生計を一にしていることになりません。この父親に事業を手伝ってもらい、その給与を経費にしたいならば、通常の従業員として雇う必要があります。
まったく経費にできない場合
生計を一にする親族であっても、15才に満たなかったり、専ら従事している期間が足りなかったりすると、専従者給与として経費にはできません。報酬を支払っても、ただの「おこづかい」とみなされ、必要経費にはできないということです。
たとえば、年間を通じて6ヶ月間だけお店を開いている場合、専ら従事すべき期間は3ヶ月超です。事業主からの仕送りで生活している大学生の息子が、夏休みの2ヶ月間だけこのお店でバイトをしても、そのバイト代は経費にできません。
専従者給与を計上するために必要な手続き
専従者給与を経費計上するには、以下の届出書を税務署へ提出しておく必要があります。いちど提出したら、内容に変更が無い限り毎年提出する必要はありません。
| 給与支払事務所等の開設届出書* | 初めて人を雇った日から1ヶ月以内 |
|---|---|
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 初めて専従者を雇った日から2ヶ月以内 ※もしくは、その年の3月15日まで |
* 通常の従業員を雇っていて、すでに提出済みであれば改めて提出する必要はない
新たに専従者が増えたり、給与の金額が変わったりすることもあるでしょう。その際は、できるだけ速やかに、青色事業専従者給与に関する「変更届出書」を提出しなければなりません。
源泉徴収の義務について
青色専従者に給与を支払ったら、源泉徴収をしなくてはいけません。原則として、翌月10日までに「所得税徴収高計算書」を作成して、銀行などで納付します。もし、給与が少なく源泉徴収額が0円でも、この書類は提出する決まりです。
従業員が常時10人未満なら「源泉所得税の納期の特例」の申請ができます。この承認を受けると、所得税徴収高計算書の納付は年2回で済みます。
専従者給与の適正額はいくら?
専従者給与に上限の定めはありません。ただ、税務署が「給与として不相応な金額」と判断した場合、その部分は必要経費にできないので注意しましょう。
労務の対価として相当な金額とは
- 従事した期間、業務内容、業務量、拘束時間に見合った額
- 事業の規模、業績に見合った額
- 同種・同規模の仕事を行う一般労働者と同程度の額
ちなみに、一般的には「月80,000円」ぐらいに落ち着くことが多いようです。多く支給すれば、そのぶん経費を増やせますが、事務的な負担も増えます。とくに、月88,000円以上支給すると所得税の源泉徴収が必要になります。
専従者給与の仕訳例
たとえば、青色事業専従者の妻に10万円の給与を現金で支給した場合、以下のように記帳します。源泉徴収する場合は、その天引き分を「預り金」としておきます。ここでは数字をわかりやすくするため、実際の源泉徴収税額に近い数字で表記します。
複式簿記の記帳例
| 日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 20XX年5月25日 | 専従者給与 100,000 | 現金 99,000 | 妻 5月分 専従者給与 |
| 預り金 1,000 | 源泉所得税 |
青色申告55万円控除や65万円控除をねらう事業者のみ、複式簿記で記帳する必要があります。青色申告10万円控除の事業者は、以下のように単式簿記で記帳して構いません。
単式簿記の記帳例
| 日付 | 預り金 | 専従者給与 | 現金残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 3,300,000 | ||||
| 20XX年 5月25日 |
-100,000 | 3,200,000 | 妻 5月分 専従者給与 |
|
| +1,000 | 3,201,000 | 源泉所得税 (預かり) |
なお、専従者給与の消費税区分は「不課税」です。ただし、通勤手当のみ「課税」の扱いになります。
【注意点】配偶者控除・扶養控除とは併用できない!
事業専従者は「配偶者控除」と「扶養控除」の対象になりません。ですから、専従者扱いすることで、かえって損になることもあります。
配偶者控除と扶養控除の控除額
| 配偶者控除 | 扶養控除 |
|---|---|
| 納税者の所得によって控除額が決まる | 扶養親族の年齢などで控除額が決まる |
| 1,000万円超:控除なし 950万円~1,000万円:13万円控除 900万円~950万円:26万円控除 900万円以下:38万円控除 |
70歳以上の同居老親:58万円控除 70歳以上:48万円控除 23~69歳:38万円控除 19~22歳:63万円控除 16~18歳:38万円控除 16歳未満:控除なし |
配偶者控除・扶養控除で充分にメリットが得られる事業者は、あえて専従者の届出をしないという選択もできます。専従者給与と配偶者控除・扶養控除を比べて、どちらが得になるか計算してみてください。
まとめ
下記の条件を満たす親族は「青色事業専従者」に該当します。事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していれば、青色事業専従者に支払った給与を「専従者給与」として必要経費にできます。
青色事業専従者に該当する親族の条件
- 事業主本人と「生計を一にする配偶者その他の親族」である
- その年の12月31日時点で「15才以上」である
- 青色申告者の事業に「年間6ヶ月を超えて」もっぱら従事している*
* 一定の場合には、従事可能な期間の半分を超えていればよい
専従者の条件を満たさない場合、同一生計の親族は「ただの家庭内のお手伝い」とみなされ、給与を支給しても必要経費にはできません。生計を一にしていない親族を雇う際は、通常の従業員として扱い、給与は「給料賃金」として経費にできます。
青色専従者給与のポイント
- 消費税区分は不課税(通勤手当のみ課税)
- 事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出
- 「給与支払事務所等の開設届出書」を一ヶ月以内に税務署へ提出(初回のみ)
- 月88,000円以上支給する場合は、所得税の源泉徴収が必要になる
- 給与として不相応な金額の場合、必要経費として認められないことがある
専従者給与として経費計上する場合、配偶者控除・扶養控除と併用できません。状況によって、専従者扱いはせずに、配偶者控除・扶養控除を受けたほうがよい場合もあります。