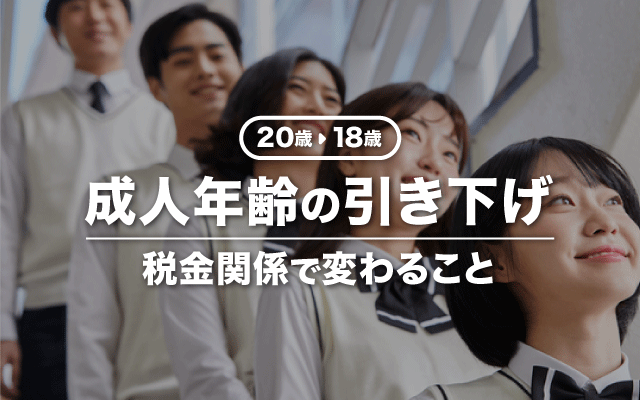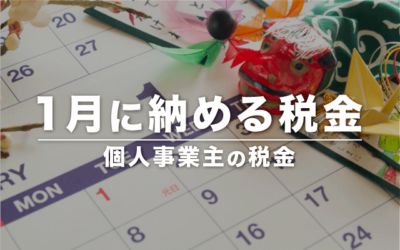目次
税金関連の変更点まとめ
2022年4月から、成人年齢が「20歳」から「18歳」に引き下げられました。これによって、税金関係のルールでも一部変更があります。
税金関連の主な変更点【成年年齢の引き下げ】
| 所得税 |
|
|---|---|
| 住民税 |
|
| 相続税 |
|
| 贈与税 |
|
税金関連の身近な変更点としては、「NISA(少額投資非課税制度)」の年齢制限引き下げが挙げられます。これは、所得税と住民税の両方に関係する変更です。
その他、住民税の非課税に関する変更は、たとえば「バイトで年間100万円くらい稼いでいる18~19歳」などに影響する可能性があります。また、相続税・贈与税の変更は、18~19歳あたりの人が「遺産相続」や「まとまった財産の贈与」を受ける際に関係します。
所得税
成人年齢の引き下げに伴って、「NISA(少額投資非課税制度)」の年齢制限が2023年から引き下げられます。NISAには、成人を対象とした「一般NISA・つみたてNISA」と、未成年を対象とした「ジュニアNISA」があり、3種類とも対象年齢が変わります。
NISAの対象年齢
| 2022年まで | 2023年から | |
|---|---|---|
| 一般NISA | 20歳以上が対象 | 18歳以上が対象 |
| つみたてNISA | 20歳以上が対象 | 18歳以上が対象 |
| ジュニアNISA | 19歳以下が対象 | 17歳以下が対象 |
2023年1月以降は、18歳から「一般NISA・つみたてNISA」の口座を開設できるようになります。より若い年齢から自由度の高い制度を利用できるようになるので、対象者にとっては嬉しい改正だと言えます。
成人年齢の引き下げ後も変わらないこと
所得税・住民税には、子供に関係する所得控除がいくつか存在します。これらは、そもそも「成年 or 未成年」を基準にした制度設計ではないので、成人年齢の引き下げ後も変更はありません。
子どもが関係する主な所得控除
| 社会保険料控除 | 1年間に納めた、本人や家族の社会保険料に関する控除 家族の年齢に関わらず、納めた金額を控除できる |
|---|---|
| 生命保険料控除 | 1年間に支払った、本人や家族の生命保険料に関する控除 家族の年齢に関わらず、支払った金額を控除できる |
| 扶養控除 | 16歳以上の扶養親族がいる場合に受けられる控除 成人年齢の引き下げ後も、年齢制限に変更はない |
| ひとり親控除 | シングルマザー・シングルファザーのための控除 そもそも子供の年齢に制限はない |
| 勤労学生控除 | 学校に通いながら働いている人のための控除 そもそも対象者に年齢制限はない |
「扶養控除」は、扶養親族の年齢に応じて控除額が変わる仕組みになっています(たとえば「16~18歳は38万円」「19~22歳は63万円」など)。この年齢の区切りについても変更はありません。
住民税
成人年齢の引き下げによって、住民税非課税の基準が一部変更されます。従来から、下記のどれかに該当する人は住民税が免除されていましたが、このうち「未成年者」の範囲が変わります。
住民税が課されない人(均等割も所得割も非課税の人)
- 生活保護の対象者のうち「生活扶助」を受けている人
- 前年の給与収入が190万円以下の未成年者など(厳密には「合計所得135万円以下」)
- 前年の給与収入がおおよそ100万円以下の人*
* 具体的な基準額は、地域や扶養の有無によって異なる
ここで言う「未成年者」の年齢は、これまで「20歳未満」でしたが、改正後は「18歳未満」になりました(その年の1月1日の年齢で判断する)。この変更によって「住民税を納める18~19歳の人」がちょっと増えることになります。
たとえば、前年の給与収入が110万円だったとしたら、住民税の課税・非課税は下記のような扱いになります。(給与以外に収入がある場合は、それらも含めた「合計所得金額」で考える必要があります)
住民税の課税・非課税(前年の給与が110万円だった場合)
| 令和4年度の住民税まで | 令和5年度の住民税から | |
|---|---|---|
| 20歳 | 住民税が徴収される | 住民税が徴収される |
| 19歳 | 住民税が課されない | 住民税が徴収される |
| 18歳 | 住民税が課されない | 住民税が徴収される |
| 17歳 | 住民税が課されない | 住民税が課されない |
※ 扶養親族などがいない会社員・アルバイトを想定しています
この改正は、2023年度(令和5年度)の住民税から適用されます。2023年度の住民税は「2022年分の所得」から算出されるので、今年の収入が高いと、来年はお給料から住民税が天引きされるかもしれません。
- 住民税の納付が必要になると言っても、がっつり稼いでいない限り、納税額がそこまで高くなることはない。たとえば、年収100万円を少し超えた程度なら、年額5,000円程度の「均等割」を納めるだけで済む場合も多い。
相続税
相続税に関しては、成年年齢の引き下げによって下記のような変更があります。
相続税に関する主な変更点
| 未成年者控除 | 相続人が未成年者の時、相続税から一定金額を差し引く制度 →年齢制限が「20歳未満」から「18歳未満」に変わった |
|---|
「未成年者控除」とは、簡単に言うと「未成年者」に課される相続税を軽減する制度です。これまでは「20歳未満」で相続等をした人が対象でしたが、2022年4月以降は年齢制限が「18歳未満」に引き下げられています。
贈与税
成年年齢の引き下げによって、贈与税には主に下記のような変更があります。
贈与税に関する主な変更点
| 特例税率 | 直系尊属からの贈与について、通常よりも有利な税率を適用できる制度 →18歳から適用可能になった |
|---|---|
| 結婚・子育て資金の 非課税制度 |
直系尊属から所定の方法で受け取った「結婚・子育て資金」が、1,000万円まで非課税になる制度 →18歳から適用可能になった |
| 住宅取得等資金の 非課税制度 |
直系尊属から受け取った「住宅取得資金」などが、原則1,000万円まで非課税になる制度 →18歳から適用可能になった |
| 相続時精算課税制度 | 年間2,500万円までの生前贈与について、贈与税を非課税にする代わりに相続税の課税対象とする制度 →18歳から適用可能になった |
これまで、上記はどれも「20歳以上」の人が父母や祖父母から贈与を受けた場合に利用する制度でした。しかし、成人年齢に引き下げに伴って、対象者の範囲が「18歳以上」に拡大されています。
税金以外で変わることは?
税金以外の面では、成人年齢の引き下げに伴って、下記のようなルールが変更されています。
成人年齢引き下げの影響(主な例)
| 18歳からできるようになったこと | 20歳にならないとできないこと (改正後も年齢制限が変わらないこと) |
|---|---|
|
|
* 親の同意が不要になった
なお、選挙権の年齢制限については、2018年からすでに「18歳以上」に改正されています。今回の成年年齢引き下げで、投票権に関する変更はありません。