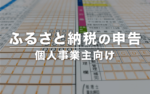2020年分の確定申告からは、控除に関する改正がいくつか適用されます。これらの改正は、ふるさと納税の「上限額」にも影響します。大きな影響が出るケースは稀ですが、念のため確認しておきましょう。本記事では、個人事業主に向けて説明します。
目次
「上限額」に影響する税制改正
2020年は、ふるさと納税の「上限額」に注意しましょう。下記のような改正の影響で、予期せず負担額が増えてしまうかもしれません。(本記事で「上限額」とは、実質2,000円の負担でふるさと納税ができる上限額のことを指す)
改正される主な控除
| 基礎控除 | 控除額が10万円アップする(所得2,400万円超の場合を除く) |
|---|---|
| 青色申告特別控除 | 控除額が10万・55万・65万の3パターンに変わる |
| 寡婦・寡夫控除 | 寡婦控除の要件が厳しくなり、寡夫控除は廃止される |
| 配偶者控除 | 要件が少しだけ緩和される (控除対象の親族の所得要件が38万円以下→48万円以下に上がる) |
| 扶養控除 |
多くの場合、改正の影響は些細なものです。が、新たに配偶者控除や扶養控除の対象になる人は特に注意しましょう。いずれにしても、今年は新型コロナの影響で所得が減少している人も多いので、改めて自分の「上限額」を確認しておくのが安心です。
【おさらい】ふるさと納税の仕組み
ふるさと納税は、任意の自治体に寄附をすることで、所得税と住民税が軽減される制度です。いわゆる「上限額」の範囲内で寄附をすれば、翌年に納める税金が「寄附した金額 – 2,000円」の分だけ軽減されます。

多くの自治体が、この寄附に対して「返礼品」を贈呈しています。なので、ひとまず「実質2,000円で高級なお肉やフルーツがもらえる制度」と認識している人も多いでしょう。
ただ、控除される金額には、その人の所得などに応じた上限があります。所得に対して寄附額が多すぎたりすると、実質的な負担が2,000円を超えてしまいます。ですから、寄附する金額は、実質負担が2,000円を超えない「上限額」におさめるのが一般的です。
なぜ控除の改正が影響する?
ふるさと納税の「上限額」を考える上で、重要なのは下記の2点です。
- 所得が多いほど、ふるさと納税の「上限額」も増える
- 他の所得控除が少ないほど、ふるさと納税の「上限額」は増える

①は、みなさんなんとなくご存知でしょう。注意したいのは②で、ふるさと納税のことだけを見れば、他の所得控除は言わば競合で、少ないほうがよいのです。そして、この所得控除で重要な改正があり、ふるさと納税もその影響を受けるというのが、本記事の主旨です。
とはいえ、他の控除額が10万円変わったところで、「上限額」はだいたい数千円変わるくらいです。たとえば基礎控除額が10万円増えることで、ふるさと納税の「上限額」がまるまる10万円減るというわけではありません。
ちなみに、ふるさと納税の「上限額」は下記の計算式で算出できます。実際には、役所や税理士に問い合わせたり、シミュレーションサイトで計算する人が多いと思うので、よく分からなくてもOKです。

【上限額一覧】目安をざっくり計算してみた!
2020年のふるさと納税の「上限額」について、基礎控除の控除額を48万円として、おおまかな目安を算出しました。試算の都合上、主要な所得控除しか適用していないので、あくまで参考程度にご覧ください。
下表の所得とは「収入 – 必要経費」の金額のことです。もし青色申告特別控除を受ける場合は、それも差し引いた金額で考えてください。また、ここで言う「独身」や「夫婦」とは、要するに「あなたは配偶者控除や扶養控除を受けますか?」という違いです。
【目安】実質2,000円の負担で寄附できる上限額
| 独身 | 夫婦 (配偶者控除) |
夫婦 + 子供1人 (配偶者控除・扶養控除) |
||
|---|---|---|---|---|
| 本人の所得 | 1,000万 | 259,000円 | 249,000円 | 239,000円 |
| 900万 | 229,000円 | 203,000円 | 193,000円 | |
| 800万 | 190,000円 | 174,000円 | 165,000円 | |
| 700万 | 165,000円 | 147,000円 | 136,000円 | |
| 600万 | 138,000円 | 121,000円 | 110,000円 | |
| 500万 | 112,000円 | 83,000円 | 74,000円 | |
| 400万 | 75,000円 | 61,000円 | 47,000円 | |
| 300万 | 53,000円 | 35,000円 | 26,000円 | |
| 200万 | 28,000円 | 14,000円 | 5,000円 | |
| 100万 | 7,000円 | 0円 | 0円 | |
※ 自己負担の2,000円を含む
たとえば、今年の所得が400万円程度になりそうなら、ふるさと納税は7万円くらいまでにしておくのが安心だということです(独身の場合)。ただ、この試算よりも多くの所得控除を適用する場合などは、さらに「上限額」が下がるので注意しましょう。
- 試算の設定
-
・「独身」は基礎控除と社会保険料控除のみ適用
・「夫婦」は、基礎控除と社会保険料控除に加え、配偶者控除を適用
・「夫婦 + 子供」は、さらに38万円の扶養控除を適用(住民税の控除は33万円)
・社会保険料控除は、家族の人数に応じた国民年金保険料と国民健康保険料を払ったものとして計算
・国民年金保険料は、2020年1月~12月の金額で計算
・国民健康保険料は所得の10%と仮定(ただし、814,000円を賦課限度額とする)
・住民税(所得割額)の税率は10%で計算
先述のとおり、控除の適用状況などによって「上限額」は大きく変動する可能性があります。詳細にシミュレーションしたいときは、税理士や、住んでいる市区町村の役所に相談しましょう。
上限額はどれだけ変わる? – 改正前と改正後の比較
先ほど試算した数値をもとに、改正の前後で「上限額」がどれだけ変わるか考えてみます。結論から言うと、控除額の変更だけで「上限額」が大きく変わることはほとんどありません。
たとえば、昨年も今年も所得が400万円で、基礎控除の改正の影響だけを受けたとします。この場合、下記のように「上限額」はほとんど変わりません。
上限額の変動(基礎控除改正の影響しか受けない場合)
| 2019年(改正前) | 2020年(改正後) |
|---|---|
| 78,000円 | 75,000円 |
※ 前述の「独身」の設定で試算
今回の設定では、基礎控除がアップしても「上限額」は3,000円ほどしか下がらない計算です。控除額が10万円増えたところで、ふるさと納税の「上限額」がまるまる10万円減るわけではないのです。
ちなみに、改正によって適用できる控除が増えたりすると、もう少し大きな差が出てきます。といっても、今回の改正で新たに配偶者控除や扶養控除の対象となる人は稀です。基本的に、所得の変動に注意するほうが重要だと考えておきましょう。
まとめ
2020年は、税制改正などの影響で、ふるさと納税の「上限額」が変わる可能性があります。それほど大きな影響が出ない場合も多いですが、下記に該当する人は気をつけておきましょう。
「上限額」が大きく変わるかもしれない人
- 新たに配偶者控除を受けられるようになった人
- 新たに扶養控除を受けられるようになった人
- 新型コロナの影響などで、所得が大きく減少する人
特に、所得の変動は「上限額」に大きく影響します。ふるさと納税をする際には、改めて「上限額」を確認しておきましょう。なお、金額を詳細にシミュレーションしたいなら、税理士や役所に問い合わせるのが確実です。
ちなみに、上限を超えてふるさと納税をしても「上限額」まではちゃんと控除されます。少しオーバーするくらいなら、大きな損につながるわけではないので、改正の影響をあまり受けない人は、それほど神経質になる必要はありません。