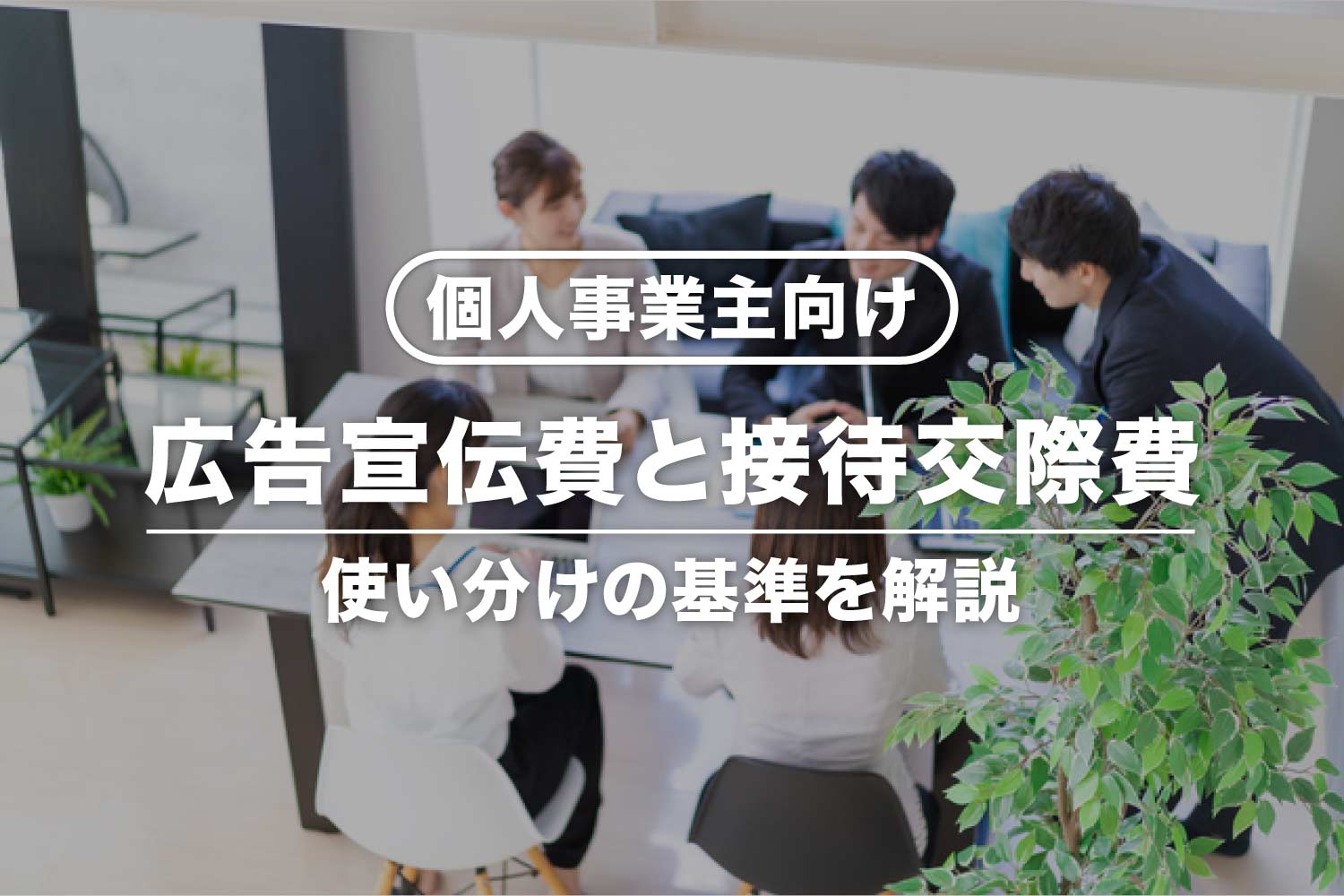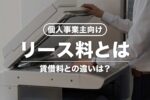個人事業主・フリーランス向けに、広告宣伝費と接待交際費の違いをまとめました。取引先との食事代やビジネス交流会の参加費など、ケース別で解説します。
目次
広告宣伝費と接待交際費の違い
広告宣伝費とは、その名のとおり「商品やサービスのプロモーションにかかった費用」の勘定科目です。一方、接待交際費とは、ひとことで言えば「取引先との関係構築のために使った費用」を経費計上するときに使う勘定科目です。
| 広告宣伝費 | 接待交際費 |
|---|---|
| 事業の宣伝にかかる費用 | 取引先との関係構築にかかる費用 |
| ・ウェブ広告の出稿費用 ・広告媒体への掲載費用 ・チラシやパンフレットの配布費用 ・ホームページの制作費用 など |
・取引先との飲食代 ・取引先とのゴルフ代 ・取引先へのお中元・お歳暮 ・結婚祝い・葬式香典 など |
ざっくり言うと、広告宣伝費は”不特定多数”への働きかけにかかる費用ですが、接待交際費には”特定の相手”との関係維持にかかる費用が該当します。
【大前提】個人事業主なら厳密な使い分けは不要!
個人事業主・フリーランスの場合、広告宣伝費と接待交際費を「こう使い分けないとダメ!」というルールはありません。どちらを使うか迷った場合は、自分なりのルールを決めて使い分けておけばOKです。
| 個人事業主 | 事業に必要な支出はすべて必要経費に計上できる →勘定科目の使い分けはそれほど重要でない |
|---|---|
| 法人 | 交際費として損金算入できる金額に上限がある →勘定科目を上手に使い分けないと損をする |
「〇〇は広告宣伝費で、〇〇は接待交際費」というルールを聞いたことがあるかもしれませんが、これらは基本的に法人企業(株式会社など)の会計ルールです。個人事業主も参考にできますが、厳密に従う必要はありません。
広告宣伝費と接待交際費の使い分け基準
前述の通り、個人事業主やフリーランスの場合、広告宣伝費と接待交際費をそれほど厳密に使い分ける必要はありません。とはいえ「自己流だと不安…」という方も多そうなので、参考までに法人の使い分けルールを紹介します。
交際費と広告宣伝費の使い分けについて、国税庁は下記のように説明しています。(これは法人のルールなので、個人事業主は参考にする程度でOKです)
引用……(前略)……カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用や次のような不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は、交際費等には含まれないものとされ、広告宣伝費となります。
要するに「得意先などにカレンダーや手帳を贈与する費用」や「不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用」は、交際費ではなく広告宣伝費にしてね、ということです。後者は、下記のような費用を指しています。
「不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用」の例
- 抽選で、一般消費者に金品を交付する費用
- 抽選で、一般消費者を旅行・観劇等に招待する費用
- 金品引換券付販売に伴い、一般消費者に金品を交付する費用
- 一定の商品を購入した一般消費者を、旅行・観劇等に招待する費用
- 商品を購入した一般消費者に景品を交付する費用
- 一般の工場見学者等に製品の試飲・試食をさせる費用
- 得意先等に見本品・試用品を供与する費用
- 商品の試用を行った一般消費者に、謝礼として金品を交付する費用
※ 国税庁の通達を易しい表現に変えています
繰り返しになりますが、上記はあくまで法人向けのルールです。個人事業主がキッチリ従う必要はないので、「だいたいこんな感じね」くらいに捉えておけばよいです。
これは広告宣伝費?接待交際費?【ケース別解説】
ここからは、広告宣伝費と接待交際費で迷いそうなケースを例に挙げて、使い分けの考え方を解説していきます。(あくまで考え方の一例なので、この通りに使い分けないといけないわけではありません)
取引先と食事に行った
取引先との食事代は「接待交際費」で処理するのが妥当です。法人のルールでは「得意先などに対する接待や贈答のために支出する費用」は交際費に該当するので、個人事業主もこれにならっておくのが無難でしょう。
ちなみに、たとえば「新商品のお披露目会に複数の取引先を招待した」というような場合の食事代は「広告宣伝費」で処理しても違和感がなさそうです。ただ、このようなレアケースについては、税務署も確固たる答えがあるわけではないので、どちらの勘定科目を使ってもさほど問題ないでしょう。
軽食付きのビジネス交流会に参加した
ビジネス交流会の参加費用は、食事の有無に関わらず「接待交際費」で処理するのが一般的です。ただ「不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用」とも言えそうなので、広告宣伝費に計上しても間違いではありません。どちらを使っても大きな問題はありません。
取引先とゴルフに行った
取引先とのゴルフ代は「接待交際費」で処理するのがよいでしょう。たとえゴルフ中にガンガン宣伝することが目的だったとしても、一般的には「接待」や「お付き合い」とみなされるので、接待交際費に計上しておくのが無難です。
取引先にノベルティグッズを配った
ノベルティグッズの製造・配布にかかる費用は「広告宣伝費」で処理しましょう。法人のルールでは、取引先などに「カレンダー、手帳、手ぬぐいなど」を贈与する費用は、基本的に「広告宣伝費」とされています。個人事業主もこのルールに従っておくと安心です。
ただ、国税庁が例に挙げている「カレンダー、手帳、手ぬぐいなど」より大幅に高価なノベルティを配布する場合は、「接待交際費」のほうがしっくりくるかもしれません。取引先に物品を贈与する機会が多い場合は、勘定科目の使い分け基準を決めておきましょう。
取引先に商品のサンプルを配った
取引先にサンプル品などを配ったら、その費用は「広告宣伝費」に計上しましょう。法人のルールに倣えば、「得意先などに対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用」は広告宣伝費に該当します。
ちなみに、小売業などで一般消費者にサンプル品を配る場合の費用も、「広告宣伝費」で処理するのが妥当です。
まとめ
個人事業主やフリーランスの場合、「広告宣伝費」と「接待交際費」の使い分けについて一律のルールは定められていません。法人のルールを参考にして、おおまかに使い分けておけばOKです。
広告宣伝費と接待交際費の一般的な使い分け
| 広告宣伝費 | 接待交際費 |
|---|---|
| 不特定多数に対する 宣伝にかかった費用 |
特定の相手との 関係構築にかかる費用 |
個人事業主の会計では、勘定科目の細かな使い分けよりも、下記のようなポイントを守ることが重要です。
- 事業に関係のない支出を必要経費に含めない
- レシートや領収書などの証拠を残しておく
- 一貫性をもって帳簿付けする
たとえば、同じような費用について「前回は広告宣伝費にしたけど、今回は接待交際費にしよう」などと、基準をコロコロ変えるのはNGです。勘定科目の使い分けについては、自分なりのルールでも構わないので、いちど決めた基準を保てるようにしましょう.