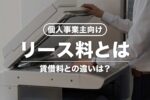個人事業主・フリーランス向けに、「消耗品費」の会計処理をまとめました。年間の上限額や、減価償却が必要になるラインについても解説します。
目次
個人事業主の消耗品費とは?
事業で使う事務用品や日用品を購入したら、その費用は「消耗品費」の勘定科目で経費に計上します。消耗品費の消費税区分は、基本的に「課税」です。
消耗品費の具体例
| 事務用品 | 器具・備品 | 日用品 | その他 |
|---|---|---|---|
| ・筆記用具 ・ノート ・ファイル ・コピー用紙 ・インク ・領収書 ・封筒 ・印鑑 ・名刺 |
・パソコン ・キーボード ・マウス ・USBメモリ ・LANケーブル ・機械部品 ・デスク ・椅子 ・ロッカー |
・電球 ・電池 ・お茶 ・食器 ・洗剤 ・ゴミ袋 ・ティッシュ ・タオル ・植物 |
・ソフトウェア ・ライセンス料 ・クラウド会計ソフトの利用料 ・コピー代金 ・ガソリン代 |
取得価額が10万円以上のものは原則として「減価償却」が必要で、消耗品費として経費計上できません。取得価額とは、本体価格に送料や手数料などを加えた金額を指します。
消耗品費は年間いくらまで認められる?
消耗品費に「年間〇〇円まで」という上限は存在しません。極端な話、年間100万円単位で計上しても問題ありません。ただ、金額が大きくなると使途が不明瞭になりやすいので、他の勘定科目も上手に使いましょう。
他の勘定科目との使い分け – 事務用品費・雑費など
下記のような費用は、「消耗品費」以外の勘定科目でも記帳できます。
| 費用(用途) | 勘定科目の例 |
|---|---|
| ボールペン、ノート、電卓、デスクライト、伝票 | 事務用品費 |
| 封筒、印刷料金、切手代、電話機 | 通信費 |
| 蛍光灯、ネジ、ドライバー、工具 | 修繕費 |
| ガソリン代、ヘルメット、タイヤ交換 | 旅費交通費 |
帳簿のつけ方に一貫性さえあれば、基本的にはどの科目を使っても問題ありません。重要なのは「いちど消耗品費で記帳した費用は、その後もずっと消耗品費で記帳する」ということです。年をまたいでも、この一貫性を保ちましょう。
「雑費」はどういうときに使う?
「雑費」は、どの勘定科目にも当てはまらない場合に使います(たとえばクリーニング代やゴミの処理費用など)。雑費の金額が膨れ上がるのは好ましくないので、まずは雑費以外の勘定科目が使えないか考えるようにしましょう。
消耗品費の記帳方法【仕訳例】
たとえば、書類を整理するためのファイル(2,000円分)を現金で購入した場合、複式簿記では以下のように仕訳します。
複式簿記の記帳例
| 日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 20XX年5月18日 | 消耗品費 2,000 | 現金 2,000 | ファイル |
複式簿記は55万円・65万円の「青色申告特別控除」を受けるために必要な記帳方法です。単式簿記の場合は、以下のように記帳します。
単式簿記の記帳例
| 日付 | 消耗品費 | 摘要 |
|---|---|---|
| 20XX年5月18日 | 2,000 | ファイル |
10万円以上は減価償却が必要?
事業用の備品などを購入した際、その「取得価額」が10万円以上なら「減価償却」が必要です(厳密には「10万円以上」かつ「使用可能な期間が1年以上」のもの)。
| 取得価額10万円未満 | 取得価額10万円以上 |
|---|---|
| 購入時に全額を経費計上する | 購入時は資産に計上し、減価償却する |
「取得価額」には、購入したものの本体価格だけでなく、購入にかかった送料や手数料などを含めます。購入にかかった費用の合計額が10万円以上なら、減価償却が必要になるということです。
取得価額はセットで考える
「応接セット」や「パソコン本体とディスプレイ」など、セットで使うものは、それらの購入費用の合計を取得価額とみなします。つまり、5万円の椅子でも7万円のテーブルとセットなら、減価償却することになります。
減価償却が必要になる基準について詳しく
【注意点】経費にできるのは使った分だけ
原則としては、その年の経費にできるのは「その年に使った分」の購入費用だけです。「その年に使わなかった分」は、いったん「貯蔵品」という資産の勘定科目に計上し、翌年以降に経費計上するのが原則です。

ただし、以下2点の両方にあてはまる消耗品は「使わなかった分」も含めて、全額をその年の経費に計上して問題ありません。
- 毎年、おおよそ一定の量を購入するもの
- 毎年、継続的に消費するもの
たとえばプリンターのインクを年末に購入してその年に使わなかったとしても、コンスタントに購入して使っているのであれば、その年の消耗品費として計上してしまってよいということです。ただし、大量買いした場合には、「貯蔵品」の科目で資産計上しておきましょう。
消耗品費に関する疑問まとめ【Q&A】
- 消耗品費は年間いくらまで?
- 消耗品費として経費計上できる金額に上限はありません。ただし、特定の勘定科目だけ金額が大きいと税務署に目をつけられやすいので、「面倒だからぜんぶ消耗品費にしちゃおう」というのは避けましょう。
- 10万円以上の備品を買ったらどうなる?
- 10万円以上の資産は、消耗品費ではなく固定資産として計上します。その後、耐用年数に応じて、毎年少しずつ経費にしていきます。このような会計処理を「減価償却」といいます。
- 30万円未満なら減価償却が不要って本当?
- 青色申告の個人事業主は、30万円未満の資産を「少額減価償却資産の特例」で一度に経費計上できます。ただし、年間合計300万円までという上限があります。
- 消耗品費と「事務用品費」の違いは?
- 「消耗品費」の勘定科目は消耗品全般に使えますが、「事務用品費」はそのうち事務用品の購入費用に特化した勘定科目です。消耗品費の金額が大きくなりそうな個人事業主は、「事務用品費」も使って使途を整理するのがおすすめです。
- 消耗品費の代わりに「雑費」を使ってもいい?
- 「雑費」という勘定科目は、他にちょうどいい勘定科目がない場合に使うものです。「消耗品費」に該当する費用を、わざわざ雑費に計上するのは避けましょう。基本的に「雑費」の金額は少ないほどよいです。
まとめ
「消耗品費」は汎用性の高い勘定科目で、何かモノを買った際には大体この勘定科目で記帳できます。仕事で使うパソコンでも、取得価額10万円未満であれば「消耗品費」として経費計上できます。ただし、10万円の基準には注意して帳簿づけしましょう。
- 本体価格に手数料、配送料などを加えたものが「取得価額」
- 取得価額10万円未満なら「消耗品費」として経費計上できる
- 取得価額10万円以上なら、原則「減価償却」が必要
少額の物品購入についてそこまで気にする必要はありませんが、原則としては、その年に購入したものならすべてその年の経費に計上できるというわけではありません。
- 原則としては、その年に使った分だけを経費計上できる
- その年に使わなかった分は、期末に「貯蔵品」として資産に計上するのが原則
- 貯蔵品に計上したものは、翌年以降に経費計上することになる
年内に使い切らない場合でも、毎年「おおよそ一定の量を購入するもの」で「継続的に消費するもの」であれば、購入した日付で「消耗品費」に計上してOKです。ただし、年末に大きなまとめ買いをしたような場合には「貯蔵品」の科目で資産計上しておきましょう。