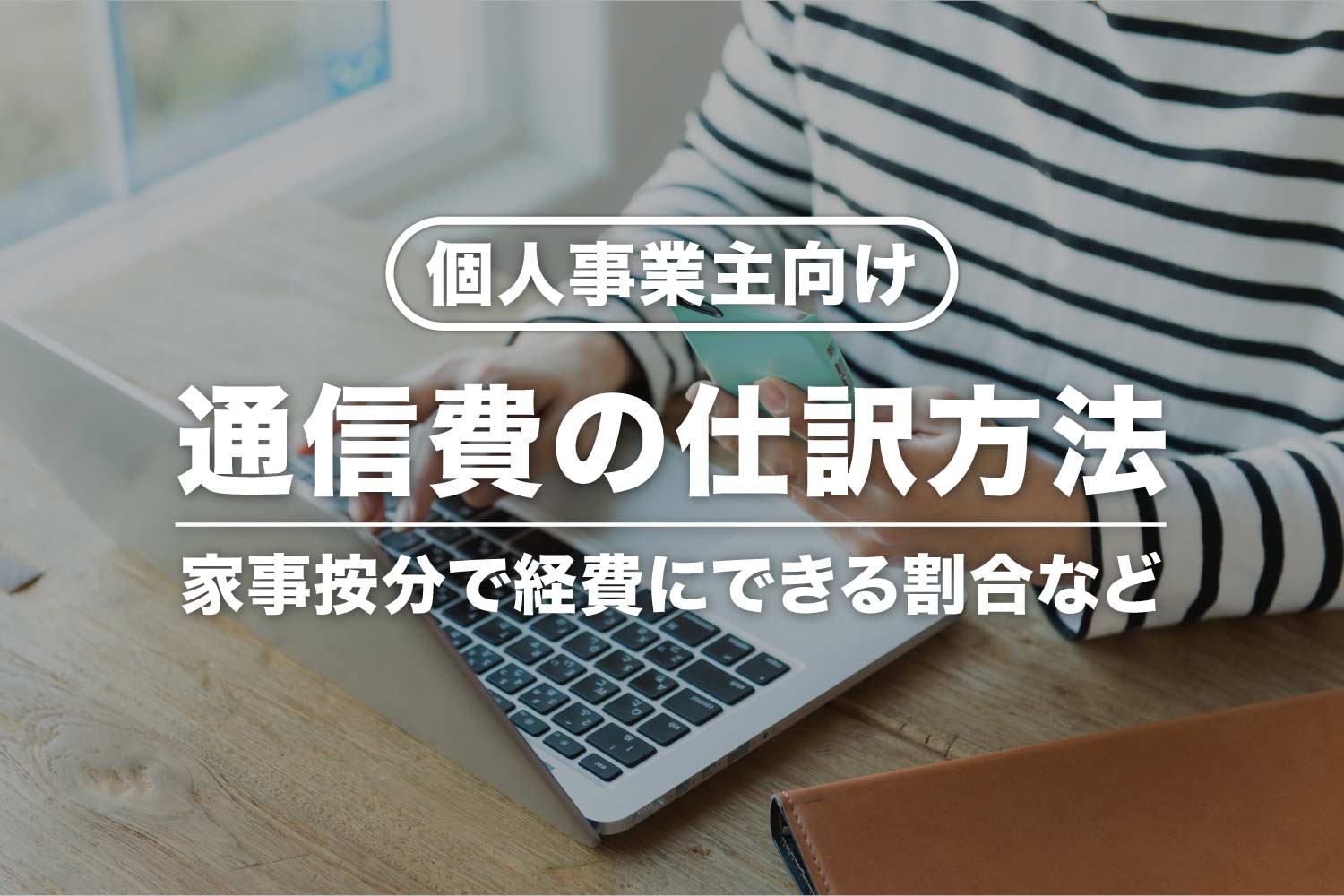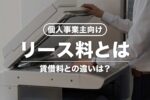個人事業主・フリーランス向けに、通信費の仕訳方法を解説します。仕事とプライベートの両方で使っているスマホ料金なども、家事按分で一部の割合を経費にできます。
目次
個人事業主の通信費とは?
業務に関わる電話代・インターネット料金・郵便料金などは、「通信費」の勘定科目で経費に計上できます。プライベートのスマホを仕事でも使っている場合などは、料金を家事按分して一部を経費計上します。
個人事業主の通信費の例
| 電話 | インターネット | 郵便 |
|---|---|---|
|
|
|
電話機本体などの端末については、10万円以上であれば「工具器具備品」に計上して減価償却するのが基本です。そうでなければ「消耗品費」として処理しましょう。
また、商品の発送にかかる費用は「荷造運賃」の勘定科目で処理するのが一般的です。
通信費の消費税区分
通信費の消費税区分は、基本的に「課税」です。ただし、国際電話や国際郵便など、海外と国内をつなぐ通信の費用は「免税」です。国内を経由しない、海外同士の通信は「不課税」となります。郵便切手は金券なので、本来は「非課税」です。
| 課税 | 免税 | 非課税 | 不課税 |
|---|---|---|---|
|
|
郵便切手 (課税でもよい) |
海外同士の通信 |
郵便切手は「使う時に初めて経費になり、消費税が課税される」という特殊な扱いになっています。そのため、厳密には購入時に「貯蔵品」として資産に計上します。
しかし、「仕訳例③ 郵便切手代の記帳方法」で後述するように、日常的に切手を使用している事業者は、実務的には購入時に「通信費」として経費計上し、その消費税区分は「課税」として処理することが多いです。
消費税の課税区分について詳しく【課税・免税・非課税・不課税】
通信費を家事按分する方法 – 経費にできる割合は?
プライベート用と事業用の料金を一緒に支払っている場合は、「家事按分」という方法で一部を経費にできます。事業用に使用している割合を、税務署に対してきちんと説明できればOKです。
家事按分する通信費の例
- 固定電話の利用料金
- 携帯電話の利用料金
- インターネット回線使用料
- プロバイダ料
- Wi-Fi利用料
事業用の割合を「按分比率」といい、事業者が自由に設定しますが、税務署が納得する割合である必要があります。大抵は「使用時間」「使用日数」などを基準にします。なお、プライベート用とは別に仕事用の携帯電話を契約している事業者は、仕事用の携帯電話料金をすべて経費にできます。

また、「事業開始前はいつも2,000円で済んでいた携帯の利用料金が、開始後には10,000円になったので、増えた8,000円は事業用だ」などのように明確な根拠を示すことができれば、按分比率80%でも認められるケースがあります。
家事按分について詳しく – 比率の考え方や仕訳方法など
通信費の仕訳方法
仕訳例① 基本的な記帳方法
ここでは通信費の基本的な仕訳例として、郵送料を挙げます。取引先のA社へ簡易書留で書類を発送し、現金430円を郵便局に支払ったとします。その場合は、次のように仕訳します。
複式簿記の記帳例
| 日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 20XX年12月20日 | 通信費 430 | 現金 430 | A社 簡易書留郵便 |
複式簿記では、費用である通信費を借方(=左側)に書く決まりになっています。青色申告で65万円・55万円控除を目指す事業者は、複式簿記で記帳する必要があります。それ以外の事業者は、たとえば次のように単式簿記で記帳します。
単式簿記の記帳例
| 日付 | 通信費 | 摘要 |
|---|---|---|
| 20XX年12月20日 | 430 | A社 簡易書留郵便 |
仕訳例② 家事按分した場合の記帳方法
家事按分をした際の記帳例として、スマホの利用料金を例に仕訳をします。「仕事でもプライベートでも同じスマホを使っていて、その使用時間が半々であることから、按分比率は50%に設定した」と仮定します。
以上の状況で、携帯料金として銀行口座から10,000円引き落とされた場合、複式簿記での記帳は次のようになります。
銀行口座から引き落とされた場合の仕訳例
| 日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 20XX年12月27日 | 通信費 5,000 | 普通預金 10,000 | 携帯料金 |
| 事業主貸 5,000 |
按分する場合は、プライベートで使った部分は「事業主貸」という個人事業主に特有の勘定科目で処理します。なお、コンビニなどで現金を使って支払ったときは、「事業主貸」は使わずに次のように記帳してもOKです。
現金で直接支払った場合の仕訳例
| 日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 20XX年12月25日 | 通信費 5,000 | 現金 5,000 | 携帯料金 |
仕訳例③ 郵便切手代の記帳方法
日常的に郵便切手を使用している事業者は、切手を購入したタイミングで経費計上してOKです。消費税区分もこのタイミングで「課税」とします。この場合、切手を実際に使ったときの記帳が不要になります。
本来、郵便切手は使って初めて経費になります。消費税もこのとき初めて課税されるという扱いになっています。ただし、切手を事業主が使用するために購入し、かつ少額である場合、実務上は購入時に経費計上でき、消費税もこのとき「課税」として処理します。
| 購入時 | 使用時 |
|---|---|
|
記帳不要 |
少額の切手代に対する実務的な仕訳例
複式簿記で記帳する場合の例として、「11月1日に82円切手を100枚購入し、11月5日に1枚使用した」ときは以下のようになります。なお、11月5日に使用した分の記帳はしなくて構いません。
| 日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 20XX年11月1日 | 通信費 8,200 | 現金 8,200 | 切手代 |
年度末に切手が余った場合の仕訳例
年度末の時点で、上記で購入した切手の半分が余った場合は、下記のように帳簿づけをします。その年のうちに消費しなかった分がその年の経費にできないので、ひとまず余った切手を「貯蔵品」として資産計上しておくという仕訳です。
| 日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 貯蔵品 4,100 | 通信費 4,100 | 使わなかった切手 |
貯蔵品へ計上した余りの切手を次の年に使用する時には、次のように仕訳をします。ここでは、余っていた82円切手を10枚使用したとします。これで、2022年に消費した切手代が2022年分の経費として計上でき、正しいタイミングで経費計上することになります。
| 日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 2022年3月20日 | 通信費 820 | 貯蔵品 820 | 切手代 |
まとめ
通信費は、家事按分できる場合が多いです。また、郵便切手を事業主が使うために少額購入したときは、まとめて経費にしてOKです。電話機本体などの通信機器については、大抵は「消耗品費」で処理します。10万円を超えたら「工具器具備品」として計上します。
通信費の重要ポイント
- 事業と私用の両方で使う電話代などは家事按分できる
- 按分比率は「使用日数」「使用時間」などを基準にする
- 家事按分のプライベート分は「事業主貸」で処理する
- 通信費の消費税区分は基本的には「課税」
- 海外を経由する国際電話などの消費税区分は「免税」
- 郵便切手は原則、使用して初めて消費税が「課税」扱いになる
- 事業主自身が使う少額の郵便切手は、購入時に消費税を「課税」扱いとしてもよい
- 郵便切手を購入時に「課税」で経費計上した場合は、使用時の記帳はしない
「通信費」「消耗品費」「荷造運賃」の区別が難しいときは、一度つけた勘定科目で今後もずっと帳簿づけする、という一貫性さえあれば、どれでつけても問題ありません(継続性の原則)。