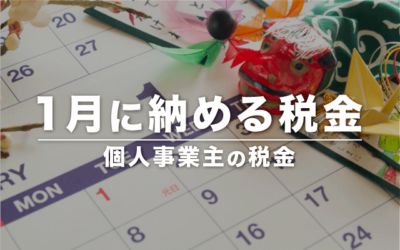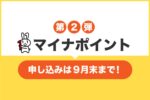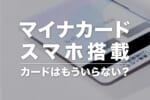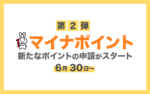マイナンバーカードは、顔写真付きの身分証明書としてはもちろん、オンラインでの本人確認にも利用できるなど、機能が続々と拡充されています。本記事では、マイナンバーカードで今できること、そしてこれからできるようになることをまとめています。
目次
「マイナンバーカード」のおさらい
マイナンバーカードは、マイナンバーや顔写真、氏名、住所などが記載されたプラスチック製のカードです。これは、自ら申請手続きをすることで取得できます。交付手数料は無料です。

- そもそも「マイナンバー」とは
- 日本に住民票を有するすべての人がもつ12桁の番号のこと。「個人番号」ともいう。原則として、生涯を通して同じ番号を使用する。引越しや結婚によって番号が変わることはない。
マイナンバーカードの機能は、大きく3つに分けられます。
マイナンバーカードの機能と主な利用シーン
| ① マイナンバーの証明 | ・源泉徴収票を作成するとき(年末調整) ・確定申告をするとき ・年金の受給手続きをするとき |
|---|---|
| ② 写真付き身分証明書としての利用 | ・口座を開設するとき ・賃貸物件を契約するとき ・レンタル店の会員登録をするとき |
| ③ オンライン上での本人確認 | ・確定申告をネットで行うとき(電子申告) ・ネット銀行の口座を開設するとき ・コンビニで住民票の写しを発行するとき |
まずはこれらの機能を順番にみていきましょう。
① マイナンバーの証明
会社の入社時や社会保険・税金の手続きの際などに、マイナンバーを求められることがあります。このとき、マイナンバーカードで自分の個人番号を証明できます。マイナンバーの「通知カード」や、マイナンバーが記載された住民票の写しでも、マイナンバーの証明は可能です。

マイナンバーを求められるシーン
- 源泉徴収票を作成するとき(年末調整)
- 確定申告をするとき
- 年金の受給手続きをするとき
マイナンバーカードと通知カードの違い
「マイナンバーカード」と、マイナンバーの「通知カード」は異なります。通知カードは紙製のカードです。2015(平成27)年10月以降にマイナンバーを伝達する目的で「通知カード・個人番号カードの交付申請書」として各家庭に郵送されました。
| マイナンバーカード (個人番号カード) |
通知カード |
|---|---|
 |
 |
なお、通知カードは2020年5月をもって廃止され、再交付や記載事項の変更手続きができなくなりました。新規発行や再交付は終了したのですが、通知カードが手元にある方は、引き続きマイナンバーの証明書類として使用することができます。
>> 通知カードの廃止について詳しく
② 写真付き身分証明書としての利用
マイナンバーカードには、顔写真や氏名、住所、生年月日などが記載されているので、本人確認の身分証明書として使用できます。

顔写真付き身分証明書の提示が求められるシーン
- 口座を開設するとき
- 賃貸物件を契約するとき
- レンタル店の会員登録をするとき
マイナンバーカードは、運転免許証やパスポートなどと同じように、身分証明書として利用できます。運転免許証を返納した高齢者なども、手軽に発行できるので、そういった人におすすめです。
③ オンライン上での本人確認
マイナンバーカードのICチップには「電子証明書」が標準で内蔵されており、オンラインでの本人確認などに利用できます。行政機関の電子手続きなどで、これを活用する場合が多いです。

電子的な本人確認に利用するシーン
- 確定申告をネットで行うとき(電子申告)
- ネット銀行の口座を開設するとき
- コンビニで住民票の写しを発行するとき
新型コロナウイルス感染症の支援対策のひとつ「特別定額給付金」(10万円の給付金)のオンライン申請する場合にも、マイナンバーカードが必須でした。
行政機関の手続きだけでなく、民間のサービスの手続きにおいても、マイナンバーカードで本人確認が可能になる動きが広がっています。たとえば、2つ目の「ネット銀行の口座を開設するとき」ですが、これにはPayPay銀行が対応しています。
コンビニなどで各種証明書を発行することも可能
マイナンバーカードがあれば、コンビニやスーパーなどに設置されているマルチコピー機で、住民票の写しなどを発行できます。対応している時間帯は、6:30~23:00で、平日だけでなく土日祝日でも利用可能です。
役所は開庁時間が限られており、平日しか対応していないことも多いです。コンビニなら土日祝日でも発行でき、市区町村によっては発行手数料が安くなることもあります。たとえば、東京都新宿区ではコンビニのほうが手数料が100円安いです。
住民票の写しを発行する際の手数料と対応時間(東京都新宿区)
| コンビニなどで発行 | 区役所の窓口で発行 | |
|---|---|---|
| 発行手数料 | 一通あたり200円 | 一通あたり300円 |
| 対応時間 | 平日および土日祝日 6:30~23:00 |
基本、平日のみ 8:30~17:00(※) |
(※)火曜日のみ19:00まで
なお、コンビニなどで発行できるのは以下のような書類です。市区町村によっては対応していないものもあります。自分の地域でどの書類が発行できるかは、各自治体のホームページで確認してください。
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- 住民票記載事項証明書
- 各種税証明書
- 戸籍証明書
- 戸籍の附票の写し
将来的にできるようになること
マイナンバーカードの交付が開始された当初と比べると、機能は年々拡充されています。内閣府が公開している「マイナンバー制度導入後のロードマップ」によると、今後は以下のようなサービスが予定されているようです。
| ・マイナポイント事業がスタート | 2020年9月1日〜 |
| ・健康保険証として利用できるように | 2021年3月〜 |
|
・国立大学での活用促進(デジタル・キャンパスの推進) ・ハローワークカードとしての活用 ・電子版ジョブ・カードとしての活用 ・建設キャリアアップシステムとの連携 |
2022年〜 |
| ・海外継続利用開始 | 2023年〜 |
9月からマイナポイント事業がスタート
「マイナポイント事業」とは、マイナンバーカードと決済サービスを紐付けることで、ポイントが還元されるサービスです。対象者は、マイナンバーカードを所持しているかつ事前登録をした人だけです。
健康保険証として利用できる?
2021(令和3)年3月から、マイナンバーカードを健康保険証として使えるようになる予定です。さらに、2021年秋頃からは、ネット上で自分の医療費情報の確認が可能になる見込みなので、医療費控除を受ける際の利便化も期待できます。
このほかにも、さまざまなサービスが検討されています。たとえば、一部の企業ではすでにマイナンバーカードを社員証として活用しています。今後は自治体のサービスだけでなく、民間のサービスにも広がっていくことが予想されます。
マイナンバーカードの申請方法
マイナンバーカードの申請方法は、大きく分けると以下の3つです。マイナンバーカードの「交付申請書」がある場合は、好きな方法を選択できます。

「交付申請書」とは、下図のように「通知カード」がくっついていた紙のことです。2015年に各家庭へ郵送されたものです。これを無くしてしまった場合、手書き用の交付申請書をダウンロードし、自分で作成して郵送で申請します。

申請をすると、通常1~2ヶ月ほどで通知書(はがき)が届きます。通知書には、マイナンバーカードの交付場所が記載されているので、そこへ受け取りに行きます。カードを郵送で受け取ることはできません。
まとめ
マイナンバーカードがあれば、さまざまな場面で身分を証明することができます。また、コンビニ等で住民票の写しなどの書類が発行できるなど、便利なサービスも導入され始めています。

マイナンバーカードがあれば、それを利用して確定申告がネットで行えるといったメリットもあります。マイナンバーカード所持者に限定したサービスもあり、直近では2020年9月から「マイナポイント事業」が始まりました。
なお、マイナンバーカードを申請をしてから交付されるまでには、通常で1ヶ月ほどかかるとされています。自治体によっては、2ヶ月以上の期間を要するところもあるようです。