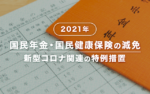個人事業主が加入する、市区町村の介護保険についてまとめました。「国民健康保険」の加入者は、40歳になったら必ずこの介護保険に加入します。とはいえ、加入手続きなどは基本的に不要。40歳以降は、自動的に介護保険料の納付がスタートします。
目次
介護保険とは?
介護保険とは、40歳になったら加入する社会保険の一種。高齢者など、介護が必要な人々を支援するための制度です。海外居住者など、ごく一部の適用除外者をのぞいて、必ず加入することになります。
加入者は、介護や支援が必要だと認められた場合、1~3割の自己負担で介護サービスを利用できます。

介護保険は加入手続きが不要
公的な医療保険に加入していれば、40歳以降、自動的に介護保険料の納付がスタートします。つまり、介護保険は基本的に自分で加入手続きをする必要がないということ。個人事業主の場合は、ひとまず「国民健康保険」に加入していればOKです。
なお、この記事では市区町村が運営する介護保険について説明します。「国民健康保険組合」や「健康保険」に加入している場合は内容が異なる部分もあるため、参考程度にご覧ください。
保険料や給付要件は年齢によって異なる
介護保険の加入者は、年齢によって以下のように区別されます。40歳になったら「第2号被保険者」として加入し、65歳以降は「第1号被保険者」に切り替わります。
- 第1号被保険者……65歳以上
- 第2号被保険者……40歳~64歳
原則として、介護保険の給付を受けられるのは第1号被保険者のみ。ただし、国が指定する特定の病気を患っている場合は、第2号被保険者でも給付を受けられます。また、第1号被保険者と第2号被保険者で、保険料の算出方法と納付方法が異なります。
第1号被保険者と第2号被保険者の違い
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
|---|---|---|
| 年齢 | 65歳以上 | 40~64歳 |
| 保険料の平均 | おおよそ6,000円/月 | おおよそ6,000円/月 |
| 納付方法 | 基本的に年金から天引き | 国民健康保険料に上乗せ |
| 給付を受けられる人 | 全員 | 「特定疾病」を患う人のみ |
表中の保険料はあくまでおおよその平均額なので、目安程度にご覧ください。自治体や個人の所得などによって、保険料は大きく異なります。
第2号被保険者の保険料 – 40~64歳
第2号被保険者の介護保険料は、前年の総所得金額等をもとに、自治体ごとの保険料率などから算出されます。ちなみに、納付が始まるのは「40歳になる誕生日の前日」が含まれる月からです。
第2号被保険者は、介護保険料を国民健康保険の保険料に上乗せして納めます。40~64歳の間は、国民健康保険の保険料に介護保険料が含まれているということ。そのため第2号被保険者の介護保険料は、国民健康保険の「介護分」と呼ばれることもあります。
以下の表は、千葉県松戸市が公開している国民健康保険料の早見表から一部を抜粋したものです。介護保険料を含めた国民健康保険料の参考にしてください。なお、ここで言う「総所得」は、専業の個人事業主なら「収入 − 必要経費」の金額だと考えて構いません。
前年の総所得に応じた国民健康保険料(千葉県松戸市の例)
| 39歳以下の年間保険料 (介護分なし) |
40~64歳の年間保険料 (介護分あり) |
|
|---|---|---|
| 500万円 | 518,960円 | 616,670円 |
| 400万円 | 416,560円 | 496,170円 |
| 300万円 | 314,160円 | 375,670円 |
| 200万円 | 211,760円 | 255,170円 |
| 100万円 | 109,360円 | 134,670円 |
第2号被保険者の介護保険料は、国民健康保険料と合わせて徴収されるため、特別な納付手続きは不要です。介護保険料も合わせた金額で保険料の通知などが届くので、いつも通り納付しましょう。
第1号被保険者の保険料 – 65歳以上
第1号被保険者の介護保険料は、所得などに応じて段階的に決められています。つまり、年金などの収入が多いと保険料も高くなるということですが、自治体や所得によって大きく異なります。
たとえば千葉県松戸市では、第1号被保険者の介護保険料が以下のように定められています。加入者は所得に応じて20の段階に分けられ、それぞれ定められた額の保険料を納付します。なお、保険料は3年ごとに見直されます。
第1号被保険者の保険料(千葉県松戸市の例)
| おおまかな対象者 | 介護保険料(年額) | |
|---|---|---|
| 第20段階 | 前年の合計所得が3,000万円以上 | 241,920円 |
| 第19段階 | 前年の合計所得が2,500~3,000万円 | 234,360円 |
| ・ ・ ・ |
||
| 第7段階 | 前年の合計所得が120~200万円 | 94,560円 |
| 第6段階 | 前年の合計所得が120万円未満 | 83,160円 |
| 第5段階 | 本人が市民税非課税で、第4段階に該当しない | 75,600円 |
| 第4段階 | 前年の年金収入と事業所得などが合わせて80万円以下 | 64,320円 |
| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で第1,2段階に該当しない | 50,280円 |
| 第2段階 | 前年の年金収入と事業所得などが合わせて120万円以下 | 32,160円 |
| 第1段階 | 前年の年金収入と事業所得などが合わせて80万円以下 (世帯全員が住民税非課税) |
20,760円 |
世帯の全員が住民税を免除されている場合は、第1~3段階のいずれかに該当します。また、世帯全員でなくても、本人だけが免除されているなら該当するのは第4,5段階のどちらかです。
>> 住民税の「非課税限度額」について
第1号被保険者の介護保険料は、基本的に年金からの天引きで納付します。第2号被保険者の時と同じく、納付手続きをする必要はありません。ただし、年金の受給額が年間18万円未満の場合などは、窓口納付や口座振替で納税することになっています。
介護保険の給付を受ける要件
要介護(要支援)の認定を受けた加入者は、1~3割の自己負担額で介護サービスを利用できます。この給付を受けられるのは、原則として第1号被保険者のみ。ただし、特定の病気(特定疾患)を患っている場合は、第2号被保険者でも給付を受けられます。
介護保険の給付要件
| 第1号被保険者(65歳以上) | 第2号被保険者(40~64歳) |
|---|---|
| 原因を問わず、要介護(要支援)状態にある | 「特定疾病」によって要介護(要支援)状態にある |
要介護・要支援の認定は、自治体に申請を出したのち、審査を受けることで得られます。最も軽度の「要支援1」の認定でも、介護保険の受給は可能。なお「要支援1」とは、おおよそ「日常生活の一部に介護が必要な状態」を指します。
なお「特定疾病」とは、国が定める以下の病気などを指します。
「特定疾病」の主な例
- 末期のガン
- 関節リウマチ(回復の見込みがないもの)
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- パーキンソン病に関連する疾患
詳しくは厚生労働省の選定基準をご覧ください。例示されていない病気でも、要件を満たせば「特定疾病」と認められます。
介護サービスの自己負担額
介護サービスを受けた際の自己負担割合は、加入者の合計所得などによって以下のように異なります。

合計所得金額とは、ざっくり言えば事業所得や不動産所得、雑所得(年金を含む)などの合計のこと。ただし、年金収入からは最低でも120万円が控除されるため、年間の年金収入が120万円以下の方であれば、「年金以外の所得の合計」と考えてOKです。
第2号被保険者と合計所得が160万円未満の第1号被保険者は、必ず1割の自己負担でサービスを受けられます。それ以外の場合は、年金収入や世帯全体の収入が多いと負担割合が増えます。なお、自己負担割合の基準はどの自治体でも変わりません。
詳細は糸魚川市の説明をご覧ください。
自己負担額が医療費控除の対象になる場合
「医療系サービス」と呼ばれる介護サービスを利用したら、基本的にその自己負担額は「医療費控除」の対象になります。また「福祉系サービス」と呼ばれるものも、医療系サービスと一緒に受ければ、医療費控除の対象となる場合があります。
ちなみに、生計を共にする家族などのために支払ったお金も医療費控除の対象になります。たとえば、一緒に暮らす親の介護サービス料金を負担したら、そのぶん医療費控除を受けて、税金を減らせるということです。
医療費控除の対象となるのは、主に以下のような介護サービスです。
| 医療費控除の取り扱い | サービスの種類 |
|---|---|
| 医療費控除の対象になる |
|
| 上記と併せて利用した場合のみ対象 |
|
「介護療養型医療施設(いわゆる介護医療院)」や「介護老人保健施設」といった施設の利用料も医療費控除の対象となります。ただし、医療サービス的な性質が少ない「特別養護老人ホーム」の場合、控除の対象となるのは自己負担額の2分の1だけです。
なお、施設における特別な食事代や個室代などは医療費控除の対象になりません。また、要介護認定がなくても入れる、いわゆる「有料老人ホーム」も、基本的に医療費控除の対象外です。判断に迷う場合は、税務署などに問い合わせましょう。
>> 医療費が控除対象になるケースまとめ
まとめ – 介護保険の重要ポイント
「国民健康保険」の加入者は、40歳になったら自動的に市区町村の介護保険に加入します。保険料の徴収が自動的にスタートするため、加入手続きは必要ありません。要介護認定を受けた加入者などは、1~3割の自己負担で介護サービスが利用できます。
介護保険の加入者は、年齢によって「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に区別されます。第1号と第2号では、保険料の算出方法や納付方法などが以下のように異なります。
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
|---|---|---|
| 年齢 | 65歳以上 | 40~64歳 |
| 保険料の平均 | おおよそ6,000円/月 | おおよそ6,000円/月 |
| 保険料の納付方法 | 基本的に年金から天引き | 国民健康保険料に上乗せ |
| 給付を受けられる人 | 全員 | 「特定疾病」を患う人のみ |
| 介護サービス費用の自己負担 | 所得などに応じて1~3割 | 所得などに関わらず1割 |
介護サービス料金の自己負担分については、医療費控除の対象となる場合があります。また、面倒をみている親の介護サービス料金を負担した際などは、そのぶんの医療費控除を受けることもできます。