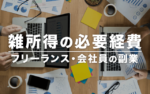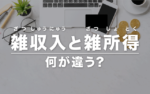「事業所得」と「雑所得」のわかりやすい見分け方や、税務上の違いを解説します。取引に関する帳簿書類をきちんと保存している場合は「事業所得」に該当することが多く、税制上の優遇措置が受けやすくなっています。
目次
事業所得・雑所得の見極めポイント
ごく簡単に言うと、本業で営む個人事業の収入などで、十分に事業性のあるものを「事業所得」と考えます。一方、会社員の副業収入などで、事業性の薄いものは「雑所得」として扱うことが多いです。
| 事業所得 | 雑所得 |
|---|---|
| 「事業所得を生ずべき事業」による所得 例:農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業などの所得 |
他の所得に含まれない所得 例:シェアリングエコノミー、著述家以外の人が得る原稿料などによる所得 |
ただ、一口に「事業性」と言われても、抽象的でよくわからないと思います。素人でも簡単に見分けられるよう、国税庁は以下のように例示しています(所得税基本通達35-2 および解説)。
わかりやすい見分け方 – 国税庁の例示
| 事業所得 | 雑所得(業務) |
|---|---|
| 帳簿書類の保存あり | 帳簿書類の保存なし |
※ 社会通念(≒一般常識)に照らして総合的に判定するのが原則です
きちんと帳簿を付けて、レシートなどの書類と合わせて適切に保存していれば、基本的には「事業所得」に該当すると考えられます。ただし、収入が少なすぎる副業や、赤字がずっと続いている場合は、帳簿があっても「雑所得」になりえます。
事業所得と雑所得の見極め方について詳しく
確定申告における扱いの違い
そもそも、なぜ事業所得と雑所得をしっかり区別する必要があるかと言うと、確定申告での扱いが大きく異なるからです。主には以下のような違いがあります。
| 事業所得 | 雑所得 | |
|---|---|---|
| 損益通算 | できる | できない |
| 青色申告の特典 | 適用できる | 適用できない |
| 帳簿の作成・保存 | 義務 | 義務でない |
| 主な申告書類 | 決算書 + 確定申告書 | 確定申告書だけでOK* |
事業所得は、赤字のときに損益通算をできたり、青色申告の特典を利用できたり、節税につながる制度が多いです。それに対して雑所得は、帳簿づけや申告に手間がかからないぶん、節税面では優遇されません。
ちなみに、株式の譲渡などによる事業所得・雑所得は「分離課税」の対象となり、特殊な扱いをする必要があるので、本記事での説明からは除外しています。
① 損益通算の可否
事業所得が赤字のときは、その赤字金額を他の所得から差し引くことができます(損益通算)。一方、雑所得の赤字について同様の処理はできません。

たとえば、アルバイトをしている個人事業主などは、事業が赤字ならそのぶん給与所得を抑えられます。しかし、副業をしている会社員などは、副業(雑所得)が赤字でも、その金額を給与所得から差し引くことはできません。
- 損益通算とは
- 一定のルールに従って、ある所得の赤字金額を他の所得から差し引くこと。損益通算できるのは、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得のいずれかが赤字になったときだけ。
事業所得が赤字の場合は、赤字になった分を他の所得から差し引き、最終的な納税額を減らせるわけです。
② 青色申告の特典
青色申告とは、簡単に言うと「ちょっと面倒だけど特典がある申告方式」です。青色申告を選択すると、事業所得に様々な特典を適用できます。一方、雑所得には特典を適用できません。(というより、そもそも雑所得には青色申告という制度がない)
青色申告の主な特典
| 青色申告特別控除 | クリアする要件に応じて、10万・55万・65万の控除が受けられる |
|---|---|
| 純損失の繰り越し | 損益通算をしても控除しきれなかった事業の赤字金額を、翌年以後3年繰り越せる |
| 少額減価償却資産の特例 | 30万円未満の備品などについて、減価償却をせずに購入年の必要経費にできる |
| 青色事業専従者給与 | 専従者( ≒ 家族従業員)に支払った給与の全額を「専従者給与」として必要経費にできる |
事業所得については、青色申告をすることで節税効果が見込めるわけです。ちなみに、事業所得と雑所得の両方を得ていても、青色申告の特典を適用できるのは事業所得に関わる部分だけです。
③ 記帳義務の有無
事業所得を得ている人は、その事業の売上や経費などを帳簿に記録し、保存しておく義務があります(所得税法148条・232条)。そのため、もし税務調査が入れば、帳簿の内容もチェックされます。
しかし、雑所得に関わる取引については、記帳の義務が定められていません。まったく帳簿をつけていなくても、そのことでペナルティを受けたりしないのです。
| 事業所得 | 雑所得 | |
|---|---|---|
| 青色申告 | 白色申告 | |
| 帳簿の作成・保存が義務 (細かいルールがある) |
帳簿の作成・保存が義務 (簡易的でもよい) |
帳簿の作成・保存が義務でない |
とはいえ、雑所得の場合でも、収入や必要経費の金額が記載された書類(請求書や領収書など)はとっておきましょう。確定申告の際には、それらをもとに所得金額を算出します。なお、申告後も5年ほど保存しておけば、万が一税務調査が入っても安心です。
ちなみに、2022年分の確定申告から、前々年の「雑所得(業務)」の収入が年間300万円を超えた人に、領収書などの保存が義務付けられました。帳簿を作る必要がないことは変わりませんが、書類の扱いには注意しましょう。
雑所得でも領収書の保存が必要に?【2022年1月~】
④ 確定申告の提出書類
事業所得の申告では、主に「確定申告書」と「決算書」を提出します。一方、雑所得は基本的に「確定申告書」だけで申告できます。
主な提出書類
| 事業所得の申告 | 雑所得の申告 |
|---|---|
| ・確定申告書 ・収支内訳書(白色申告者のみ) ・青色申告決算書(青色申告者のみ) |
・確定申告書 |
2021年分以前の申告をする際には、申告内容に応じて「確定申告書A」と「確定申告書B」を使い分ける必要があります。「A」は事業所得の申告に対応していません。
なお、2022年分からは「確定申告書A」が廃止され、申告書の様式が一本化されています。したがって、A・Bの使い分けを気にする必要はありません。
確定申告書の統合について【令和4年分〜】
どちらでも変わらないこと
事業所得でも雑所得でも、以下のポイントは変わりません。
- 確定申告が必要になるライン
- 必要経費の考え方
- 税率
- 特定の事業にかかる個人事業税
確定申告が必要になるライン
たとえば、副業をする会社員は、副業収入が事業所得・雑所得のどちらに該当する場合でも、その所得が20万円を超えたら確定申告が必要です。また、給与所得がない人は、基本的に各種の所得金額が、所得控除の額を超えると確定申告が必要になります。
必要経費の考え方
事業所得も雑所得も、基本的に「収入 - 必要経費」で算出することは変わりません。必要経費とは、収入を得るために要した売上原価や販売費などのことで、その範囲も原則としては同じです。(ただし、専従者や青色申告に関するものを除く)
税率
事業所得・雑所得どちらの場合でも、所得税や住民税の税率は同じです。株式の譲渡などよる所得には特殊な税率が適用されるケースもありますが(分離課税)、事業所得・雑所得の区別で税率が変わることはありません。
特定の事業にかかる個人事業税
個人事業税は、基本的には事業所得者が納める税金です。ただし、厳密に言えば、個人が営む“特定の事業”(法定業種)にかかる税金です。なので、雑所得者であっても、特定の事業を営んでいれば、事業所得者と同様に課税される場合があります(地方税法72条の50)。
「事業性」とは? 過去の判例など
そもそも法令上は「事業所得」と「雑所得」を区別する明確な基準はありません。したがって、厳密な判定を行うには社会通念に照らし、個別のケースごとに「事業性」の有無を考える必要があります。
「事業性」の要素 – 過去の判例・裁決事例から
| 営利性・有償性の有無 | 何らかの対価として収益を得られるか |
|---|---|
| 継続性・反復性の有無 | 継続して繰り返し収益を得られるか |
| 企画遂行性の有無 | 計画的に収益を得られるよう営まれているか |
| 人的・物的設備の有無 | 従業員や機材などが備えられているか |
| 資金の調達方法 | 相応のリスクを伴って資金を調達しているか |
| 精神的・肉体的疲労の程度 | 精神的・肉体的に相応の労力を投じているか |
| その者の職業・生活状況 | 収入状況などから、事業に合理性が認められるか |
※ 上記は、有名な判例・裁決事例を参考に、重視されやすい要素を簡単にまとめたものです。
税務調査により「事業ではない」との処分を受け、それでもなお不服を申し立てる場合には、社会通念に照らして総合的に判定するしかないでしょう。上記の要素のうち、満たしている要素が多いほど「事業性」が認められやすくなる傾向にあります。
とはいえ、特殊な状況でないかぎり、税務調査は国税庁の通達に沿って行われるはずです。本記事の冒頭で解説したように、帳簿書類の有無によって見分ければ、実務においては概ね問題ないでしょう。
まとめ
事業所得と雑所得は、主に以下のような点で扱いが異なります。なお、事業所得は青色申告を選択できるため、申告方式によって異なる項目もあります。
| 事業所得 | 雑所得 | ||
|---|---|---|---|
| 青色申告 | 白色申告 | ||
| 損益通算 | ○ | ○ | ✕ |
| 青色申告の特典 | ○ | ✕ | ✕ |
| 帳簿作成・保存 | 義務あり | 義務あり(簡易的) | 義務なし |
| 主な申告書類 | ・確定申告書 ・青色申告決算書 |
・確定申告書 ・収支内訳書 |
確定申告書だけ* |
事業所得には青色申告の特典を適用できるため、雑所得より節税はしやすいです。また、事業所得が赤字の場合は、損益通算により他の所得を抑えられるので、トータルで節税につなげられます。一方、雑所得には会計や申告の手間が少ないというメリットがあります。
とはいえ、そもそも「事業所得と雑所得のどっちで申告しようかなぁ」と自由に選べるわけではありません。帳簿書類を保存していない場合や、社会通念上の“事業”に当てはまらない場合、「事業所得」とは認められない恐れがあるので注意しましょう。