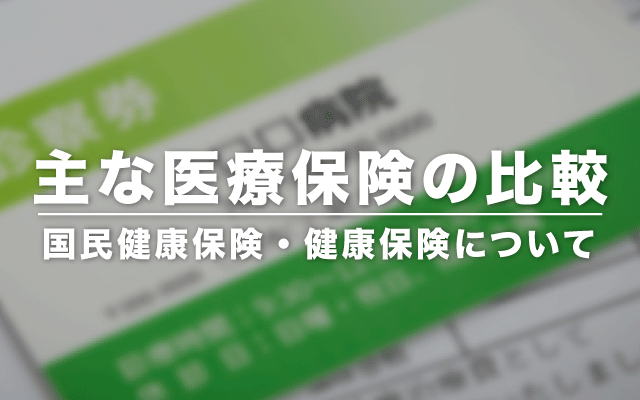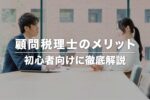主な4つの医療保険について、比較情報を一覧表にまとめました。現役世代の個人事業主や会社員なら、4つのうちのどれか1つにお世話になります。
目次
医療保険のおさらい
現役世代の個人事業主・会社員が加入する医療保険は「国民健康保険」と「健康保険」に大別できます。個人事業主は国保に、会社員は健保に加入します。

- 医療保険は、少ない負担額で治療を受けたり、必要なときに給付を受けたりできる制度
- 加入すると、定期的に保険料を支払う
- 個人事業主は「国民健康保険」に加入する
- 会社員は「健康保険」に加入する
- 保険の運営主体によって、保険料や給付内容などが異なる
国民健康保険の運営主体には「都道府県・市町村」と「国民健康保険組合」があります。健康保険の運営主体には「全国健康保険協会」と「健康保険組合」があります。これらが管理する医療保険についてまとめたのが、次の一覧表です。
4つの医療保険を比較【一覧表】
| 国民健康保険 | 健康保険 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国保 | 組合国保 | 協会けんぽ | 組合健保 | ||
| 運営者 | 都道府県 市町村 |
国民健康保険組合 | 全国健康保険協会 | 健康保険組合 | |
| 主な加入 対象者 |
一般的な 個人事業主など |
業界・地域に 組合がある 個人事業主 |
組合に加入していない 企業の会社員 |
組合に加入している 企業の会社員 |
|
| 加入者数 (10万以下を 四捨五入) |
約2,750万人 | 約270万人 | 約3,940万人 | 約2,950万人 | |
| 保険料の目安 (年額) |
所得の7〜14% (地域による) |
組合によって 大きく異なる |
標準報酬月額 × 12の約10% | 標準報酬月額 × 12の約6~11% (組合による) | |
| 加入者の保険料の負担割合 | 100% (全額自己負担) |
基本100% (全額自己負担) |
50% | 50%以下 (具体的な数値は組合による) |
|
| 法定給付 | 医療費の自己負担 | 現役世代は3割 | |||
| 医療費が高すぎる時の給付 | 高額療養費・高額介護合算療養費 | ||||
| 入院にかかる給付 | 入院時食事療養費・移送費など | ||||
| 出産にかかる給付 | 出産育児一時金のみ | 出産育児一時金 出産手当金 |
|||
| 葬祭にかかる給付 | 葬祭費 or 葬祭の給付 (内容は同一、地域で 名前が異なる) |
埋葬料 or 埋葬費 (死亡した被保険者の状況による) |
|||
| 家族に ついての 給付 |
なし (そもそも「扶養家族」が 存在しない) |
家族療養費・家族埋葬料など | |||
| 任意給付 (国民健康保険 のみの給付) |
なし | 傷病手当金 など |
ー | ||
| 付加給付 (健康保険 のみの給付) |
ー | なし | あり | ||
健康保険組合の「保険料の目安」は、予算編成状況資料編の保険料率別組合数を参照
医療費の一部負担について
ケガや病気で病院にかかったとき、窓口で負担する医療費の割合は、健康保険でも国民健康保険でも同じです。現役世代(6歳~70歳未満)の場合は3割負担、それ以外(0歳~6歳未満、70歳~75歳未満)の場合は基本的に2割負担、と年齢によって異なります。
ちなみに、75歳以上は「後期高齢者医療制度」に加入するため、負担割合は基本的に1割となります。
医療保険の比較【個人事業主向け】
国保と組合国保の比較 – 国民健康保険
| 国保 | 組合国保 | |
|---|---|---|
| 保険料 (年額) |
所得の7〜14% (地域による) |
組合によって大きく異なる |
| 負担割合 | 100% (全額自己負担) |
基本100% (全額自己負担) |
| 運営者 | 都道府県・市町村 | 国民健康保険組合 |
国保の場合、所得が高くなるほど保険料も上がります。対して組合国保の場合、保険料は所得に関係なく定額という組合もあるため、所得が高い人にとってはおトクです。ただし、従業員より事業主の方が保険料は高く設定される傾向にあります。
どちらに入っても構いませんが、基本的には「国保」に加入し、あなたの業種で組合があるなら「組合国保」に加入してもよいと考えましょう。組合には、たとえば「医師国民健康保険組合」や「全国土木建築国民健康保険組合」などがあります。
医療保険の比較【会社員向け】
協会けんぽと組合健保の比較 – 健康保険
| 協会けんぽ | 組合健保 | |
|---|---|---|
| 保険料 (月額) |
標準報酬月額の約10% | 標準報酬月額の約6~10% (組合による) |
| 負担割合 | 50% | 50%以下 (具体的な数値は組合による) |
| 運営主体 | 全国健康保険協会 | 健康保険組合 |
協会けんぽの場合、保険料率が高い上に負担割合も事業主と折半なので、保険料が高くなる傾向にあります。対して組合健保は、料率も負担割合も協会けんぽより少なく設定されていることが多いです。そのため、保険料は低くなりがちな傾向にあります。
こちらは国保とは異なり、従業員が「協会けんぽ」と「健保組合の保険」のどちらかを自分で選ぶことはできません。会社や業界に組合があるなら組合の保険へ、なければ協会けんぽへ加入することになります。