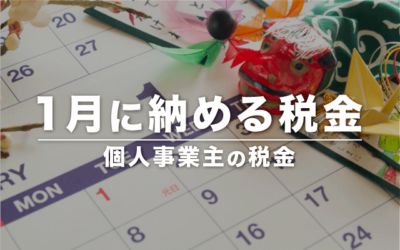2024年12月27日、令和7年度(2025年度)税制改正大綱が閣議決定されました。いわゆる「103万円の壁」についても盛り込まれています。個人事業主向けに、要点だけをわかりやすくコンパクトにまとめました。
目次
2025年度(令和7年度)税制改正大綱の要点 ‐ 個人事業主向け
2025年度の税制改正では、基礎控除が58万円にアップし、扶養控除や配偶者控除などが受けやすくなるようです。いわゆる「103万円の壁」が引き上げられ、個人事業主の税負担も少し軽くなります。

多くの個人事業主・フリーランスにとって関係がありそうな改正項目は、だいたい上記のとおりです。すぐには適用されないものもあるので、開始時期はよく確認しておきましょう。
そもそも「控除」とは? 個人事業主向けのわかりやすい解説
2025年 税制改正のスケジュール – 2月上旬ごろに法案化

税制改正大綱(たいこう)とは「税金のルールをこんなふうに変えたいです!」という政府の方針をまとめたものです。あくまで方針であって、まだ正式に法律として決まったわけではありません。
例年は、大綱のとおりに改正されることが多いです。ただ、現在は与党が国会で過半数を占めていないため、内容が変わる可能性もあります。
① 基礎控除などの引き上げ【103万円の壁】
- 2025年分から、いわゆる「103万円の壁」が引き上げとなる
- 基礎控除が10万円アップして58万円になる(現行48万円)
- 扶養控除や配偶者控除などの要件も緩和される
「103万円の壁」とは、アルバイト代などで「年収103万円を超えたら所得税が発生しますよ」という意味の用語です。103万円の内訳は、基礎控除48万円と給与所得控除55万円です。このうち、基礎控除は個人事業主にも適用されます。

「103万円の壁」が引き上げられると、アルバイトやパートの人だけでなく、個人事業主やフリーランスの税負担も軽くなります。給与所得控除の影響があるのは会社に雇われている人だけですが、上図の通り、基礎控除については個人事業主にもきちんと影響があります。

たとえば、課税所得(収入−経費−所得控除)がおよそ400万円の個人事業主であれば、所得税の税率は20%です。そのため、基礎控除が10万円アップすると、1ヶ月あたり1,667円ほど手取りが増える計算になります。
ほかの控除も受けやすくなる(主な例)‐ 基礎控除アップの影響

基礎控除と給与所得控除の引き上げにともない、上記のように他の控除も受けやすくなります。改正後は、配偶者や子の所得が58万円以下であれば「同一生計配偶者」や「扶養親族」として認められます(現行制度では48万円以下)。
創設予定の「特定親族特別控除(仮称)」は、大学生などの子どもが103万円以上稼いだ場合でも、親の税負担がいきなり跳ね上がることがないようにする仕組みです。子どもが稼いだ金額に応じて、親の控除額が63万円から3万円まで段階的に減少します。
② 生命保険料控除の拡充 – 子育て世帯向け
- 23才未満の扶養親族がいる人のみが拡充の対象
- 一般生命保険料の控除額が上限6万円にアップ(現行4万円)
- その他の保険料を含めたトータルでの控除上限は12万円で据え置き

2026年分から、23才未満の扶養親族がいる子育て世帯は、一般生命保険の掛け金が年間12万円以上であれば、6万円の生命保険料控除が受けられるようになります(現行制度では4万円が上限)。詳しい計算式については、下表をご覧ください。

なお、23才未満の扶養親族がいない場合は、従来の計算式がそのまま適用されます(控除上限は4万円のまま)。また、住民税に関しては大綱に記載がないため、上記のような生命保険料控除の拡充は行われない見込みです。
③ iDeCoの拠出限度額アップ – 個人事業主も対象
- iDeCoの拠出限度額(掛け金の上限)がアップ
- 個人事業主は最大で月75,000円に(現行68,000円)
- 「小規模企業共済等掛金控除」による節税額も増やせる
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、税制優遇を受けながら老後に向けた資産運用ができる制度です。個人事業主・フリーランスには会社員のような退職金制度がないため、こうした制度をうまく活用しながら老後に備える必要があります。
イデコの掛け金は「小規模企業共済等掛金控除」の対象ですので、掛け金が多いほど節税額が増えます。個人事業主の場合、今回の改正により上限が月7,000円アップします。年間の控除額でいうと、上限まで掛けている人は84,000円増える計算です。
ただし、後述しますが、iDeCoについては受け取り時の改悪も行われる見込みです。今後iDeCoを利用する方は、そちらも併せてご確認ください。
iDeCo受け取り時の改悪 – 退職所得控除の5年ルール→10年ルール
④ 青色申告特別控除65万円の要件が一部変更
- 65万円の青色申告特別控除を受ける際の選択肢が増える
- これまで通り、電子申告でも65万円控除は受けられる
2027年分から、青色申告特別控除の要件が一部変更されます。といっても、従来と同じ要件を満たしていれば引き続き65万円控除は受けられるので、これまで65万円控除を受けてきた個人事業主は気にしなくてOKです。

「電子取引データ」とは、メールでやり取りした請求書などを指します。取引先からPDFで受け取った請求書や、ネットショッピングをしたときに発行される電子明細などがこれに該当します。
現行の青色申告特別控除65万円の要件まとめ
⑤ 国民健康保険料の上限アップ
- 国民健康保険料の上限額が「92万円」に引き上げ
- 基礎分:65万円→66万円
- 後期高齢者支援金分:24万円→26万円
国民健康保険料の上限額は、4年連続で増加となる見込みです。2024年度は年間89万円が上限でしたが、2025年度は3万円引き上げとなり、上限額は年間92万円となるようです。

国民健康保険料の上限額を気にする必要があるのは、所得が一定以上の人だけです。一人暮らしの個人事業主・フリーランスであれば、所得が1,000万円ぐらいで上限額に到達します(事業収入 − 必要経費 = 事業所得)。
なお、国民健康保険料は世帯で計算されます。そのため、夫婦がどちらもフリーランスとして収入を得ている場合などでは、それぞれの所得が500万円程度であっても、保険料の上限に到達する場合があります。
国民健康保険料の仕組みや計算方法をわかりやすく解説
⑥ 退職所得控除の5年ルールが変更 – iDeCoにも影響あり
- 退職所得控除の「5年ルール」が「10年ルール」に変更
- iDeCoと小規模企業共済の受け取り時期を10年以上ずらす必要がある
- このルールを守らないと退職所得控除が減り、税負担が増える

2026年から、退職所得控除のルールが上図のように変更され、事実上の増税となります。iDeCoと小規模企業共済の両方に加入している個人事業主は、受け取り間隔を10年以上空けないと、退職所得控除をフル活用できずに税負担が増えます。
iDeCoは60才にならないと受け取れないので、退職所得控除をフル活用したければ、少なくとも70才までは現役で仕事を続けながら小規模企業共済に加入しておく必要があります。かなりハードルが高くなるため、事実上の増税と言えるでしょう。
退職所得控除の計算方法をわかりやすく解説
まとめ
2025年度(令和7年度)の税制改正大綱について、個人事業主に関係がありそうな改正は以下の通りです。とくに「103万円の壁」の引き上げにともない、基礎控除が10万円アップする点は、ほぼすべての個人事業主に影響があります。
- 基礎控除が48万円から58万円に【103万円の壁】
- 一般の新生命保険料の控除額が4万円から6万円に(子育て世帯のみ)
- iDeCoの拠出限度額が6.8万円から7.5万円に
- 青色申告特別控除で「電子取引データ」に関する要件が追加
- 国民健康保険料の上限額が92万円に(介護保険分を除く)
- 退職所得控除を満額利用するための「5年ルール」が10年に
※ 太字は2025年(令和7年)から適用開始
上記のうち、2025年からすぐに適用開始となるのは、太字で示した「①基礎控除」と「⑤国民健康保険料」だけです。ほかは2026年以降の話なので、急いで対応する必要はありません。
その他の主な改正内容 ‐ 2025年度(令和7年度)税制改正大綱
- NISAの利便性向上
- 住宅ローン控除、住宅リフォーム税制(子育て世帯支援)
- 固定資産税の課税標準の特例措置の2年延長
- 事業承継税制における役員就任要件等の見直し
- 結婚・子育て資金の一括贈与に関する非課税措置の2年延長
- 外国人旅行者向け免税制度の見直し(不正防止)
- たばこ税の見直し(税率引き上げなど)
>> 令和7年度 税制改正の大綱(令和6年12月27日 閣議決定) ‐ 財務省
2025年度の税制改正大綱には、本記事で解説した改正のほか、上記のような項目も盛り込まれています。基本的には大綱の通りに改正が行われるのが通例ですが、法案が国会で可決されるまでは、途中で変更される可能性もあります。