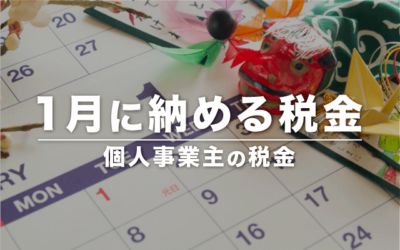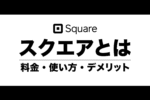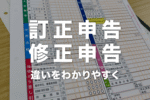個人事業主やフリーランスが受けられる「所得控除」を一覧表にまとめました。控除額や適用条件もわかりやすく解説しています。
目次
個人事業主の所得控除【一覧】
| 社会保険料控除 | 国民年金や国民健康保険の保険料を納めたときの控除 控除額:その年に支払った保険料の全額 |
|---|---|
| 小規模企業共済等 掛金控除 |
小規模企業共済や確定拠出年金の掛金を支払ったときの控除 控除額:その年に支払った保険料の全額 |
| 生命保険料控除 | 生命保険(民間の保険会社によるもの)などを支払ったときの控除 控除額:最高12万円 |
| 地震保険料控除 | 地震保険料などを支払ったときの控除 控除額:最高5万円 |
| 寡婦控除 | 夫と離婚や死別をした女性の控除 控除額:27万円 |
| ひとり親控除 | シングルマザー・シングルファザーの控除 控除額:35万円 |
| 勤労学生控除 | 学校に通いながら働いている人の控除 27万円 |
| 障害者控除 | 本人や配偶者、扶養親族が障害者である人の控除 控除額:1人につき27万 or 40万 or 75万 |
| 配偶者控除 | 対象の配偶者がいる場合に受けられる控除 控除額:13万円 or 26万円 or 38万円 |
| 配偶者特別控除 | 配偶者控除の対象外でも条件を満たせば受けられる控除 控除額:1万円~38万円 |
| 扶養控除 | 16歳以上の扶養親族がいる人の控除 控除額:1人につき38万円〜63万円 |
| 特定親族特別控除 | 扶養控除の所得要件をオーバーしたときの控除 控除額:1人につき最大63万円 |
| 基礎控除 | ほとんどの人が適用できる控除 控除額:16万円〜95万円 |
| 雑損控除 | 災害などで住宅や家財に損害を受けたときの控除 控除額:損失額に応じた金額 |
| 医療費控除 | 医療費などを一定額以上支払ったときの控除 控除額:その年に払った医療費に応じた金額 |
| 寄附金控除 | 特定の団体に寄附をしたときの控除(ふるさと納税を含む) 控除額:対象となる寄附金額 – 2,000円 |
| 青色申告特別控除 | 青色申告者だけが受けられる控除(厳密には所得控除ではないが、同様の節税効果がある) 控除額:10万 or 55万 or 65万 |
注意したいのは、控除額そのままの金額を税金から差し引くわけではないということです。たとえば、95万円の基礎控除を適用したからといって、税金が95万円まるまる少なくなるわけではありません(詳細は後述)。
家族の分も受けられる控除
医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・雑損控除は、生計が同じ家族の分を納税者が支払っている場合、その分を含めて控除額を計算できます。家族のなかで一番所得が多い人が家族分の医療費や保険料を支払っていれば、節税につながるというわけです。
所得控除とは?節税につながる理由
所得税は、一年間の所得金額をベースに納税額を算出します。しかし同程度の所得でも、一人暮らしの人もいれば、子や親を養っている人もいます。そういった個人・家庭的な負担を軽減するために「所得控除」があります。
そもそも、所得税の金額は以下のような流れで算出します。

所得控除の金額が大きいほど「課税所得」の金額が少なくなります。課税所得が少なければ、そのぶん所得税額も少なくなります。所得(収入 − 経費)が同じくらいでも、下図のような差が生まれるわけです。

ただ、所得控除は申告をし忘れるとその恩恵を受けることができないので、忘れずに申告しましょう。
確定申告で所得控除を受ける流れ
所得控除を受けるために、計算した控除額を確定申告書に記入します。確定申告は、原則2月16日~3月15日の間に行います。
確定申告で提出する「確定申告書」の第一表に、控除額を記入する欄が設けられています。第二表には、控除額の算出に関わる情報(保険料の支払い金額など)を記入します。
| 確定申告書 第一表 | 確定申告書 第二表 |
|---|---|
 |
 |
所得控除は住民税の金額にも影響する
所得控除は、所得税だけでなく住民税の納税額を計算する際にも適用されます。とはいえ住民税の金額は、確定申告の内容に基づいて納付先の自治体が納税額を算出してくれるので、自分で行う必要はありません。
所得税と住民税の違い
| 所得税(国税) | 住民税(地方税) | |
|---|---|---|
| 税額の計算 | 自分で計算して申告 (申告納税方式) |
市区町村が計算して通知 (賦課課税方式) |
| 納付時期 | 原則3月15日までに納付 | 6月頃に届く通知書に従って納付 |
住民税の場合も所得税と同様に、控除額が大きいほど節税につながります。ただ控除額の上限は、所得税よりも低く見積もられていることがほとんどです。
所得税と住民税の控除額を比較【一覧】
納付する住民税を計算するときの税率は、自治体によって異なりますが基本的には一律10%です。それと同様に、住民税の控除額もだいたいの地域で同じ金額が設定されています。所得税の控除額とまったく同じものもあれば、低く設定されているものもあります。
住民税の計算において、所得税の場合と同じ控除額が適用されるのは「雑損控除」「医療費控除」「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」「青色申告特別控除」の5つです。
控除額が同じ所得控除
| 所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|
| 社会保険料控除 | その年に支払った保険料の全額 | |
| 小規模企業共済等掛金控除 | その年に支払った保険料の全額 | |
| 雑損控除 | 損失額に応じた控除額 | |
| 医療費控除 | その年に支払った医療費などに応じた控除額 | |
| 青色申告特別控除 | 10万円 or 55万円 or 65万円 | |
上記5つ以外の所得控除は、所得税を計算する場合よりも控除額が低めです。ものによっては、住民税では半分程度の控除しか適用されないものもあります。
控除額が異なる所得控除
| 所得税の控除額 | 住民税の控除額 | |
|---|---|---|
| 生命保険料控除 | 最高12万円 | 最高7万円 |
| 地震保険料控除 | 最高5万円 | 最高25,000円 |
| 寡婦控除 | 27万円 | 26万円 |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 |
| 障害者控除 | 27万円 or 40万円 or 75万円 | 26万円 |
| 配偶者控除 | 13万円 or 26万円 or 38万円 | 11万円 or 22万円 or 33万円 |
| 配偶者特別控除 | 1万~38万円 | 1万~33万円 |
| 扶養控除 | 原則38万円 | 原則33万円 |
| 特定親族特別控除 | 最大63万円 | 最大45万円 |
| 基礎控除 | 最高95万円 | 最高43万円 |
| 寄附金控除 | 特定寄附金 - 2,000円 = 控除額 (総所得金額の40%まで) |
特定寄附金 - 2,000円 = 控除額 (総所得金額の30%まで) |
「基礎控除」と「青色申告特別控除」は国保の保険料にも適用
個人事業主が加入する「国民健康保険」(以下「国保」)の保険料を計算する際にも、控除は活躍します。該当するのは「基礎控除」と「青色申告特別控除」の2つのみ。以下の金額が控除されます。
国民健康保険での控除額
| 控除額 | |
|---|---|
| 基礎控除 | 最高43万円 |
| 青色申告特別控除 | 10万円 or 55万円 or 65万円 |
国保の保険料は、住んでいる地域ごとに異なります。個人事業主の場合は保険料を全額負担しなくてはならないので、負担を軽減してくれる控除はありがたいです。
>> 国保の詳細
ちなみに、その年に支払った国保の保険料は「社会保険料控除」の対象です。そちらの申告も忘れずに行いましょう。
所得控除のまとめ
所得控除は、納税者の家庭環境や生活状況などのプライベートに関わる部分を考慮して、税金をおさえてくれる制度です。個人事業主が受けられる控除は、最大15種です。
所得控除の重要ポイント
- 控除額が大きいほど、納める税金が少なくなる
- 控除額そのままの金額が税金から差し引かれるわけではない
- 医療費や保険料などは生計を一にする家族の分も支払っていれば控除の対象になる
- 「基礎控除」「社会保険料控除」は納税者のほとんどが控除の対象
- 「障害者控除」「扶養控除」は対象者一人ごとに控除が適用される
- 所得控除を受けるには、控除額などを確定申告書に記入する
事業主自身の社会保険や生命保険などのプライベートな保険料は「所得控除」の対象です。「必要経費」として収入から差し引くことはできません。ただし、自宅兼事務所に対する保険の場合などは家事按分して一部を所得控除に、一部を必要経費にできます。