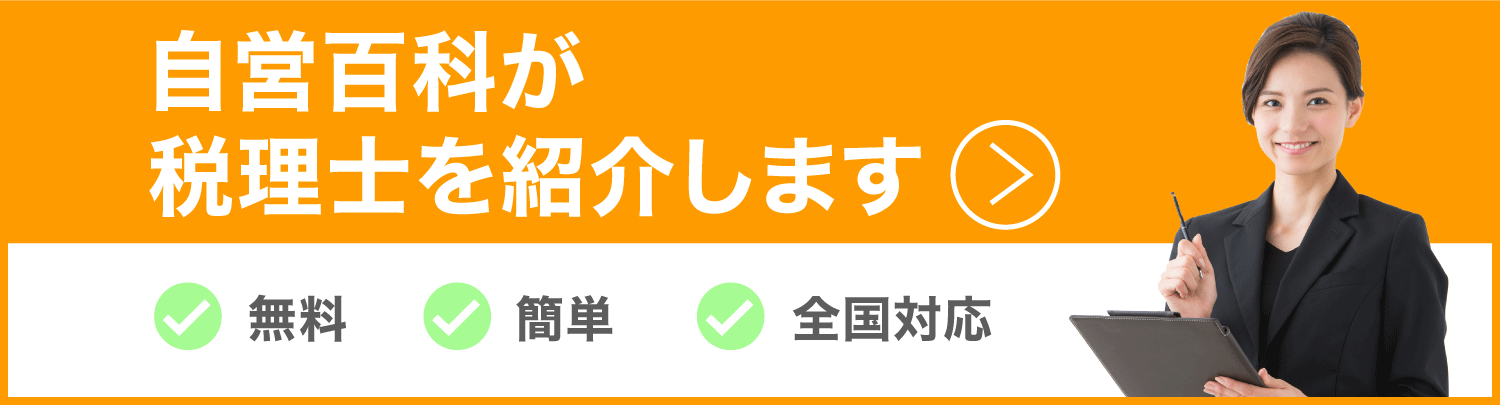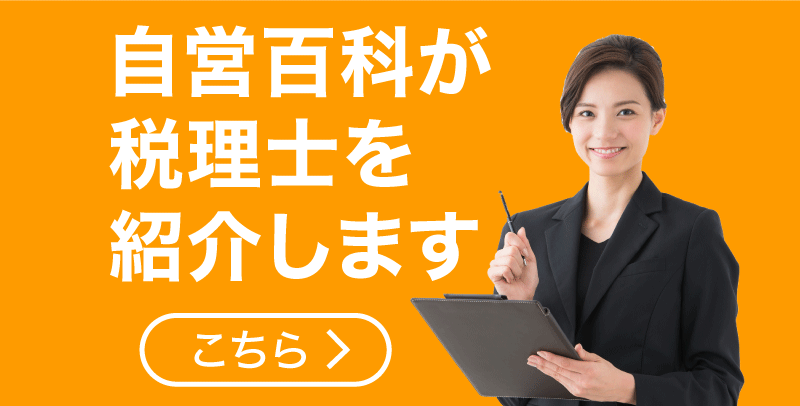個人事業主やフリーランス向けに、必要経費の勘定科目を一覧表にまとめました。具体例付きでわかりやすく解説します。
目次
個人事業主の必要経費【勘定科目一覧表】
確定申告の決算書に載っている勘定科目
| 概要と具体例 | |
|---|---|
| 租税公課 | 事業で課される税金や公的な団体に払う負担金 個人事業税・固定資産税・自動車税・収入印紙代 |
| 荷造運賃 | 商品などを発送する際の費用 ダンボール箱・エアパッキン・宅配便代・航空便 |
| 水道光熱費 | 事業に必要なエネルギーインフラにかかる費用 水道代・電気代・ガス代・暖房灯油代 |
| 旅費交通費 | 仕事上の移動にかかる費用や宿泊費用 電車賃・バス運賃・タクシー代・出張時のホテル代 |
| 通信費 | 事業の通信や郵便にかかる費用 電話料金・インターネット料金・切手代・ハガキ代 |
| 広告宣伝費 | 事業や商品を不特定多数へ向けて宣伝する際の費用 ポスター・メルマガ・看板・HPの制作費用 |
| 接待交際費 | 事業を円滑に行うための交流にかかる費用 取引先との飲食代・お中元・お歳暮 |
| 損害保険料 | 事務所や店舗・商品などに対する損害保険の費用 自動車保険・火災保険・盗難保険 |
| 修繕費 | 固定資産を修理・改良する費用 コピー機の修理・パソコンの保守料・タイヤ交換 |
| 消耗品費 | 短い期間で消耗してしまう事務用品などの費用 ノート・安価なパソコン・ソフトウェア |
| 減価償却費 | 固定資産を減価償却する際に使う科目 事務所や店舗などの建物・自動車・高額なパソコン |
| 福利厚生費 | 従業員の生活向上や労働環境改善を目的とした費用 健康診断費・慰安旅行費・忘年会費・残業中の食費 |
| 給料賃金 | 従業員に支給する給料 基本給・残業代・賞与・退職金 |
| 外注工賃 | 外部の業者などに仕事を委託するときの費用 デザイン発注・業務委託費用・事務代行・営業代行 |
| 利子割引料 | 事業用に借り入れをした際の利子など 金融機関の支払利息・自動車ローン |
| 地代家賃 | 事業所や店舗にかかる賃借料や使用料 家賃・レンタルオフィスの料金・月極駐車場の賃料 |
| 貸倒金 | 売掛金などが回収不能になった際の損失 取引先が倒産したために回収できなくなった売掛金 |
| 雑費 | どの勘定科目にも当てはまらない少額の費用 ゴミ処理代・引っ越し代・清掃代 |
| 専従者給与 | 青色事業専従者(家族従業員)に支払う給料 |
個人事業主の場合、経費計上できる金額に上限はありません。ただ、一部の勘定科目だけ金額が大きいと、税務署の目に止まりやすいです。金額を分散して整理するために、任意で勘定科目を追加することもできます。
任意で追加する勘定科目(主な例)
| 概要と具体例 | |
|---|---|
| 支払手数料 | 支払時にかかる手数料 振込手数料・仲介手数料・証明書発行手数料 |
| 事務用品費 | 事務用品の購入費用 文房具・コピー代・事務用机・インクカートリッジ |
| 新聞図書費 | 情報収集のために必要な新聞紙や書籍などの費用 新聞紙代・書籍代・雑誌の定期購読料 |
| 取材費 | 原稿を執筆するための取材にかかる費用 取材にかかる交通費や宿泊費・インタビュー時の食事代 |
| パソコン関連費 | パソコンやパソコン周辺の機器などの費用(10万円未満) パソコン本体・プリンター・ハードディスク・ソフトウェア |
| 車両関連費 | 業務用の車両に関係する出費 ガソリン代・車検費用・ETC代 |
| ちんしゃくりょう 賃借料 |
機械や設備などを外部から借りる際の費用 工具や家具のレンタル料・レンタルオフィスの一時的な利用料 |
| リース料 | 事務用品や機械などのリース費用 コピー機・パソコン・ファックス・自動車などのリース代 |
| 会議費 | 取引先と打ち合わせする際にかかる費用 会食代・会議に使った会場代・弁当代・お茶代 |
| しょかいひ 諸会費 |
同業者の団体や自治体などの会費 商工会費・町内会費・カード年会費 |
| 研修費 | 業務に必要なスキルを習得するためにかかる費用 セミナー参加費・資格取得のためのテキスト代 |
上記に挙げた勘定科目は、決算書には載っていませんが、一般的によく使われています。個人事業主向けの会計ソフトでは、これらの勘定科目が標準で設定されている場合もあります。
どんなときに勘定科目を追加する?
確定申告で使う決算書には19種類の勘定科目が載っていますが、自分で勘定科目を追加することもできます。むやみに増やすのはおすすめできませんが、下記のような場合には勘定科目を追加しましょう。
- 特定の勘定科目がふくらみすぎているので、複数に分けて管理したい
- 該当する勘定科目が複数あって迷うので、ひとつにまとめたい
勘定科目の追加によって、例年と比べて決算書の見え方が大きく変わってしまう場合は、決算書にある「本年中における特殊事項」という欄に変更内容を記入しておけば良いです。
ケース① 複数の勘定科目に分けて管理したい
たとえばフリーライターの場合、取材にかかる費用も「旅費交通費」に計上していると、取材にいくら使ったのかわかりにくいです。この場合は「取材費」という勘定科目を追加して、取材関連の費用を普段の交通費を分けて計上することで、支出の流れがより明確になります。

ケース② ひとつの勘定科目にまとめたい
たとえば、自動車に関する費用は様々な勘定科目に分類されます。自動車を持っている人は「車両費」という勘定科目を作成すると、細々とした支出をひとつの勘定科目にまとめられるので、帳簿付けがカンタンになります。

必要経費を帳簿付けするときのポイント
ポイント① 自分なりのルールを決めておく(継続性の原則)
勘定科目のなかには似ているものも多く、どれで仕訳すべきか迷うことがあります。判断が難しいものについては、ひとまず「コレ!」と決めた勘定科目を使い続けることが大切です。
たとえば「接待交際費」と「会議費」は使い分けに迷いやすい勘定科目ですが、下記のようなルールを決めておくと明瞭に整理できます。
接待交際費と会議費の使い分けルール(例)
- 飲食代が一人あたり5,000円以内の打ち合わせ費用……会議費
- 会議費に当てはまらない打ち合わせ費用……接待交際費
ちなみにこのルールは、法人企業における接待費と会議費の使い分けルールを参考にしています。個人事業主には一律のルールがないので、このように自分で決めておくとよいでしょう。
ポイント② 領収書は7年間保管しておく
必要経費の領収書やレシートは保管しておく必要があります。保存期間は、白色申告なら「5年間」、青色申告なら「7年間」です。いつ・誰に・何を・いくら支払ったかということがわかれば、レシートでも問題ありません。
領収書やレシートがもらえない場合は、出金伝票を作っておきましょう。出金伝票はコンビニなどでも売っています。レシートが出ない支出があったときのために、ひとつ持っておくと良いです。
出金伝票の記入例

ポイント③ 10万円超の備品は減価償却する
高額なパソコンや自動車などを購入したら「減価償却」という処理が必要です。この場合、購入費用を数年にわたって少しずつ経費にしていきます。
ポイント④ プライベートでも使うなら家事按分する
自宅兼事務所の家賃など、事業とプライベートの両方に関わる支出は「事業に関わる金額」だけを経費に計上します。このような会計処理を「家事按分」といいます。水道光熱費・通信費・地代家賃などは、家事按分をすることが多いです。
確定申告で必要経費はどこに書く?
確定申告の際には、必要経費の金額を勘定科目ごとに分けて書きます。白色申告なら「収支内訳書」、青色申告なら「青色申告決算書」に記入欄があります。
| 収支内訳書 | 青色申告決算書 |
|---|---|
 |
 |
なお、任意で追加した勘定科目は空欄のところに記入します。空欄が足りなくなるとちょっと面倒なので、追加する勘定科目は5つくらいに抑えておくのがおすすめです。
個人事業主の必要経費に関する疑問まとめ【Q&A】
- そもそも必要経費とは?
- 必要経費とは、事業を行うために直接必要となる支出のことです。税金や保険料は「所得」が多いほど高くなりますが、この「所得」は収入から必要経費などを差し引いて算出します。
- 白色申告と青色申告で必要経費の扱いは違う?
- 必要経費の範囲は基本的にどちらも同じです。唯一の違いとして、白色申告では家族従業員への給与を一部しか経費扱いにできませんが、青色申告では「専従者給与」の勘定科目で全額経費にできます。
- 税金や保険料も必要経費にできる?
- 事業に関わる個人事業税や固定資産税は「租税公課」の勘定科目で必要経費に計上できます。一方、所得税・住民税・国民年金・健康保険料などは、あくまで個人にかかるお金なので必要経費にはできません。
- 領収書がない支出は必要経費にできる?
- 領収書がなくても、なんらかの証拠があれば経費にできます。振込明細やクレジットカードの利用明細などを保存しておきましょう。
- 領収書じゃなくてレシートでもいい?
- レシートでも問題ありません。「いつ・誰に・何を・いくら支払ったか」ということがわかれば、領収書でもレシートでもとくに違いはありません。
まとめ
事業で収入を得るために必要な支出は、必要経費に計上できます。個人事業の確定申告で提出する決算書においては、経費の勘定科目が19個用意されています。費用の使途に応じて、適切な勘定科目で記帳しましょう。
個人事業主の必要経費の重要ポイント
- 事業に必要な支出が必要経費として計上できる
- 事業と私用の両方で使うものは、家事按分してその一部を経費にできる
- 特定の勘定科目だけ金額がふくらまないように配慮する
- もともと決算書にない経費の勘定科目をつくってもOK
- 同じ内容は同じ勘定科目で毎回記帳すること(継続性の原則)
- 領収書やレシートは白色申告の場合5年、青色申告の場合7年保管する
支出の内容によっては、どの勘定科目で仕訳をしていいか悩むものもあります。たとえば、自動車のガソリン代は「消耗品費」で計上する人もいれば、「旅費交通費」と考える人もいます。
このような複数の勘定科目があてはまる支出については、自分で決めた勘定科目で毎年仕訳をしていけばOKです。一度決めた会計基準を更新したい場合は、決算書の「本年中における特殊事項」という欄に変更内容を記入しておきます。