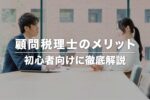目次
特例の概要
新型コロナの影響で収入が減少した人は、保険料の「減免」か「猶予」を受けられる可能性があります。国民年金と国民健康保険の対応状況は、下記のとおりです。
| 減額・免除 | 納付猶予 | |
|---|---|---|
| 国民年金 | ◯ コロナ特例あり |
◯ コロナ特例あり |
| 国民健康保険 | ◯ コロナ特例あり |
× コロナ特例はない* |
*ベーシックな猶予制度を適用できる可能性はある
本記事では、全国的に利用できる、新型コロナ関連の特例措置について説明します。本記事で説明する要件が満たせなくても、自治体が独自の制度を設けている場合があるので、お住まいの自治体ホームページなどもあわせてご確認ください。
国民年金の特例措置
| 減額・免除 | 納付猶予 |
|---|---|
| ◯ コロナ特例あり |
◯ コロナ特例あり |
国民年金の減免・猶予制度は、本来「前年の所得が基準を下回る人」を対象とした制度です。しかし、現在はコロナ関連の特例的な措置として「当年の所得見込額が基準を下回る人」も利用できるようになっています。
免除制度の概要
| 要件 |
|
|
|---|---|---|
| 基準額 | 全額免除 | (扶養親族等の数 + 1 ) × 35万円 +22万円 |
| 4分の3免除 | 78万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 | |
| 半額免除 | 118万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 | |
| 4分の1免除 | 158万円+ 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 | |
| 受給への影響 |
|
|
猶予制度の概要
| 要件 |
|
|---|---|
| 基準額 | (扶養親族等の数 + 1) × 35万円 + 22万円 |
| 受給への影響 |
|
減免・猶予制度を利用した人は、10年以内であれば任意で追納することができます。猶予制度も含め、追納しない場合のペナルティはありません。ただし、将来の受給額は少なくなったままです。
申請方法(国民年金)
コロナ特例による減免・猶予制度の申請受付は、すでに始まっています。令和2年2月以降の保険料なら、さかのぼって申請することもできます。
| 必要書類 |
|
|---|---|
| 提出先 | 住所地の市区町村役場 or 年金事務所 |
| 提出方法 | 郵送が基本(推奨はしていないが窓口での提出も可能) |
*日本年金機構のHPからダウンロードできる
申請書には、免除割合などを記入する欄がありますが、この部分は基本的に記入不要です。ひとまず、その他の情報を記入しておけば、具体的な免除区分等は機構側が審査・決定してくれます。
国民健康保険の特例措置
| 減額・免除 | 納付猶予 |
|---|---|
| ◯ コロナ特例あり |
× コロナ特例はない |
国民健康保険料の減免については、厚生労働省が各自治体に「コロナの特例でこういうふうに対応してくださいね」という通達を出しています。これによると、下記のいずれかに該当する人は、特例的な保険料の減免を受けられます。
コロナ特例で保険料の減免を受けられる人
- 新型コロナで生計維持者が死亡 or 重篤な傷病を負った人
- 新型コロナで生計維持者の収入が減った人
ここで言う「生計維持者」は、原則として「国民健康保険の世帯主」を指します。自分で保険料を納めている人は、自分が上記に該当するかどうかで考えればOKです。
パターン1. 新型コロナで生計維持者が死亡 or 重篤な傷病を負った人
| 要件 | とくになし |
|---|---|
| 免除額 | 保険料の全額が免除される |
パターン2. 新型コロナで生計維持者の収入が減った人
| 要件 |
下記のすべてに該当すること
|
|---|---|
| 免除額 | 生計維持者の所得に応じて減免割合が異なる |
なお、国民健康保険料の「猶予」に関するコロナ特例はありません。ただ、法律では災害時などを想定した猶予制度が設けられおり、それを利用できる場合もあります。利用の可否は自治体の判断によるので、気になる人は自治体のHPなどを確認してみましょう。
申請方法(国民健康保険)
国民健康保険の減免額は、申請書類を提出すれば自治体側が計算してくれます。「そもそも要件を満たしているか分からない」という人は、とりあえず申請しておいて、審査結果を待つのもアリです。
| 主な必要書類 |
|
|---|---|
| 提出先 | 住所地の市区町村役場 |
| 提出方法 | 直接提出 or 郵送 |
必要な添付書類は、前述の「パターン1」と「パターン2」のどちらに該当するかによって異なります。
主な添付書類
| パターン1の場合 |
次のいずれかの写しを添付する
|
|---|---|
| パターン2の場合 |
以下全ての書類を添付する
|
令和3年度分(2021年度分)の減免申請は、原則として令和4年(2022年)3月31日が期限となっています(自治体によって期日や必要書類が異なる場合があります)。