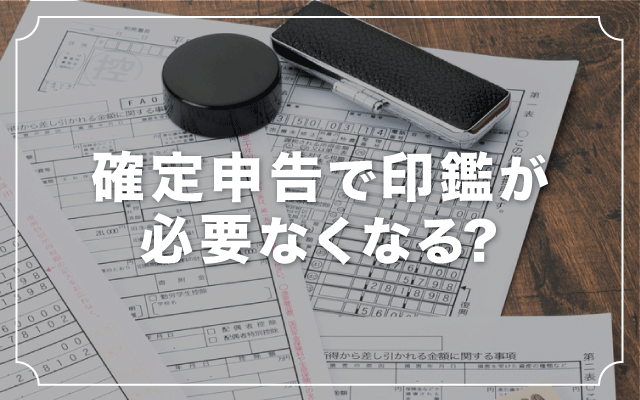2022年1月追記:本改正により、現在は確定申告などの様々な行政手続きで、押印が不要になっています。新様式の確定申告書からは、印鑑の欄がなくなりました。
>> 確定申告書類の書き方 – 新様式の申告書
目次
確定申告でハンコが要らなくなった?
2020年12月、国税庁は、税務関係書類の押印義務を原則として廃止することを発表しました。これにともない2021年4月1日からは、いわゆる「認印」で済む税務関係の書類について、押印義務が廃止されました。
脱ハンコの対象・対象外(一例)
| 脱ハンコの対象 | 脱ハンコの対象外 |
|---|---|
|
|
| 「認印」で済んでいたもの およそ15,000種類 |
「実印」が必要なもの 83種類 |
対象となったのは、およそ1万5,000種類の行政手続きのうち、押印が認印で済んでいたものです。実印が必要となる手続き(法人登記など83種類)については、以前の通り押印が必要です。
- 「実印」と「認印」の違い
- 実印は、印鑑登録を済ませたハンコのこと。印鑑登録を行うと「印鑑証明書」を受け取ることができる。不動産の売買時や自動車の契約時など、重要な契約の際に使用する。
認印は、個人が日常生活において使用するハンコのこと。印鑑登録は不要で、買ってきてそのまま利用できる。宅急便の受取や、社内書類の確認など、様々な場面で使用する。
一足早く「脱ハンコ」を進めてきた自治体も
地方自治体によっては、以前から脱ハンコを進めている地域もありました。福岡市は、2019年から独自で脱ハンコの取り組みを進め、2020年9月末には市へ提出される申請書等の押印義務をすべて廃止しました(国や県の法令で押印が義務付けられているものなどを除く)。
また、脱ハンコの流れを受けて、新たに脱ハンコに踏み出した自治体も増えています。東京都は、行政手続きで必要とされていた押印の多くを廃止しました。ハンコを廃止する代わりに、電子署名や電子申請を整備することで、脱ハンコを徹底していく意向です。
政府は「押印廃止マニュアル」を発表
2020年12月18日、河野大臣は、地方自治体に向けた「押印廃止マニュアル」を作成したと発表しました。このマニュアルは自治体に通知されたほか、内閣府のホームページにも掲載されています。
車庫証明などもハンコが不要に
警察が対応する手続きでも、脱ハンコの取り組みが進んでいます。警察庁は2020年10月22日、車庫証明や道路使用許可など315種類の行政手続きで、押印を原則廃止する方針であると発表しました。
2021年中には、下記のような手続きで、ハンコが不要となっています。すでに押印廃止を進めている地域も多いですが、具体的な対応状況は地域によって異なります。
押印廃止となる主な行政手続き
- 車庫証明
- 道路使用許可
- 猟銃や空気銃の所持許可
- 古物商や質店の営業許可
- 警備業の認定
一部の手続きについては、オンライン化も検討されています。河野大臣は、2021年度から道路使用許可などの手続きをメールで申請できるよう準備を進めることを表明しています。
また、運転免許の取得についても、卒業証明書などの押印の廃止や、学科教習のオンライン受講が実現できるよう、関係者と調整を進める方針であると発表されました。
抗議の声も – 自民党「はんこ議連」の主張
一部では、脱ハンコに難色を示す声も上がっています。自民党員で結成された「日本の印章制度・文化を守る議員連盟」(通称、はんこ議連)は、今回の政策について抗議の姿勢を示しています。2020年10月8日、「はんこ議連」は政府に対して、はんこ事業者への風評被害の防止を要請しました。
はんこ議連会長代行の城内実氏は、デジタル化の推進には理解を示しつつも、全面的なハンコの廃止に関しては「行き過ぎ」と指摘しています。城内氏は、紙やハンコにこだわりたい人や、高齢者などのインターネットに不慣れな人が、社会の潮流から取り残されてしまうことを危惧しているようです。
また、ハンコ文化の根付いた日本において、“意思の担保”という側面では、サインよりもハンコが優れている、とも主張しました。城内氏は、現在の社会においてはサインよりハンコのほうが書類や契約に信用感が出る、と見解を示しています。