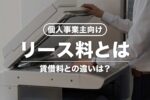個人事業主・フリーランス向けに、福利厚生費についてまとめました。経費計上できる条件や、福利厚生費の具体例などを解説します。
目次
個人事業主の福利厚生費とは?
福利厚生費とは、労働環境の改善などを目的として、事業主が「従業員のために負担する費用」のことです。具体的には、下記のような費用が該当します。
福利厚生費の具体例
- 従業員の社会保険料(事業主が負担する分)
- 従業員の通勤手当
- 従業員との飲み会費用
- 従業員の食事補助
- 従業員への慶弔見舞金
- 従業員の健康診断費用
- 従業員の住宅手当・家族手当など
ここでいう「従業員」とは、雇用関係を結んでいる労働者のことです。アルバイトやパートも該当します。ただし、専従者(≒家族従業員)は「従業員」には該当しません。専従者との食事代などを「福利厚生費」として経費計上するのは避けましょう。
法定福利費と法定外福利費の違い
福利厚生費は「法定福利費」と「法定”外”福利費」に大別されます。違いをざっくり理解しておくと、福利厚生費の会計処理がわかりやすいです。
| 法定福利費 | 法定外福利費 | |
|---|---|---|
| 主な例 | ・従業員の雇用保険料 ・従業員の労災保険料 ・従業員の健康保険料 ・従業員の厚生年金保険料 |
・従業員の通勤手当 ・従業員との飲み会代 ・従業員の食事補助 ・従業員への慶弔見舞金 |
| 特徴 | 事業主の負担が 法律で定められている費用 |
従業員のために 事業主が任意で払う費用 |
| 勘定科目 | 福利厚生費 | 基本は福利厚生費だが 給与に該当する場合もある |
法定福利費については、迷わず「福利厚生費」として経費計上してOKです。一方、法定外福利費については、実質的に「従業員への給与」とみなされる場合もあるので注意しましょう。詳しくは以下で説明します。
福利厚生費と給与の判別方法【3つの条件】
従業員のために支払った費用は、福利厚生費ではなく「従業員への給与」とみなされる場合もあります。基本的に、給与とみなされるような支出は「給料賃金」として処理しなくてはなりません。
判断に迷ったら、下記の基準で考えてみてください。一般的に、下記の条件を3つとも満たす費用は「福利厚生費」に該当します。
- 現金や金券でないこと
- すべての従業員が平等に利用できること
- 社会通念上、妥当な金額であること
ここからは、それぞれの条件について詳しく解説していきます。
条件① 現金や金券でないこと
福利厚生のつもりでも、従業員に現金や金券(商品券など)を渡すと、それは「給与」とみなされる可能性が高いです。福利厚生の一環で従業員に何かをしてあげたいなら、食事などの現物支給が無難と考えましょう。
ただ、例外として「通勤手当」や「慶弔見舞金(結婚祝いなど)」については現金でも構いません。これらは、後述の②と③の条件を満たしていれば、福利厚生費として処理してOKです。
条件② すべての従業員が平等に利用できること
特定の従業員だけが対象の費用は、その従業員への「給与」とみなされる可能性があります。福利厚生費として処理したいなら、すべての従業員が平等に利用できるように、制度を整えておきましょう。
たとえば、従業員に支給する通勤手当や結婚祝いなどについては、「こういう場合に〇〇円を支給する」と規定を作っておくと安心です。お気に入りの従業員にだけ羽振りを良くすると、給与扱いになってしまうかもしれません。
条件③ 社会通念上、妥当な金額であること
通常なら福利厚生に該当するような費用でも、金額が多すぎると「給与」とみなされる可能性があります。具体的に「〇〇円以上は給与とみなす!」という基準はありませんが、福利厚生の一環で支給したいなら、常識の範囲内にとどめておきましょう。
たとえば、従業員3人との忘年会で300万円を使ったとします。これは、社会通念上「妥当な金額」とは言えなそうなので、参加した従業員に対する給与とみなされる可能性があります。
これは福利厚生費?それとも給与?
下記のような費用について、福利厚生費と給与の判定基準を解説します。
- 従業員の通勤手当
- 食事代の補助
- 忘年会や歓送迎会の飲食費用
- 健康診断費用
- 慶弔見舞金
このうち「通勤手当」と「食事代の補助」に関しては、明確な金額基準が設けられています。そのほかの費用については、前述した3つの条件に照らして考えるのが基本です。
① 従業員の通勤手当
従業員の通勤手当は、一定の金額までは「福利厚生費」として処理できます。アルバイトやパートに通勤手当を支給する場合も同じです。
たとえば、従業員が公共交通機関(電車やバスなど)で通勤している場合、その従業員への通勤手当は「月15万円」が上限です。月15万円を超えた分は、その従業員への給与とみなされます。
マイカー・自転車通勤者の通勤手当 – 国税庁
② 食事代の補助
従業員に食事代の補助を提供する場合、以下の条件を満たせば「福利厚生費」で処理できます。
- 従業員が食事代の半分以上を負担していること
- 事業主の負担が1ヶ月あたり「税抜3,500円以下」であること
たとえば、週2回勤務するアルバイト従業員に、事業主が購入した1,000円のお弁当を600円で支給する場合、月間の事業主負担は400円 × 8日 = 3,200円となります。この場合は、福利厚生費で処理できます。
ただし例外として、残業時などは、食事を現物支給(お弁当など)する場合に限り、全額を福利厚生費として処理できます。このときの金額は1,000~1,500円程度が一般的です。
③ 忘年会や歓送迎会の飲食費用
忘年会・新年会・歓送迎会などの飲食費用は、以下の条件を満たせば「福利厚生費」として処理できます。
- 全従業員に対しておおむね一律であること
- 社会通念上、事業主の負担金額が高額になりすぎないこと
ただし、従業員の表彰式やビンゴ大会などで従業員に「賞金」を渡す場合、その賞金は給与扱いになるので注意しましょう。ちなみに、ビール券などの「賞品」については、基本的に福利厚生費で処理できます。
④ 健康診断費用
健康診断や人間ドックの費用は、以下の要件を満たせば「福利厚生費」で処理できます。
- すべての従業員が対象であること(ただし年齢制限は可能)
- 受診費用を、事業主から医療機関に直接支払っていること
- 診断内容が常識の範囲内であること
たとえば、一般的な健康診断や人間ドックなら問題ありませんが、アレルギー検査などは「福利厚生費」と認められない場合が多いようです。
ちなみに、「これで払ってね」と従業員に現金を渡したり、従業員に立て替えてもらった金額をあとから渡したりすると、「給与」とみなされる可能性があります。
⑤ 慶弔見舞金
従業員に対する慶弔見舞金は、一定の基準(社則など)に従って支給していれば、基本的に「福利厚生費」として処理できます。
慶弔見舞金の例
- 結婚祝い
- 出産祝い
- 見舞金
- 香典など慶弔金
- お祝い品、花輪の費用
ただし、支給する金額は常識の範囲内におさめておきましょう。たとえば、結婚式のご祝儀に5万円を包むくらいなら問題ありません。
「接待交際費」や「会議費」との使い分け
福利厚生費と他の勘定科目の違いについて、使い分けに迷いやすいケースを例に挙げて解説します。
① 飲食費用は接待交際費?会議費?
飲食費用の勘定科目は、参加者や目的に応じて使い分けるのが一般的です。個人事業主の場合は、ざっくり下記のように使い分けておけばよいでしょう。
| 従業員との食事 | 取引先との食事 | |
|---|---|---|
| 懇親が目的 | 福利厚生費 | 接待交際費 |
| ミーティングが目的 | 会議費 |
※ あくまで目安なので、この通りでなくても問題ありません
法人(株式会社など)の会計では「接待交際費」などの使い方に色々とルールがありますが、個人事業主の場合はざっくりで大丈夫です。
接待交際費と福利厚生費の使い分けについて詳しく
② 結婚式のご祝儀は接待交際費?
結婚式のご祝儀は、送る相手によって会計処理が異なります。個人事業主の場合は、下記のように勘定科目を使い分けるのがよいでしょう。
| 従業員へのご祝儀 | 取引先へのご祝儀 |
|---|---|
| 福利厚生費 | 接待交際費 |
結婚式のご祝儀以外でも、いわゆる慶弔見舞金はすべて上記のような使い分けでOKです。なお、当然ですが、従業員も取引先も関係のない結婚式のご祝儀などは、そもそも必要経費に計上できません。
③ 従業員の電車賃は旅費交通費?
従業員に交通費を支給した際は、「旅費交通費」の勘定科目を使うこともあります。下記のように使い分けましょう。
| 通勤手当 | 業務中の交通費 |
|---|---|
| 福利厚生費 | 旅費交通費 |
たとえば、従業員が取引先へ出向くときの電車賃やタクシー代は「旅費交通費」で処理するのが妥当です。ちなみに、業務中に使った駐車場の代金や、出張の宿泊費なども「旅費交通費」で処理できます。
福利厚生費の仕訳方法
たとえば、従業員が全員参加する忘年会の費用として、現金で50,000円を支払ったとします。この場合、複式簿記では下記のように仕訳します。
複式簿記の記帳例
| 日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 20XX年12月20日 | 福利厚生費 50,000 | 現金 50,000 | 社内忘年会費用 |
なお、同じ支出を単式簿記で帳簿付けすると、記帳例は以下のようになります。
単式簿記の記帳例
| 日付 | 福利厚生費 | 摘要 |
|---|---|---|
| 20XX年12月20日 | 50,000 | 社内忘年会費用 |
福利厚生費の消費税区分
福利厚生費の消費税区分は、具体的な内容によって異なります。福利厚生費に含まれる代表的な費用の課税区分は以下の通りです。
| 課税 | 不課税 |
|---|---|
| ・従業員の通勤手当 ・従業員との飲食費用 ・従業員の健康診断費用 ・食事代の補助費用 |
・従業員の社会保険料 ・従業員への慶弔見舞金 |
なお、消費税の免税事業者なら、消費税区分はあまり気にしなくてOKです。ちなみに、ここで言う課税・不課税とは「消費税の課税区分」のことで、「給与として課税されるかどうか」とは全く別の話なので注意してください。
福利厚生費に関するQ&A
- 個人事業主にも福利厚生費ってあるの?
- 個人事業主も、従業員を雇っている場合には「福利厚生費」を使うことがあります。自分自身のための支出は福利厚生費に該当せず、あくまで従業員のための支出が対象です。
- 従業員との飲み会代は福利厚生費にできる?
- 従業員全員を対象とした飲み会代は「福利厚生費」として処理するのが一般的です。ただし、特定の従業員だけとの飲食は、接待交際費や給与扱いになる可能性があります。
- 福利厚生費と接待交際費の違いは?
- ざっくり言うと、福利厚生費は従業員のための支出、接待交際費は取引先のための支出です。ただ、判断に迷う場合は、個人事業主ならそれほど厳密に使い分けなくてもOKです。
福利厚生費と接待交際費の違い【個人事業主向け】
- 従業員が1人だけの場合でも福利厚生費は使える?
- 従業員が1人でも福利厚生費は計上可能です。ただし、事業主本人だけの支出は認められない点に注意が必要です。
- 福利厚生費はいくらまでなら大丈夫?
- 福利厚生費の金額に明確な上限はありませんが、社会通念上妥当な範囲である必要があります。常識を超えた高額支出は、必要経費として認められないおそれがあります。
まとめ
福利厚生費とは、従業員の生活向上や労働環境改善のために支出する費用のことです。基本的に、事業に必要な範囲であれば全額を必要経費に計上できます.
福利厚生費の重要ポイント
- 従業員のために支出した費用が該当する
- 専従者(≒家族従業員)のための費用は該当しない
- 福利厚生費は「法定福利費」と「法定外福利費」に分けられる
- 法定福利費とは、従業員の社会保険料などのこと
- 法定外福利費には、従業員の通勤手当や懇親会費などが含まれる
- 法定外福利費は、給与とみなされる場合もあるので要注意
従業員に高額な食事をおごったり、高額な結婚祝いを送ったりすると、その金額は「その従業員への給与」とみなされる場合があります。下記のような支出は「給与」とみなされる可能性が高いので注意しましょう。
こんな場合は「給与」かも!
- 従業員に現金や金券を渡した場合
- 一部の従業員のためだけに費用を払った場合
- 社会通念上、妥当な金額を超えている場合
給与に該当するような支出は「給料賃金」の勘定科目で処理するのが妥当です。なお、通常の給与と同じように、受け取った従業員のほうに所得税がかかることになります。