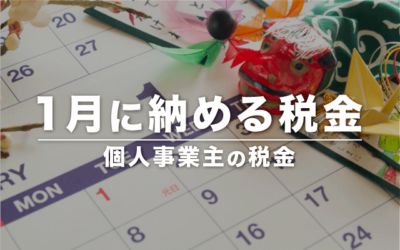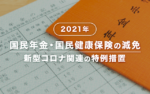通常、個人事業主は労災保険に加入できません。ただ、一定の要件を満たせば「労災保険の特別加入」ができます。
目次
労災保険の特別加入制度とは
個人事業主でも、労働者と同様の保護を受けるべきとみなされる場合は、任意で労災保険に加入できます。これを「労災保険の特別加入制度」といいます。
特別加入制度の対象
| 対象 | 概要 |
|---|---|
| 中小事業主 | 一定数以下の労働者を雇用している事業主 |
| 一人親方等 | 特定の業種(建設業や運輸業など)を営む事業主 |
| 特定作業従事者 | 特定の種類に該当する作業を行う事業主 |
| 海外派遣者 | 国内から海外の事業に派遣される事業主 |
個人事業主で当てはまるケースが多いのは「中小事業主」と「一人親方等」です。本記事では、この2つに当てはまる事業者や、加入の要件について解説します。
-
2021年9月から、特別加入の対象範囲が拡大されます。これにより、たとえばフードデリバリーの自転車配達員は「一人親方等」に、フリーのITエンジニアは「特定作業従事者」に該当することになります。
>> 特別加入の対象拡大について詳しく【2021年9月から】
事業専従者も特別加入OK
中小事業主と一人親方等の場合に限り、事業主が特別加入の要件を満たしていれば事業専従者も共に特別加入できます。労災保険において、事業者と事業専従者は同等の扱いをする、ということです。
中小事業主の場合 – 対象や加入の要件
労働者を雇用する立場である事業主でも、「中小事業主」の要件に該当すれば労災保険に特別加入できます。中小事業主と認められるかどうかは、雇用している労働者の人数によって異なります。
中小事業主と認められる企業の規模
| 業種 | 常時使用している労働者数 |
|---|---|
| 金融業・保険業・不動産業・小売業 | 50人以下 |
| 卸売業・サービス業 | 100人以下 |
| 上記以外の業種 | 300人以下 |
「常時使用」とは1年のうち100日以上使用していること
上記にあてはまるなら、個人事業主であっても「中小事業主」に該当します。一人も労働者を雇っていない場合は、中小事業主とは認められません。中小事業主の場合、下記の要件を2つとも満たすことで、労災保険に加入できます。
- 雇用している労働者を労働保険に加入させている
- 労働保険の事務処理を「労働保険事務組合」に委託している
① 雇用している労働者を労働保険に加入させている
従業員を一人でも雇用すれば、事業者はその従業員を労働保険(労災保険+雇用保険)に加入させる義務があります。つまり、この要件はクリアしているのがあたりまえということです。
② 労働保険の事務処理を「労働保険事務組合」に委託している
「労働保険事務組合」とは、労働保険の事務処理について厚生労働大臣の認可を受けている団体のことです。本来、事業主が行うべき労働保険の加入申請や届出といった事務的な業務を代行してくれます。
この労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託することで、中小事業主は労働保険に特別加入できます。ただ加入可能な業種や地域は、たいてい限定されています。また、入会金や委託手数料が発生する場合がほとんどなので、確認してから申し込みましょう。

一人親方等の場合 – 対象や加入の要件
労働者を雇わず一人で事業を営んでいる場合、以下のいずれかにあてはまる業種を営んでいれば「一人親方等」として認められます。「一人親方」と聞くと、建設業関係の事業者だけのような印象がありますが、実際にはそのほかの業種も対象です。
一人親方等と認められる主な業種
- 自動車で旅客や貨物を運送する事業 (個人タクシーなど)
- 土木工事や建築物の建設、修理、解体などの事業 (大工やとび職など)
- 漁業や林業などの事業
ちなみに、勤務日数が年間で合計100日未満の従業員を雇っている場合は「一人親方等」として認められます。100日以上働いている従業員を雇用していたら「一人親方等」にはあてはまりません(中小事業主に該当)。
加入要件「特別加入団体に加入する」
一人親方等が労災保険に加入するには、「特別加入団体」に加入する必要があります。一人親方等を労働者、特別加入団体を事業主とみなして労災保険を適用するからです。

労災保険の特別加入団体には、古くからある●●土建組合といった名称の団体や、社労士を介して加入する事務組合など、さまざまなタイプがあります。近年では、インターネットから加入できる団体も登場しました。
加入できる団体は、地域ごとに定められています。入会金や会費も団体ごとに異なるので、選ぶ際の大きなポイントになります。加入の際は、所轄の都道府県労働局または労働基準監督署に問い合わせましょう。
特別加入の補償範囲
労災保険の給付は、業務災害(業務中に発生した怪我など)と通勤災害(通勤中に発生した怪我など)に対して行われます。特別加入制度を利用して労災保険に加入すると、補償の範囲が通常の場合と異なるケースがあります。
中小事業主の場合
基本的には労働者と同じ範囲を補償されます。ただ、事業主の立場で事業を行っているときに負った怪我などに関しては、労災保険の給付は行われません。あくまでも、「労働者」とみなされるときだけ補償されるということです。
一人親方等の場合
一人親方の場合、どの事業を営んでいるかによって保障内容が変わってきます。たとえば、一人親方等に該当する個人タクシー業者の場合、通勤災害は保護の対象外です(どこまでが通勤の範囲なのか見極めが難しいため)。
保険料の計算方法
特別加入制度を利用して労災保険に加入した場合、その年の保険料は「保険料算定基礎額」に「保険料率」をかけて求めます。

「給付基礎日額」は、保険料や給付額を算出する際に決め手となる数字です。基本的には、事業主が自由に選ぶことができます。特別加入申請書の「希望する給付基礎日額」の欄に、任意の額を記入すればOKです。
「保険料率」は事業ごとに定められているので、勝手に変更はできません。たとえば、小売・卸売業は0.3%、個人タクシー業は1.2%、建設業は1.8%といったように定められています。
>> 労災保険料率 – 厚生労働省
保険料の計算例
給付基礎日額ごとに保険料がどう変わるのか、表にまとめました。保険料率は1.2%として計算しています。このように、給付基礎日額が高いほど保険料も高額になります。そのかわり、もしものときに受け取れる給付金も高額になるので、慎重に選択しましょう。
給付基礎日額と保険料の具体例
| 給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 (給付基礎日額 × 365日) |
年間の保険料 (保険料率は1.2%) |
|---|---|---|
| 25,000円 | 9,125,000円 | 109,500円 |
| 20,000円 | 7,300,000円 | 87,600円 |
| 10,000円 | 3,650,000円 | 43,800円 |
| 5,000円 | 1,825,000円 | 21,900円 |
| 3,000円 | 1,277,500円 | 15,324円 |
保険料は「所得控除」の対象 – 必要経費ではない
労災保険に特別加入した場合、支払った費用は必要経費として計上することはできません。ただ、所得控除の「社会保険料控除」に該当します。確定申告の際、控除の申請を忘れないようにしましょう。
ちなみに労働者分の保険料は、事業主が負担した分を必要経費に計上できます。勘定科目は、「福利厚生費」「法定福利費」などを用います。

まとめ – 労災保険に特別加入する際のポイント
業務中や通勤中に被った怪我・病気・死亡などを補償してくれるのが、「労災保険」です。一般的には労働者を保護するための制度ですが、「特別加入」の要件を満たせば個人事業主でも加入できます。
労災保険に特別加入する際のポイント
- 通常では加入対象外の個人事業主でも、要件にあてはまれば労災保険に加入できる
- 事業主が特別加入できれば、事業専従者も労災保険に特別加入OK
- 特別加入の場合でも、基本的に補償内容や範囲は変わらない
- 業種によっては、補償される範囲が異なる
- 支払う保険料が高くなるほど、給付金額も高くなる
- 特別加入した際の労災保険料は「社会保険料控除」の対象
労災保険に特別加入するには、特定の要件を満たしている必要があります。個人事業主の場合、「中小事業主」か「一人親方等」に該当する事業者が多いです。
「中小事業主」として特別加入するには
- 常時使用している(年間100日以上)労働者の人数が規定以下
- 雇っている労働者を労働保険に加入させている
- 「労働保険事務組合」に、労働保険にまつわる事務処理を委託している
「中小事業主」として認められるには、1年のうち合計100日以上勤務している従業員を規定内の人数だけ雇っている必要があります。「一人親方等」でも、1年のうち100日未満だけの勤務なら従業員を雇っていてもOKです。
「一人親方等」として特別加入するには
- 要件に該当する事業を営んでいる(運輸業や建設業、林業、漁業など)
- 「特別加入団体」に加入する
中小事業主なら「労働保険事務組合」に、一人親方等なら「特別加入団体」に申し込む必要があります。団体によって入会金や会費、所轄の地域などが異なるので、よく確認してから手続きを行いましょう。