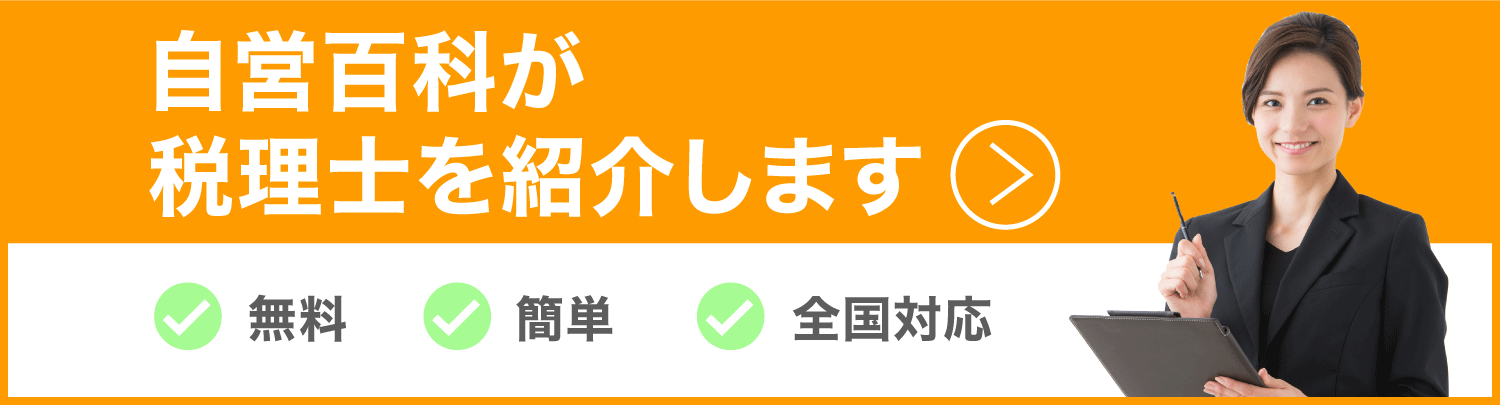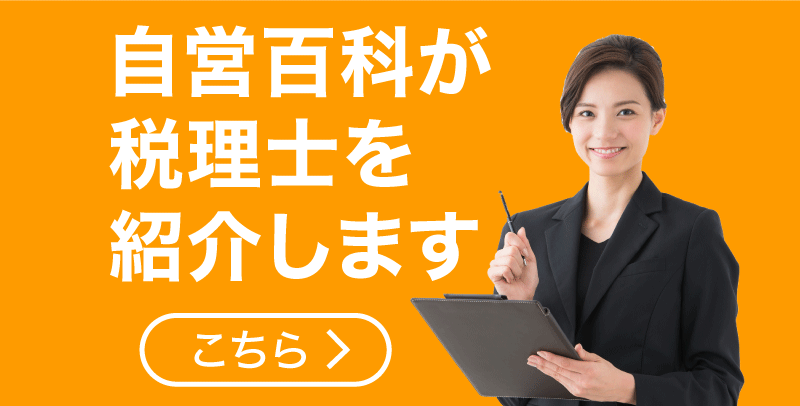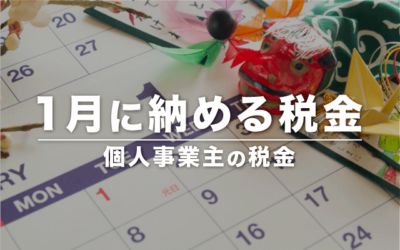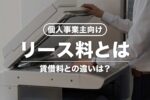個人事業主・フリーランス向けに「少額減価償却資産の特例」をわかりやすく解説します。メリット・仕訳方法・特例の期限などをまとめました。
目次
少額減価償却資産の特例とは?
| 対象者 | 青色申告者(従業員数が1,000人以下の場合に限る) |
|---|---|
| 対象となる資産 | 取得価額が10万円以上30万円未満の資産 |
| 適用できる限度額 | 年間で合計300万円まで(新規開業した年の限度額は月割) |
少額減価償却資産の特例では、取得価額が30万円未満の資産を取得したときに、全額をその年の経費にできます。簡単に言うと、青色申告なら30万円未満なら面倒な減価償却が不要になる!という特例です。
「取得価額」とは、資産の取得にかかった費用の合計金額のことです。本体価格のほか、送料や手数料なども含まれます。消費税の納付義務がない事業主(=免税事業者)であれば、税込価格で考えてOKです。
税込経理方式と税抜経理方式について詳しく
少額減価償却資産の特例はいつまで使える?
少額減価償却資産の特例は、令和6年度の税制改正によって適用期限が2026年(令和8年)3月31日まで延長されました。これまでも2年おきに延長を繰り返してきたので、2026年以降も延長される可能性があります。
少額減価償却資産の特例のメリット
- その年分の所得税を減らせる
- 会計処理をラクにできる
① その年分の所得税を減らせる
少額減価償却資産の特例を適用すると、取得価額のすべてをその年の経費にできます。したがって、利益が多くでた年に取得した資産を少額減価償却資産とすれば、高い節税効果が見込めます。
② 会計処理をラクにできる
少額減価償却資産の特例では、取得価額を一括で計上すればよいので、会計処理もカンタンです。通常の減価償却では面倒な会計処理が数年に渡って続きますが、少額減価償却資産の特例を適用すれば、その年で処理が完了します。
少額減価償却資産の仕訳方法
たとえば、22万円の業務用冷蔵庫を現金で購入し、これを少額減価償却資産の特例を適用して減価償却をした場合、下記のように仕訳します。まずは、購入日で次のように仕訳を行います。
① まずは購入日で仕訳する
| 日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 20XX年5月23日 | 工具器具備品 220,000 |
現金 220,000 |
冷蔵庫 |
「工具器具備品」は、事業で利用する工具や器具備品を処理するための勘定科目です。 本例の冷蔵庫以外にも、デスクやパソコンといったオフィス機器などが該当します。
そして、決算日で次のように仕訳をします。個人事業の決算日は原則12月31日なので、この日付で記帳を行いましょう。
② 次に決算日で仕訳する
| 日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 20XX年12月31日 | 減価償却費 220,000 | 工具器具備品 220,000 | 冷蔵庫 少額減価償却資産の 特例により減価償却 |
固定資産台帳への記録も忘れずに
固定資産台帳とは、取得価額が10万円以上の資産を持っている際に作成する帳簿です。クラウド会計ソフトなどで作成すれば、画面に従って必要事項を入力していくだけなのでカンタンです。以下は、freee(フリー)で作成した固定資産台帳です。
| 登録画面 | 固定資産台帳 一覧画面 |
|---|---|
 |
 |
青色申告決算書の書き方(減価償却費の計算欄)
確定申告の際には、青色申告決算書の3ページ目にある「減価償却の計算」へ必要事項を記入しましょう。少額減価償却資産の特例を適用する資産が複数ある場合は、次のようにまとめて記載しても構いません。
【記入例】青色申告決算書「減価償却費の計算」

本来、少額減価償却資産の特例を受けるためには、確定申告の際に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を提出しなければなりません。しかし、以下の要件をすべて満たした上で、明細を別途保管している場合は提出を省略できます。
「取得価額に関する明細書」の提出を省略する条件
- 少額減価償却資産の特例を適用した資産の取得価額の合計金額を記入
- 摘要欄に「措法28の2」と記入
- 摘要欄に明細書を別途保管している旨を記入
個人事業主であれば、明細書の形式に規定はありません。資産名、取得年月、それぞれの取得価額や合計金額などが記入してあればOKです。
少額減価償却資産に関する疑問【Q&A】
- 少額減価償却資産の特例はいつまで使える?
- 少額減価償却資産の特例は、今のところ2026年3月31日までに取得した資産が対象です。ただ、この特例は2年おきに延長を繰り返してきたので、2026年以降も延長される可能性があります。
- 少額減価償却資産の特例の上限額は年間いくらまで?
- 少額減価償却資産として計上できるのは年間300万円までです。複数の資産を購入した場合は、合計金額が300万円を超えない範囲で適用できます。
- 白色申告でも少額減価償却資産の特例を使える?
- 少額減価償却資産の特例を利用できるのは青色申告者だけです。白色申告の場合は利用できません。
- 少額減価償却資産と「一括償却資産」の違いは?
- 一括償却資産は、取得価額が20万円未満の資産を3年で均等償却できる制度です。一方、少額減価償却資産の特例では30万円未満の資産をその年に全額経費化できます。
- 少額減価償却資産の特例には「明細書」の提出が必要?
- 個人事業主なら「取得価額に関する明細書」の提出は省略できます。ひとまず、青色申告決算書に「少額減価償却資産の合計額」や、明細書を別途保管している旨を記載しておけばOKです。
まとめ
「少額減価償却資産の特例」に関するポイントをまとめておきます。
少額減価償却資産の特例のポイント
- 対象者は青色申告者のみ
- 取得価額10万円~30万円のものが対象
- 取得価額の全額をその年の経費にできる
- 合計の限度額は年間300万円(開業年などは月割)
- 青色申告決算書の3ページ目にある「減価償却の計算」へ記入する
減価償却には3つの方法がある
減価償却には大きく3つの方法があり、取得価額によって選択できる方法が異なります。要件さえ満たしていれば、どの方法を選択しても構いません。
| 通常の減価償却 | 一括償却資産 | 少額減価償却資産 の特例 |
|
|---|---|---|---|
| 概要 | 定額法 or 定率法で 償却する |
3年にわたって 1/3ずつを経費にする |
取得した年に 全額経費にする |
| 対象者 | すべての事業者 | すべての事業者 | 青色申告者 |
| 取得価額 | 10万円以上 | 10万円以上 20万円未満 |
10万円以上 30万円未満 |
| 限度額 | なし | なし | 合計300万円(年間) |
| 固定資産税 | 対象 | 対象外 | 対象 |
利益が多くでた年の所得税を減らしたい人や、会計処理をラクにしたい人には「少額減価償却資産の特例」の適用がおすすめです。