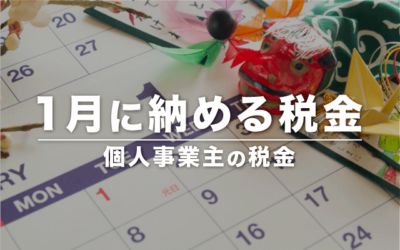iDeCoとNISAは、個人事業主が老後の資金準備をする際に役立つ制度です。それぞれのメリット・デメリットを比較しながら、賢い選び方などをわかりやすく解説します。投資未経験の初心者にも参考にしていただけます。
目次
iDeCoとNISAの特徴を比較
iDeCoとNISAは、どちらも非課税で資産運用ができる制度です。どちらの制度も一長一短あるので、両方バランスよく利用するのが理想です。もし資金にあまり余裕がなければ、ひとまずNISAから着手するのをおすすめします。

「iDeCo(イデコ)」は節税効果が高く、掛け金を払うときと、給付を受けるときの両方で税制優遇が受けられます。ただし、老後の資産形成に特化した制度なので、60歳になるまで資産を引き出せません。資金に余裕がある人に向いています。
「NISA(ニーサ)」では、非課税で運用した資産を、好きなときに引き出して現金化できます。老後のためだけでなく、子どもの教育費やマイホームの購入費などに充ててもOKです。幅広い用途で資産を形成したい人に向いています。
iDeCo(イデコ)とは? 個人事業主向けの解説
「iDeCo」とは、個人が任意で加入する私的年金制度を指します。ざっくりいうと、60歳以降にもらえる年金アップが狙える制度です。公的年金(国民年金)だけでは老後が心配な人は、利用を検討してみましょう。

iDeCoを利用する際は、積み立てる金額や運用商品を自分で決めなくてはいけません。元本割れのリスクを取ってでも利幅を重視するか、ローリスクで堅実に運用するか、あらかじめ方針を決めておきましょう。
主な運用商品の種類 ‐ iDeCoで選べるもの
| 定期預金 | 確実に元本を確保できるが、運用益は少ない。 |
|---|---|
| 保険商品 | 満期保有すれば元本割れしない。ローリスク。 |
| 投資信託 | 元本割れのリスクがある。比較的ハイリターン。 |
たとえば、ローリスクで安全に運用したいなら、投資信託の割合を少なく設定すればOKです。下図の例は、投資信託の割合を20%に抑えた、比較的ローリスクな配分だと言えます。

iDeCoで将来もらえる金額・受け取り方
将来の給付額は「積み立てた掛金の合計額+運用損益」となるため、運用成績によって増減します。定期預金や保険商品のみを選べば元本割れの心配はほぼありませんが、投資信託などは元本割れのリスクもあります。

掛金は65歳になるまで拠出でき、60歳以降に老齢給付金の受け取りが可能です。受け取る際は、一括と分割のどちらかを選択する必要があります。
NISA(ニーサ)とは? 個人事業主向けの解説
「NISA」とは、投資で得られた収益が非課税になる、国の税制優遇制度です(正式名称:少額投資非課税制度)。NISAで積み立てた資産は、いつでも現金化できます。そのため、老後の備えに限らず、子どもの学費やマイホームの購入など、さまざまなライフイベントの備えとしても活用できます。

NISAを始めるには、まず銀行や証券会社でNISA専用の口座を開設します。このNISA口座を介して取引(投資信託の購入や売却)を行うことで、運用益が非課税で受け取れる仕組みです。
今回説明する「つみたて投資枠」では、毎月一定の金額を決めて、投資信託などの金融商品を購入していきます。定期預金のような元本確保型の商品は購入できません(詳細は後述)。

NISAで積立投資する際の考え方
つみたて投資では、まとまったお金を一度に投資するのではなく、定期的に同じ金額を投資します。これを長期間にわたって続けることで、株価暴落などによるリスクを軽減できると言われています(ドルコスト平均法)。
つみたて投資枠では、毎年120万円まで投資できます。生涯では1,800万円まで非課税です(ただし、成長投資枠と合算)。ちなみに、以前は非課税期間が20年に制限されていましたが、2024年から法改正により無期限になりました。
iDeCoとNISAの相違点
ここからは、iDeCoとNISAを比較します。両制度の主な相違点は以下の6つです。重要度の高いものから順に解説していきます。
① 資産の引き出し時期
② 税制優遇の仕組み
③ 運用商品のラインナップ
④ 手数料の有無
⑤ 掛金の下限・上限
⑥ 取引を行う口座
【相違点①】資産の引き出し時期
iDeCoは原則60歳になるまで資産を引き出せません。一方、NISAは好きな時に資産を引き出せます。
| iDeCo | NISA |
|---|---|
|
原則*60才まで引き出せない |
いつでも引き出せる |
* 途中で死亡や一定の障害状態になった場合は、60歳未満でもiDeCoの給付金を受け取れる
iDeCoは原則60才まで引き出せないので、急な出費などには対応できません。ただ、手元にお金があるとすぐ浪費してしまいそうな方は、これをメリットと捉えることもできます。
NISAのほうが、基本的には使い勝手がよいです。突然のアクシデントなどで予定外に出費がかさみ、通常の生活資金では賄えないときは、NISAを取り崩して対応することもできます。
【相違点②】税制優遇の仕組み
iDeCoでは、拠出する掛金がすべて所得控除の対象になります。これに対して、NISAへの投資額は所得控除の対象になりません。そのため、投資を行う時点では、基本的にiDeCoのほうが有利です。
| iDeCo | NISA | |
|---|---|---|
| 掛金/投資額 | 所得控除あり | 控除なし |
| 運用益 | 非課税 | 非課税 |
| 受取額 | 退職所得控除など | 非課税 |
所得控除(こうじょ)とは、税金の負担を公平にするために、生活状況などに応じて税負担を軽減する仕組みです。以下の図のように、所得控除の金額が多いほど、所得税額も少なくなります。

たとえば、投資前の課税所得が100万円だとします。もしiDeCoに40万円掛けると、課税所得は「100万円 − 40万円 = 60万円」となり、税負担が大幅に軽減されます。一方、NISAに40万円を投資しても、課税所得は「100万円」のままで税負担も変わりません。
資産の受取時は、厳密にいうとNISAのほうが有利です。NISAは非課税ですが、iDeCoは課税対象になります。とはいえ、iDeCoを受け取る際は、退職所得控除などの優遇制度があるため、結果的にまったく税金がかからない場合もあります。
【相違点③】運用商品の種類・ラインナップ
iDeCoとNISAでは選択できる運用商品が異なります。iDeCoでは元本確保型の商品(定期預金や保険商品)も選べますが、NISAには元本確保型の商品がありません。
| iDeCo | NISA(つみたて投資枠) | |
|---|---|---|
| 商品の種類 | 定期預金 保険商品 投資信託 |
投資信託のみ |
| 投資信託の
ラインナップ |
比較的少ない | 比較的多い |
iDeCoには、元本確保型商品である定期預金と保険商品があります。元本確保型商品を選ぶことで元本割れするリスクを抑えられます。より大きなリターンを求める場合は投資信託を選択するなど、運用方針に沿った選択が可能です。
NISAの対象商品は、長期の積立分散投資に適した投資信託です。金融庁が定めた要件を満たしたものに限られますが、投資信託の商品ラインナップはiDeCoより豊富です。
投資信託とは、投資家から集めたお金をひとつの資金としてまとめ、運用の専門家が株式や債券などに投資して運用する商品のこと。運用の成果は、投資家それぞれの投資額に応じて分配される。
【相違点④】手数料の有無
iDeCoを利用するには、以下のような手数料を支払う必要があります。NISAであれば基本的に手数料はかかりません。ただし、投資信託の信託報酬に関しては、iDeCoとNISAのどちらも発生します。
| iDeCo | NISA(つみたて投資枠) | ||
|---|---|---|---|
| 新規開設/移設時 | 約3,000円/初回 | 手数料なし | |
| 運用中 | 口座管理 | 約170円*/月 | 手数料なし |
| 信託報酬 | 目安:資産額の0.1〜1.5%*(年率) | ||
| 受け取り時 | 約440円/回 | 手数料なし | |
* 金融機関や商品、利用状況によって手数料が異なる場合もあります
信託報酬は、次のように計算します。たとえば、投資信託で100万円分の資産を持っているとき、年率0.5%の信託報酬は「100万円 × 0.5% = 5,000円」となります。1年分を一気にまとめて支払うわけではなく、日割り計算した金額を毎日支払う形です。
ちなみに、信託報酬はiDeCoのほうが高くなりやすい傾向があるようです。NISA(つみたて投資枠)に関しては、信託報酬の上限規制があり、最大1.5%の上限が定められています。
【相違点⑤】掛金の上限・下限
iDeCoとNISAは、掛金に上限や下限があります。iDeCoは最低でも毎月5,000円は用意しなくてはいけませんが、NISAは毎月100円の積み立てからでも始められます。
| iDeCo | NISA(つみたて投資枠) | |
|---|---|---|
| 上限額 | 月6万8,000円 (年81万6,000円) |
月平均10万円
(年120万円) |
| 下限額 | 月5,000円〜 | 月100円〜* |
| 生涯投資枠 | ‐ | 1,800万円 |
* 金融機関や商品、利用状況によって手数料が異なる場合もあります
iDeCoは、年間6万円〜約80万円の拠出ができます。iDeCoで拠出した金額は、全額が所得控除の対象になるので、その年の節税にも役立ちます。
NISAのつみたて投資枠では、年間で120万円まで積み立てが可能です。NISAの下限は金融機関によって異なりますが、楽天証券などでは月100円から積み立てできます。
【相違点⑥】取引を行う口座
iDeCoとNISAは、それぞれ専用の口座を使って取引をします。iDeCoとNISAを併用する場合は、両方の口座を作らなくてはいけません。なお、開設できる口座数は、どちらも一人につき1つずつと決まっています。
| iDeCo | NISA | |
|---|---|---|
| 口座の呼び方 | iDeCo口座 | NISA口座 |
| 開設できる年齢 | 原則20才〜60才 | 18才〜 |
| 開設手数料 | 約3,000円/初回 | なし |
| 開設にかかる日数 | 約1〜2ヶ月 | 約2〜3週間 |
※「〜」は、「以上〜未満」
iDeCo口座は、満20歳になったその日から申し込みできます。一方、NISA口座は満18歳の誕生日を迎えて、さらに次の1月1日を迎えたときから申し込み可能です。
iDeCoとNISAの共通点
次に、iDeCoとNISAの主な共通点として、以下の4つを紹介します。
① 運用益が非課税である
② 安全性が比較的高い
③ 少額から始められる
④ 長期加入が前提の制度である
【共通点①】運用益が非課税である
iDeCoとNISAのどちらも、運用で得た利益(運用益)は非課税です。そのため、金融機関にお金を預けて運用してもらっているうちは、配当金や売却による利益が出ても税金はかかりません。

通常、iDeCoやNISAなしで株取引などをすると、運用益(配当所得・譲渡所得)には「20.315%」の税金が課されます。たとえば、10万円の運用益に課税された場合、約2万円が税金として引かれるため、受け取れる利益は約8万円です。
【共通点②】安全性が比較的高い
iDeCoやNISAで買える商品は、安定的な運用に向いていると国が認めた銘柄に限られています。いずれも厚生労働省や金融庁が定める要件をクリアした銘柄ばかりなので、初心者でも比較的安全に資産運用ができる仕組みです。
ただし、先述の通り、iDeCoやNISAは元本割れのリスクがゼロでない場合もあります。この点は十分理解した上で利用しましょう。
【共通点③】少額から始められる
iDeCoもNISAも少額から始められるため、自分の状況に合わせた無理のない範囲で資産形成が可能です。
iDeCoの掛金は月5,000円から設定できます。NISAは、金融機関によって異なりますが、月100円から数千円で始められます。積立投資は始めやすく、リスクも抑えて失敗しにくいため、投資初心者にもおすすめです。
どちらも高額を投資しないといけないわけではないため、できる範囲から始められます。
【共通点④】長期加入が前提の制度である
iDeCoもNISAも長期間加入を前提とした制度です。どちらも短期間に大きな利益を得ることが目的ではありません。運用に回したお金はしばらく手元に戻ってこないものと考え、余裕のある資金で運用しましょう。
iDeCoとNISAどちらを始めればよい?
iDeCoかNISAかを選ぶときは、以下の通り「何のために資金を準備するのか」という目的に応じて考えましょう。もちろん、元手に十分な余裕のある方は、iDeCoとNISAの併用も選択肢に入ります。
- iDeCoは「老後の資金準備」に特化している
- NISAは「多目的な資金準備」に向いている
老後の資金準備がメインならiDeCo
資産形成の目的が「老後の資金準備」であれば、iDeCoがおすすめです。iDeCoをうまく利用すれば、老後の資金を準備しながら、高い節税効果も期待できます。以下の3つすべてに当てはまる人は、まずiDeCoを検討しましょう。
- 老後の資金準備のみを目的としている
- 即効性のある税金対策をしたい
- とにかく元本割れを避けたい
iDeCoは原則60歳まで資産を引き出せませんが、言い換えると60歳まで絶対に使わず貯めておける、ということです。そのため、老後の不安が大きい人や、手元にお金があるとすぐ使ってしまう人にも向いています。
掛金の全額が所得控除の対象になり、すぐに節税効果が見込める点も、iDeCoの大きな魅力です。とくに個人事業主の場合は、法人に比べて節税手段が少ないので、十分な元手が用意できる人はうまく活用しましょう。
また、元本割れリスクを抑えたい人は元本確保型商品を選択することで、リスクを低減できます。iDeCoなら元本確保型の商品を選べますが、NISAでは選べません。
資金の利用目的に柔軟性を持たせたいならNISA
老後に限らず、さまざまなライフイベントに備えて「多目的な資金準備」をしたければ、NISAがおすすめです。以下の3つすべてに当てはまる人は、まずNISAから検討しましょう。
- ライフプランの幅広い用途で資産形成したい
- 幅広いラインナップから投資信託をしたい
- 受け取る際に税金がかかるのは絶対に避けたい
iDeCoとの大きな違いは、NISAは好きなときに資産を引き出せる点です。そのため、事業がうまくいかなくなった場合など、急に資金が必要になったときやライフスタイルの変化などに柔軟な対応ができます。
NISAの投資信託は、iDeCoより投資先が豊富なので、自己責任でリターンを追求することも可能です。といっても、国が選んだ安全性の高い銘柄しか買えない仕組みなので、一定の限界はあります。
NISA口座から引き出したお金は、非課税所得として扱われます。節税効果も十分ありますし、確定申告の手間が省けるのも地味に嬉しいポイントです。
余裕があれば併用も考えよう
iDeCoとNISAは併用できます。元手資金に余裕があれば、両方の特徴を生かして始めるのもよいでしょう。いきなり両方とも始めるのはちょっと怖いという人は、以下のどちらかの手順で様子を見てもOKです。
- 柔軟性が高いNISAで投資に慣れてからiDeCoに加入する
- 税金対策ができるiDeCoで老後の資金をしっかり確保してから、余裕のある資金でNISAを始める
自分の資金状況や運用目的に応じて、最適な運用方法を検討するのが大切です。
まとめ
老後資金のために資産運用をしたい個人事業主向けに、iDeCoとNISAの主な違いを、わかりやすい比較表にまとめました。個人事業主には退職金がなく、国民年金だけでは心もとないため、これらの非課税制度を上手に活用しましょう。
| iDeCo(個人事業主) | NISA(つみたて投資枠) | |
|---|---|---|
| 口座開設年齢 | 原則20才〜60才 申し込み時点 |
18才〜 その年の1月1日時点 |
| 受け取り時期 | 原則60才〜 | いつでもよい |
| 年間の積立上限額 | 81万6,000円 | 120万円 |
| 対象商品の種類 | 定期預金 保険 投資信託 |
投資信託のみ |
| 所得控除 | あり | なし |
| 運用益への課税 | 非課税 | 非課税 |
| 受取額への課税 | 課税対象になる | 非課税 |
※「〜」は、「以上〜未満」
iDeCoの受け取り額は課税対象になりますが、退職所得控除などの税制優遇が受けられるため、実質的には税金が発生しないケースも多いです。一方、NISAの受け取り額は、そもそも課税対象になりません。
iDeCoとNISAのメリット・デメリット
上記の違いを踏まえ、iDeCoとNISAを比較した場合のメリットとデメリットも表にまとめておきます。この表を参考に、自分にはどちらが合うのか検討してみてください。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| iDeCo | ・所得控除で節税できる ・元本確保がしやすい ・強制的な積み立てが可能 |
・60歳まで現金化できない ・選べる銘柄が少ない ・確定申告の手間が増える |
| NISA | ・好きなときに現金化できる ・投資で選べる銘柄が豊富 ・確定申告が不要 |
・所得控除がない ・元本割れリスクがある ・積み立ての強制力が弱い |
手元の資金に余裕があれば、iDeCoとNISAを併用しても構いません。ちなみに、両方とも上限額いっぱいまで積み立てる場合は、合計で年間200万円ほど必要です。
「200万円はちょっと用意できないけど、iDeCoとNISAの併用はしたい」という人は、上記のメリット・デメリットを参考に、投資額のバランスを決めましょう。