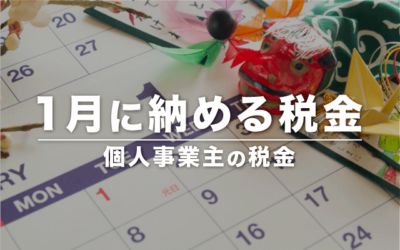住民税の「非課税限度額」についてまとめました。まず、おおまかに言うと「前年の所得が45万円以下の個人事業主」や「前年の年収が100万円以下の会社員・アルバイト」は、住民税が課されない可能性が高いです。
目次
「住民税非課税」とは?
住民税の内訳には「所得割」と「均等割」があり、それらの合計を納めます。一般的に「住民税非課税」と言うときは、所得割・均等割の両方が課されない状態を指します。
住民税の内訳
| 所得割 | 均等割 | |
|---|---|---|
| 概要 | 所得に応じて納める金額 | 地域ごとに一律の金額 |
| 目安 | 所得の10% | 年間4,000〜5,000円 |
所得割の税率と均等割の金額は、地域によって多少異なる
このうち、所得割だけが非課税になるケースもあります。しかし、低所得者への支援制度などは「両方が非課税の人」を対象としている場合が多いので注意しましょう。本記事では「両方が非課税の人」から順番に説明していきます。
- 前提として、住民税の税額は自治体が算出してくれるので、非課税かどうかを自分で計算する必要はありません。それでも「あらかじめ確認しておきたい!」という人は、本記事の説明を参考にしてください。
所得割・均等割の両方が非課税になるケース
以下のいずれかに該当する人は、所得割と均等割のどちらも課されません。
住民税(所得割・均等割)が非課税の人
- 生活保護の対象者のうち「生活扶助」を受けている人
- 合計所得金額が135万円以下の未成年者、障害者、寡婦、ひとり親
- 合計所得金額が市区町村の定める「非課税限度額」以下の人
退職金を受け取った場合などは、一部が課されることもある
「合計所得金額」は、ひとまず所得(収入 − 必要経費)のことだと考えてOKです。会社員やアルバイトの場合は、年間の額面給与から「給与所得控除」を引いた金額を所得と考えます。
「合計所得金額」の考え方について詳しく
① 生活扶助を受けている人
生活保護の対象者のうち「生活扶助(せいかつふじょ)」のお金を受け取っている人は、住民税(所得割・均等割)が非課税になります。「生活扶助」とは、食費や光熱費の補助にあたる給付のことです。
家賃をまかなう「住宅扶助」や、医療費を軽減する「医療扶助」しか受けていない人は該当しません。生活扶助を受けるのは、生活保護の対象者の中でも収入が低い人だと言えます。
- 詳しい解説
- 地方税法24条5で、「生活保護法の規定による生活扶助を受けている者」には道府県民税の所得割・均等割を課さないと定められている。また295条では、同様の者に市町村民税の所得割・均等割を課さないと定められている。よって、生活扶助の対象者には所得割も均等割も課されない。
※ 東京都の都民税・特別区民税についても同じ規定が適用される
② 所得が135万円以下の未成年者・障害者など
以下のどれかに該当する人は、前年の「合計所得金額」が135万円以下なら、住民税(所得割・均等割)が非課税になります。
- 未成年者
- 障害者
- 寡婦
- ひとり親
「合計所得金額が135万円以下」とは、会社員やアルバイトで言うと「年収200万円以下」くらいの状態です。ただし、会社やアルバイトの給与以外にも収入がある場合は、それらも合わせて考えます。
なお、ここで言う「障害者・寡婦・ひとり親」は、それぞれ障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除の対象者と同じです。(障害者控除については本人の場合のみ)
- 詳しい解説
- 地方税法24条5で、「障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く。)」には道府県民税の所得割・均等割を課さないと定められている。また295条では、同様の者に市町村民税の所得割・均等割を課さないと定められている。よって、上記の該当者には所得割も均等割も課されない。
※ 東京都の都民税・特別区民税についても同じ規定が適用される
③ 所得が市区町村の「非課税限度額」以下の人
前年の「合計所得金額」が、市区町村の条例で定める「非課税限度額」以下の人は、住民税(所得割・均等割)が非課税になります。
この非課税限度額は、基本的に「級地区分」によって異なります。おおまかにいうと、物価が高い地域から1級地・2級地・3級地と定められています。(東京23区・川崎市・さいたま市・福岡市などが1級地に当たる)
>> お住まいの地域の級地を確認 – 厚生労働省
住民税の非課税限度額
| 扶養なし | 扶養あり | |
|---|---|---|
| 1級地 | 45万円 | 35万円 × (1 + 養う人数) + 31万円 |
| 2級地 | 41.5万円 | 31.5万円 × (1 + 養う人数) + 28.9万円 |
| 3級地 | 38万円 | 28万円 × (1 + 養う人数) + 26.8万円 |
※ 地域によってはこの通りでない場合もある
表中の「扶養なし・あり」は、扶養親族と同一生計配偶者の有無を指しています。養っている親族が多い人ほど、住民税が非課税になりやすいです。
- 詳しい解説
- 厳密に言うと、市町村が定めているのは“市町村民税の均等割の非課税限度額”だが、地方税法24条5-3で「市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては…(中略)…道府県民税の均等割を課することができない」とされているため、道府県民税の均等割も同じ基準で非課税になると言える。なお、地方税法施行令47条3で、市町村民税の均等割の非課税限度額の上限が定められており、これが所得割の非課税限度額を超えることはないため、この基準で均等割が非課税になる人は、必ず所得割も非課税になる。
※ 東京都の都民税・特別区民税についても同じ規定が適用される
【計算例】住民税が非課税になるケース
たとえば、1級地にあたる東京23区内に住んでいて、配偶者や子供を養っていなければ、非課税限度額は45万円です。前年の合計所得金額が45万円以下(給与で言うと「年収100万円以下」)なら、住民税(所得割・均等割)を課されません。
同じく東京23区内で、配偶者と子供1人を養っている場合、非課税限度額は以下の計算式で算出します。
- 35万円 × (1 + 2) + 31万円 = 136万円
この場合、前年の合計所得金額が136万円以下なら、住民税(所得割・均等割)が非課税になるわけです。合計所得金額136万円以下とは、給与収入だけで言うとおよそ「年収206万円以下」です。
所得割だけ非課税になるケース
前年の「総所得金額等」が下記の金額以下ならば、級地に関係なく、少なくとも住民税の「所得割」は非課税になります(「総所得金額等」はひとまず所得のことだと考えてOK)。これは地域によらず、全国一律のルールです。
住民税の「所得割」が非課税になるボーダーライン
| 扶養なし | 45万円 |
|---|---|
| 扶養あり* | 35万円 × (1 + 養う人数) + 42万円 |
実際はもう少し所得があっても、所得控除や税額控除によって、結果的に所得割がゼロになる可能性があります。
- 詳しい解説
- 地方税法の附則3条3-1,4で、前年の総所得金額等が「三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)以下」の人には、道府県民税・市町村民税の所得割を課さないと定められている。
※ 東京都の都民税・特別区民税についても同じ規定が適用される
【計算例】所得割が非課税になるケース
配偶者や子供を養っていないなら、ボーダーラインは一律45万円です。前年の総所得金額等が45万円以下なら、所得割は課されません。
一方、たとえば配偶者と子供1人を養っている場合、所得割が非課税になるラインは以下の式で算出します。
- 35万円 × (1 + 2) + 42万円 = 147万円
この場合、前年の総所得金額等が147万円以下なら、所得割が非課税になるということです。給与以外に収入がなければ、年収がおよそ221万円以下だと、総所得金額等は147万円以下におさまります。
【おまけ】住民税非課税の人を対象とした制度
所得割・均等割の両方が非課税の人(前述の①~③に該当する人)は、以下のような優遇・支援の対象になります。ちなみに「住民税非課税世帯」とは、全員が住民税非課税の世帯のことです。
住民税非課税の人を対象とした主な制度
| 高額療養費 の軽減 |
高額な医療費の一部が支給される制度(高額療養費制度)において、自己負担額の上限が低くなる |
|---|---|
| 介護保険料 の軽減 |
65歳以上で年金収入が一定以下の場合に、介護保険料が軽減される |
| 0~2歳の 保育無償化 |
住民税非課税世帯の子供は、0歳から一部の保育施設の利用料が無料になる |
| 高等教育の 修学支援 |
住民税非課税世帯の学生は、大学の授業料などの減免を受けられる (非課税でなくても一部の支援は受けられる) |
| NHK受信料 の免除 |
障害者のいる住民税非課税世帯などは、NHKの受信料が全額免除される |
※ このほか、自治体が独自に行う支援制度の対象になる場合もある
国民年金・国民健康保険の保険料も軽減される?
国民年金と国保の保険料は、住民税の非課税と直接的には関係ありません。ただ、住民税が非課税になるほど所得が低い人なら、ほぼ確実に保険料が減額 or 免除されます。
なお、会社員などが加入する厚生年金や健康保険の場合は、住民税が非課税でも、特別に保険料が減免されることはありません。ただ、健康保険組合に加入している場合は、組合によってルールが異なります。
まとめ
以下のどれかに該当する人は、住民税の所得割・均等割の両方が非課税になります。一般的に「住民税非課税」と言うと、このような状態を指します。
- 生活保護の対象者のうち「生活扶助」を受けている人
- 合計所得金額が135万円以下の未成年者、障害者、寡婦、ひとり親
- 合計所得金額が市区町村の定める「非課税限度額」以下の人
※ 退職金を受け取った場合などは、一部が課されることもある
③の「非課税限度額」は、市区町村の級地区分によっても異なります。基本的に、物価が高い方から1級地・2級地・3級地となっています。
住民税の非課税限度額
| 扶養なし | 扶養あり | |
|---|---|---|
| 1級地 | 45万円 | 35万円 × (1 + 養う人数) + 31万円 |
| 2級地 | 41.5万円 | 31.5万円 × (1 + 養う人数) + 28.9万円 |
| 3級地 | 38万円 | 28万円 × (1 + 養う人数) + 26.8万円 |
※ 地域によってはこの通りでない場合もある
①~③に該当しない場合であっても、前年の総所得金額等が下記の金額以下なら、少なくとも住民税の「所得割」は非課税になります。
所得割が非課税になるボーダーライン
| 扶養なし | 45万円 |
|---|---|
| 扶養あり* | 35万円 × (1 + 養う人数) + 42万円 |
ちなみに、これをちょっと超えても、所得控除や税額控除で所得割がゼロになる場合もあります。ただし、住民税非課税の人を対象とした支援制度などを利用できるのは、主に「所得割も均等割も非課税の人」なので注意しましょう。