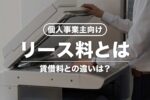個人事業主・フリーランス向けに、「荷造運賃」の勘定科目についてまとめました。仕訳方法や、通信費・消耗品費との違いなどを解説します。
目次
個人事業主の荷造運賃とは?
- 商品や製品を顧客に届けるための費用
- 国内の輸送なら、消費税区分は基本的に「課税」
- 企業によっては「発送費」や「運賃」などの科目を使っている場合も
商品を顧客に届けるのにかかった費用は、「荷造運賃」の勘定科目で必要経費に計上できます。具体的には、下記のような梱包費用や輸送費用が該当します。
荷造運賃の具体例
| 梱包に関わる費用 | 輸送に関わる費用 |
|---|---|
| ・ダンボール箱、木箱、包装紙 ・ガムテープ、のり、ひも ・緩衝材(気泡シートなど) ・外部委託費用 ・検査手数料 |
・郵便小包、レターパック ・書留 ・宅配便 ・ガソリン代 ・船舶、鉄道、航空機などの輸送費 |
ちなみに、梱包資材の購入費用は「消耗品費」として処理してもOKです。また、郵便代などは「通信費」として処理しても問題ありません。(このあたりの使い分けについては、記事の後半で詳しく解説します)
「発送費」や「運賃」との違いは?
荷造運賃の代わりに、「発送費」や「運賃」などの勘定科目を使っている企業もあります。この勘定科目じゃないとダメ!と決まっているわけではないので、それでも特に問題はありません。ただ、個人事業主は決算書に「荷造運賃」という項目があるので、「荷造運賃」の科目を使うのが無難です。
勘定科目を追加してもOK?任意で科目作成するときの注意点など
荷造運賃の消費税区分
| 取引内容 | 税区分 |
|---|---|
| 通常の国内輸送 | 課税 |
| 輸出品の国内輸送 | 課税 |
| 保税地域内*の輸送 | 免税 |
| 税関通過後の海外輸送 | 免税 |
| 国際・国際宅配便 | 免税 |
| 海外から海外への輸送 | 不課税 |
* 保税地域とは、輸出入を行う際に貨物を留置きする場所のこと
国内で荷物を輸送する場合、その運賃の消費税区分は「課税」です。一方、日本から海外へ発送する場合の運賃は「免税」です。なお、日本を経由しない、海外から海外への輸送費は「不課税」になります。
荷造運賃の仕訳方法【複式簿記・単式簿記】
宅配便で商品を発送し、送料2,200円を現金で支払った場合は、下記のように記帳します。
複式簿記の記帳例
| 日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 20XX年5月20日 | 荷造運賃 2,200 | 現金 2,200 | 〇〇運輸 配送料 |
55万円・65万円の青色申告特別控除を狙う場合は、上記のように「複式簿記」で記帳します。それ以外の場合は、下記のような「単式簿記」でOKです。
単式簿記の記帳例
| 日付 | 荷造運賃 | 摘要 |
|---|---|---|
| 20XX年5月20日 | 2,200 | 〇〇運輸 配送料 |
単式簿記の場合、日付・金額・内容などの取引実態が正確に記帳されていれば、帳簿の様式に定めはありません。上記は一例として、経費欄がある様式を使用しています。
他の勘定科目との使い分け
結論からいうと、帳簿付けのしかたに一貫性があれば、勘定科目はどれを使っても大きな問題はありません。個人事業主の場合、どの勘定科目も最終的には「必要経費」としてまとめられるので、細かな使い分けはあまり気にしなくてもOKです。
荷造運賃と「通信費」の違い
商品の発送にかかる費用は「荷造運賃」に該当します。一方、カタログの発送費用など、商品・製品以外のものを発送する際は「通信費」を使うのが一般的です。
事業者のなかには、大きな荷物を送る時は「荷造運賃」、小さな書類などは「通信費」というように、サイズや送付物の内容によって使い分ける場合もあります。それでも使い分けの基準が常に一貫していれば問題はありません。
個人事業主の通信費とは?仕訳方法や家事按分について
荷造運賃と「消耗品費」の違い
ガムテープのように、使途が梱包のみに限定されない、汎用性が高い物品を経費計上するときには、「消耗品費」の勘定科目を使うのが適当です。反対に、商品梱包専用のダンボールを用意する場合などは「荷造運賃」に計上しても構いません。
個人事業主の消耗品費とは?年間いくらまで?
荷造運賃と「支払手数料」の違い
このように「支払手数料」は、各種サービスの利用に付随して発生する費用をまとめて処理できるのが特徴です。一方、商品の発送に関わる郵便手数料や検査手数料などは、発送業務に直接結びつく費用なので、支払手数料ではなく「荷造運賃」で処理するのが適切でしょう。
【個人事業主向け】支払手数料とは?消費税区分・仕訳方法など
荷造運賃と「仕入」の違い
販売時だけでなく、商品や製品材料を仕入れる際にも、送料を負担する場合があります。これは、販売した商品を届けるための費用ではないため、荷造運賃ではなく「仕入」の勘定科目で処理するのが普通です。
ただし、仕入れる際の送料であっても、少額であったり頻度が少なかったり、重要性が低い取引については、荷造運賃として処理してもOKです。
年内に使い切らなかった梱包材は「貯蔵品」へ!
年末の時点で、年内に購入した梱包材などが大量に余っている場合は、それらの購入金額を「荷造運賃」から「貯蔵品」へ振り替えましょう。ガムテープや段ボールなどの物品は、使用して初めて経費として認識されるためです。
未使用の資材が大量に余っている年は、この処理をしないと、税務署から「やけに必要経費が多いな」と目をつけられる原因になってしまいます。このように振り替えることで、実際に使った分だけを経費計上し、未使用分は資産として翌年に繰り越せます。
荷造運賃に関する疑問まとめ【Q&A】
- 荷造運賃と通信費の使い分けは?
- 荷造運賃と通信費は、「発送するものが商品かどうか」で使い分けるのがわかりやすいです。 商品や製品を送るときの送料や梱包費は「荷造運賃」に含めます。一方、パンフレットや請求書などを送る場合の費用は「通信費」に含めるのが一般的です。
- 荷造運賃と消耗品費の使い分けは?
- 「発送のためだけに必要な費用かどうか」で判断するのがおすすめです。 ダンボールやガムテープのように発送専用に買ったものは「荷造運賃」に計上できますが、事務作業にも使える文房具やテープ類は「消耗品費」で処理するほうが自然です。
- 「発送費」や「運賃」の勘定科目でもいい?
- 個人事業主の場合は、決算書にも載っている「荷造運賃」を使うのが無難です。 ただ、法律で細かく定められているわけではないので、「同じ内容の取引を一貫した科目で処理する」というルールが守られていれば「発送費」や「運賃」を使っても問題ありません。
- 年末に梱包材が余ったらどう処理する?
- 年内に使わなかった分は「荷造運賃」ではなく「貯蔵品」として資産計上します。 理由は、梱包材は実際に使用して初めて費用と認識されるからです。この振替処理を行うことで、本当に使った分だけを「その年の経費」として計上できます。
まとめ
「荷造運賃」は、必要経費の勘定科目の1つで、商品や製品を顧客に届ける際の費用を処理するのに使います。運送会社に支払う送料を仕訳するのに使われることが多いでしょう.
荷造運賃の重要ポイント
- 荷造運賃は商品や製品の発送にかかる費用のこと
- 国内への送料は、消費税区分が「課税」
- 海外への送料は、消費税区分が「免税」
- 商品以外のものを送るときは「通信費」が妥当
- 商品の発送以外にもよく使用する物品は「消耗品費」が妥当
- 仕入れの送料は「仕入」に含めるのが妥当
- 年末に梱包材などが大量に余っていたら「貯蔵品」に振り替える
「発送するものが商品・製品かどうか」が、荷造運賃として計上するかどうかを判断する際の大きなポイントです。
荷造運賃の具体例
| 梱包に関わる費用 | 輸送に関わる費用 |
|---|---|
| ・ダンボール箱、木箱、包装紙 ・ガムテープ、のり、ひも ・緩衝材(気泡シートなど) ・外部委託費用 ・検査手数料 |
・郵便小包、レターパック ・書留 ・宅配便 ・ガソリン代 ・船舶、鉄道、航空機などの輸送費 |
業態によっては、上表に記載された費用であっても、他の科目を使ったほうがよいケースもあります。税額計算で問題が発生しないよう記帳することと、一貫性のある記帳を行うことが大切です。