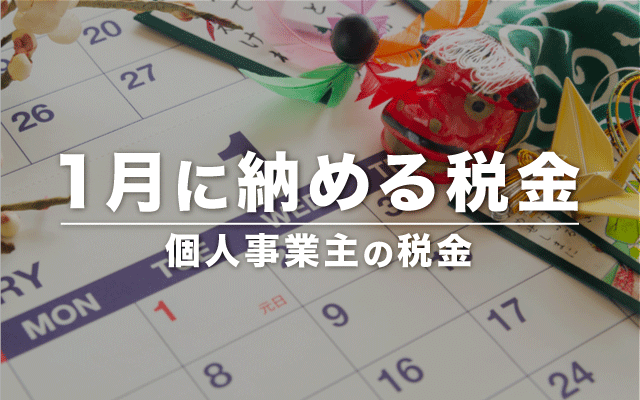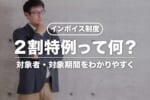個人事業主が1月に納める主な税金は、住民税の第四期分です。従業員を雇っている事業主は、源泉所得税(納期の特例分)も忘れずに納付しましょう。
目次
1月に納める税金には何がある?
個人事業主が1月に納める税金で主なものは、住民税の第四期分です。
個人事業主が1月に納付する主な税金
| 対象となる事業主 | 期限日 | |
|---|---|---|
| 住民税 (第四期分) | ほとんどの人が対象 (一括納付の場合は納付済み) |
1月末日* |
*納付期限日が土日祝日であれば翌平日へ繰越
住民税については、前年の6月中旬ごろに、市区町村の役所から納付書が送られてきているはずです。納付書には税額が記載してあるので、これにしたがって納付を済ませましょう。ちなみに口座振替の場合、納付期限日に引き落としがかかります。
社会保険料は毎月納付する
個人事業主は、「国民年金」や「国民健康保険」といった社会保険料も、毎月自分で納付しなくてはなりません。国民年金は毎年4月上旬ごろに、国保は毎年6月~7月ごろに、1年分の納付書が届きます。届いた納付書には金額や期限日が記載してあるので、これにしたがって納付しましょう。
個人事業主の社会保険料について詳しく
住民税(第四期分)
住民税の納付方法には、一括払いと分割払い(年4回)があります。分割で納付する人は、1月末までに第四期分を納付しましょう。
住民税の納付期限日
| 第一期分 | 第二期分 | 第三期分 | 第四期分 |
|---|---|---|---|
| 6月末日 | 8月末日 | 10月末日 | 1月末日 |
納付期限日が土日祝日であれば翌平日へ繰越
住民税の納付額は、前年分の確定申告の内容をもとに算出されています。税額は地域によりますが、だいたいは「所得の10% + 約5,000円」です。一括・分割どちらで納めても、トータルの納付額は変わりません。
納付方法
住民税は、毎年6月ごろに1年分の納付書がまとめて送られてきます。この納付書をつかって、コンビニ等の窓口で納付するのが一般的です。
また最近は、クレジットカード決済やスマホ決済(PayPay・LINE Payなど)に対応する自治体も増えてきています。このあたりの対応状況は地域によって異なるので、自治体のウェブサイトなどで事前に確認しておきましょう。
住民税の納付方法について詳しく
従業員分の源泉所得税(納期の特例分)も忘れずに
個人事業でも従業員を雇っていて「源泉所得税の納期の特例」を利用している人は、源泉徴収した前年7月~12月分の所得税を「1月20日」までに納付しましょう(誰も雇わず一人で働いているフリーランスは、誰かの源泉徴収をする必要はありません)。
源泉所得税(納期の特例分)の納付期限日
| 1月~6月分 | 7月~12月分 |
|---|---|
| 7月10日 | 1月20日 |
期限日が土日祝日であれば翌平日へ繰越
- 「源泉所得税の納期の特例」とは?
- 「源泉所得税の納期の特例」は、一定の要件を満たすことで、従業員などから源泉徴収した所得税を、年2回にまとめて納付できるという制度。通常だと、源泉所得税は毎月納付しなくてはならないので、この特例を利用するとかなり手間を省ける。
源泉所得税の納期の特例
| 対象者 | 給与の支給人数が常時10人以下の源泉徴収義務者 |
|---|---|
| 納付期限日* |
|
| 対象となる 源泉所得税 |
|
*土日祝の場合は翌平日に繰越
源泉所得税の納期の特例を利用するには、事前に税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。なお、外注先に支払った報酬などにかかる源泉所得税は、この特例の対象外です。
還付申告は1月から受付開始
還付申告の受付期間は、対象となる年の翌年1月1日から5年間です。事前に納めすぎた税金を取り戻すための還付申告の受付期間は、確定申告期間とは異なるわけです。したがって、過去に申告し忘れた控除がある場合も、過去5年分までなら遡って還付申告ができます。
電子申告なら還付金が早めに振り込まれる
インターネットで還付申告(電子申告)をすれば、還付金を早めに受け取れます。通常は1ヶ月半くらいかかるところ、電子申告をした場合は、申請してから2~3週間程度で還付金を振り込んでもらえます。

電子申告の際は、マイナンバーカードで本人認証するのが基本です(マイナンバーカード方式)。あるいは、事前に税務署の窓口で「ID・パスワード方式」の手続きをしておけば、マイナンバーカードを持っていなくても電子申告が可能です。
マイナンバーカードの発行には1ヶ月~3ヶ月程度かかるので、すぐに電子申告をしたいという人は「ID・パスワード方式」がおすすめです。この方法なら、税務署での手続きが終わった直後から電子申告ができます。
2025年(令和7年)10月1日以降、e-TaxのID・パスワードは新規発行ができなくなる。これから新たにe-Taxを始める方は「マイナンバーカード方式」のみ利用可能。2025年9月30日以前にID・パスワードを発行済みの方は、当面は「ID・パスワード方式」での申告も引き続き利用できるが、将来的には利用できなくなる見込み。
電子申告の方法について詳しく
償却資産の申告は1月31日まで
固定資産税の対象となる資産は、大きく「土地・家屋」と「償却資産」に分けられます。このうち「償却資産」を所有している人は、固定資産税の申告が必要です。「土地・家屋」にかかる固定資産税は、そもそも自分で申告をする必要はありません。
1月1日時点で所有している償却資産があれば、その年の1月31日までに所轄の都道府県税事務所に申告しましょう。
所有する資産の課税標準額の合計が一定額を下回るなら、固定資産税はかかりません。この一定額のことを「免税点」といい、償却資産の場合は150万円に設定されています。ただし、課税標準額の合計が150万円未満でも、償却資産の申告自体は省略できません。
償却資産の具体例
- 高価なパソコン
- 業務用冷蔵庫
- 大型の看板
- 業務用のOA機器
※ いずれも事業で使用するものに限る
事業で使う償却資産の合計額が150万円以上なら、固定資産税を納めることになります。なお、乗用車やトラックは自動車税の対象となるため、ここで言う「償却資産」には含まれません。
提出書類
| 初めて申告する場合 | 前年に引き続き申告する場合 |
|---|---|
|
|
固定資産を申告する書類の提出先は、所轄の都道府県税事務所です。書類を窓口まで直接持参するか、郵送で提出しましょう。