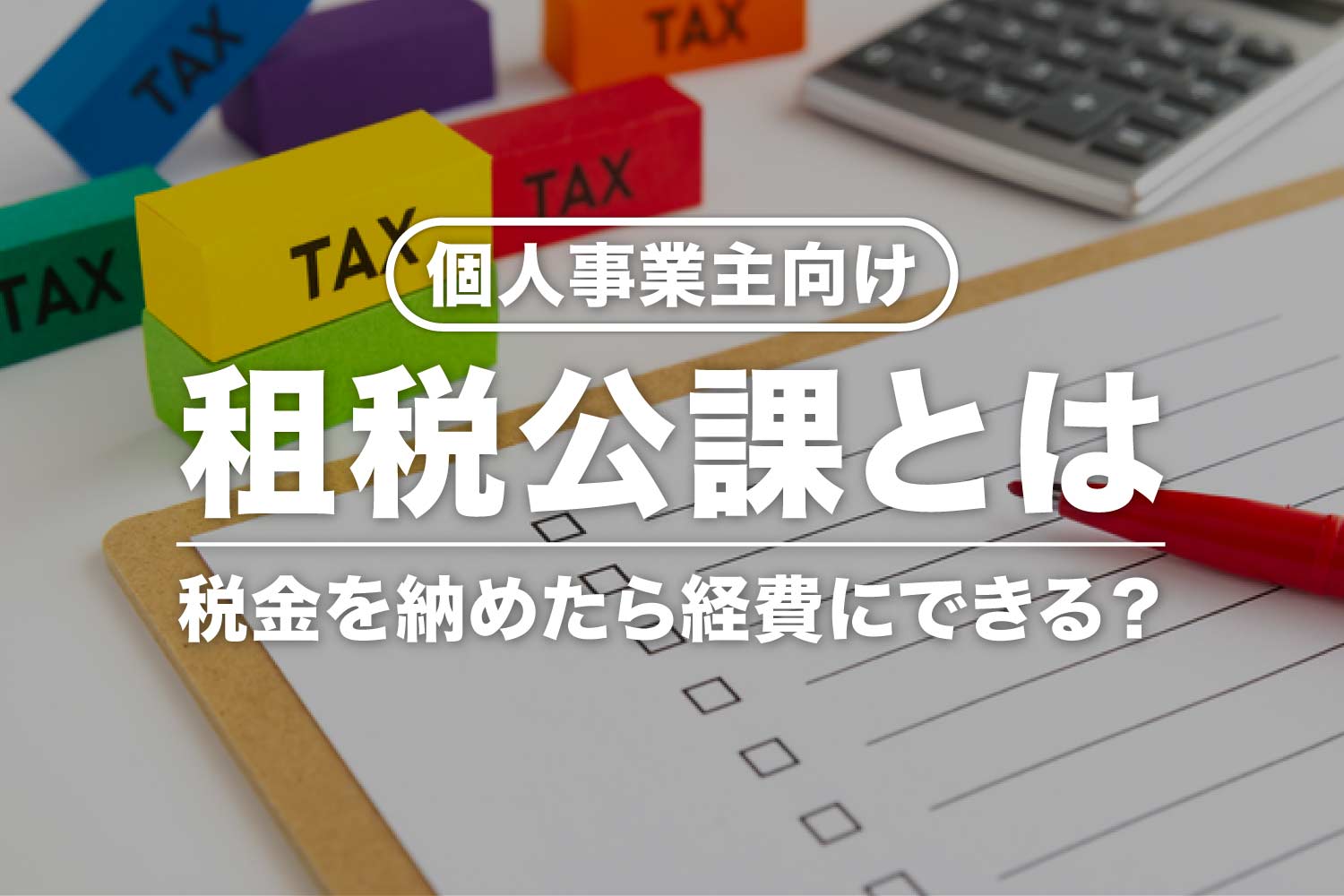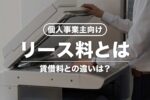個人事業主・フリーランス向けに、租税公課の記帳方法をわかりやすく解説します。経費にできる税金の見分け方や、仕訳例などをまとめました。
目次
個人事業主の租税公課とは【経費にできる税金一覧】
「租税公課」は、税金や公的な金銭負担を経費計上するための勘定科目です。下記のような費用は、租税公課の勘定科目で必要経費に計上できます。
租税公課として経費計上できる費用
- 個人事業税
- 固定資産税
- 自動車税
- 収入印紙代
- 商工会議所会費
- 利子税
一方、「個人に対してかかる税金」や「懲罰的に課される金銭負担」は経費に計上できません。これらを租税公課として帳簿付けするのはNGです。
経費計上できない税金など
- 所得税
- 住民税
- 相続税
- 贈与税
- 私用の自動車にかかる税金
- 事業所を兼ねない自宅にかかる税金
- 延滞税・加算税
- 罰金・科料・過料
- 交通反則金
これらを納める時は、基本的になにも記帳しません。ただし、これらの費用を事業用の資金から支払った場合は「事業主貸」という勘定科目で仕訳しましょう。
租税公課の消費税区分
租税公課の消費税区分は、基本的に「不課税」か「非課税」です。どちらも「消費税がかからない」という意味では同じですが、消費税の納付義務があるか判定したり、消費税の納税額を計算したりするときに違いが出ます。
租税公課の消費税区分(主な例)
| 不課税 | 非課税 |
|---|---|
|
|
>> 消費税の課税・非課税って何? – 個人事業の消費税入門
税金は消費税の対象にならないので「不課税」です。商工会議所の会費なども同様に「不課税」です。収入印紙などは、印紙税などを納める目的であっても、金券と同じ扱いで「非課税」です。
なお、郵便局やコンビニではなく、金券ショップなどで収入印紙を購入した場合は、通常の商取引になるので消費税がかかります。
租税公課の仕訳例
個人事業主は開業届を提出する際など、本人確認に住民票を使う場合があり、これは経費になります。以下の記帳例では、市役所で住民票発行の手続きをして、手数料300円を現金で支払ったとします。
複式簿記の記帳方法
| 日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 20XX年5月20日 | 租税公課 300 | 現金 300 | 住民票発行手数料 |
青色申告65万円・55万円控除を狙う事業者は、このように複式簿記で帳簿づけをしなければなりません。それ以外の事業者は、借方・貸方に仕訳する必要はなく、単式簿記で構いません。たとえば、次のように記帳します。
単式簿記の記帳方法
| 日付 | 租税公課 | 摘要 |
|---|---|---|
| 20XX年5月20日 | 300 | 住民票発行手数料 |
租税公課は家事按分が必要?
事業用とプライベート用の両方で使っている自宅や自動車の場合、購入や維持にかかる費用について、事業用に使っている割合だけ経費計上することができます。これを家事按分といいます。
たとえば、自動車のガソリン代も、事業でも利用する場合は家事按分し、一部を経費にできます。これと同じように、自動車にかかる税金も家事按分できます。
家事按分の割合は、合理的な決め方をする必要があります。自動車については、以下の3つがメジャーな基準です。
- 利用時間
- 利用回数
- 走行距離
自動車の場合、平日と週末で使い方が変わることも多いので、一週間単位で考えてもよいです。事業用と私用の利用時間が、一週間のうち5時間ずつだとすると、家事按分の割合は50%になります。

税金を分納する場合はいつ経費計上する?
税金を分納する場合の記帳方法には、大きく2パターンあります。納税通知書が届いたときに全額経費計上してしまうか、納税の度に記帳してゆくかです。いずれにせよ、大抵は同じ年の経費になるので、基本的にはどちらでも大した違いはありません。
ただし、固定資産税の場合だけ、計上タイミングが重要になることがあります。固定資産税は4回払いが基本ですが、4回目の納付が翌年の2月となっており、年をまたぎます。
固定資産税は、納税通知が来た時点で全額経費にできるので、4回目の分も当年の経費に含めてOKです。あるいは、納税の度に記帳していき、4回目の納税分だけを翌年の経費に計上するという方法でも構いません。
固定資産税の経費計上タイミング

どちらにするかは事業者の自由ですが、一度決めたらその後もずっと同じ方法で記帳してください。
租税公課に関する疑問まとめ【Q&A】
- 個人事業主の税金はすべて租税公課になる?
- すべての税金が租税公課になるわけではありません。たとえば、所得税や住民税など、個人にかかる税金は経費にできません。
- 必要経費にできる税金はどれ?
- 個人事業税、固定資産税、自動車税、自動車重量税、印紙税などは、「租税公課」の勘定科目で必要経費に計上できます。事業に必要な税金であることが条件です。
- 必要経費にできない税金は?
- 所得税、住民税、延滞税、加算税などは必要経費にできません。これらは事業の経費ではなく、個人の負担とみなされます。
- 消費税を納付したら租税公課で帳簿付けできる?
- 納めた消費税の仕訳方法は、「税込経理方式」と「税抜経理方式」のどちらで帳簿づけをしているかによって異なります。税込経理方式で帳簿付けしている場合は、「租税公課」の勘定科目を使います。
個人事業主の消費税について詳しく
- 国民健康保険料は租税公課に含まれる?
- 国民年金や国民健康保険の保険料は租税公課には含まれません。これは必要経費ではなく、確定申告で社会保険料控除の対象となります。
まとめ
帳簿づけにおいては、税金や公的な金銭負担のうち、経費計上できるものを租税公課といいます。固定資産税や自動車税のように、事業用と私用の両方で使っているものにかかる税金については、家事按分して一部を経費計上することができます。
租税公課の重要ポイント
- 基本的に租税公課には消費税がかからない
- 金券ショップで収入印紙を買ったときなどは消費税がかかる
- 税金を納付する場合は消費税「不課税」
- 商工会議所の会費なども「不課税」
- 収入印紙代などは消費税「非課税」
- 個人にかかる所得税や住民税は、租税公課として経費にできない
- 懲罰的に支払う延滞税なども、租税公課として経費にできない
- 固定資産税の分納4回目は、1~3回目と同じ年の経費にしてもよい
「経費にできる税金」「経費にできない税金」の代表例は、以下の通りです。
| 経費にできる税金など | 経費にできない税金など |
|---|---|
|
|
特に所得税と住民税は、ほとんどの事業主が納める税金ですが、これらは租税公課として経費にすることはできないので注意しましょう。たとえば、事業用口座などから所得税を振替納付した場合は「事業主貸」の勘定科目で仕訳すればOKです。